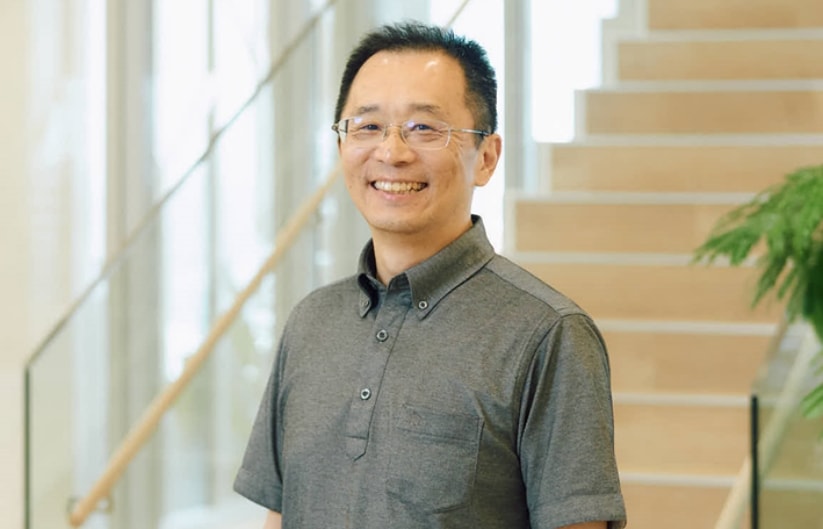
運用部運用開発グループ
グループヘッド
廣瀨 勇秀
生成AIを活用した運用高度化
生成AI活用に関しては、「独自の情報蓄積」と「技術を活用した運用」を組み合わせることで、運用フロントとして「目指す姿」を実現し、生存競争で勝ち残るために常に新たな挑戦を続けます。
生成AIが与えたインパクト
私が学生の時、ウェブアクセス・ランキングのロジック開発はホットなトピックでした。海外ではAltaVistaなどの全文検索エンジンが王道だった頃です。国内では千里眼やGooというロボット型の検索エンジンはあったものの、まだ登録型の検索エンジンが主流でした。しかし、どの検索ツールも表示結果は利用者の感覚には合いませんでした。この中、Googleがランダム・サーファー・モデルを開発し、検索結果表示に革新を起こしました。そして今では、「グーグル先生」に何でも尋ねる時代となりました。生成AIでも『「AI殿」に何でも依頼』する時代の到来です。ウェブや「グーグル先生」のいない世界を想像できないように、生成AIを利用できない世界は想像できなくなるでしょう。道具とはそういうものだと感じます。
今後起こりうる生成AI活用競争とは
企業における生成AI活用は3つのステップを経ると考えています。
ステップ1は、単純な利用です。会社には多くの内部情報があります。社内専用の生成AIを作成し、情報流出を防止する形で利用を開始します。しかし、この段階では、差別化は「利用しているか・いないか」だけです。
ステップ2では、RAG(社内情報を参照する仕組み)を用いた生成AIが使われます。社内ノウハウと生成AIの活用によって企業間の差別化が始まります。現在、多くの会社はこのステップの開発に取り組んでいると思います。
そして、ステップ3では、社内情報を用いてトレーニングした本格的な独自AIの競争が展開されます。ステップ2では情報を参照するに過ぎませんが、生成AI自体に知識を埋め込むのがこの段階です。最終的には、企業の人格の本質やノウハウそのものの継続を独自AIが担う世界も念頭に置くべきだと考えています。
運用フロントとして「目指す姿」
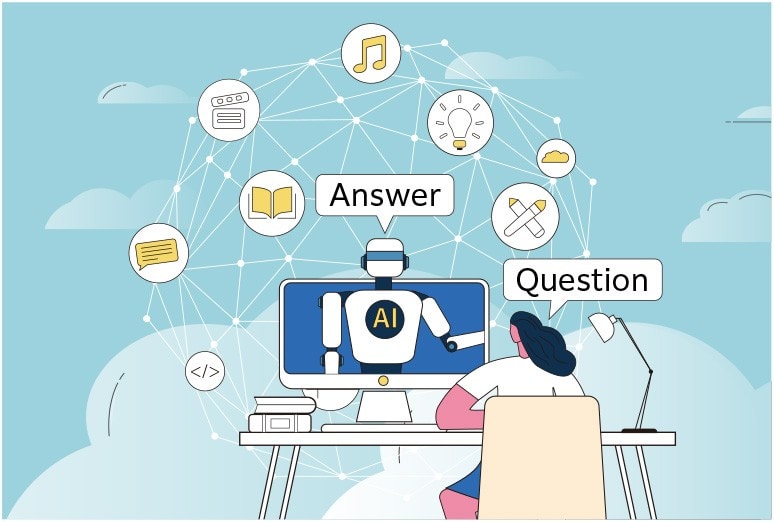
最近、Symbiotic(共生:AIと人間の共生)というキーワードを目にします。私たちは、運用現場で同じことを目指しています。社内ノウハウなどの「独自の情報」とAIなどの道具としての「技術の活用」の掛け算によって競争力を高めることが重要と考えています。「目指す姿」は、ファンドマネージャーがパフォーマンスにつなげる投資アイデアの創出に集中できるような、AIとの共生を運用現場で実現することです。
当社の取り組み状況
当社も「ステップ3」を視野に入れながら、当面は「ステップ2」に取り組んでいます。2023年度は「目指す姿」の実現を見据えた開発環境の整備に1つ1つ対応しました。生成AIはどの会社が革新的なツールを将来提供するかはわかりません。そのため、どこから革新的なサービスが出てきても対応できるように、プライベート・マルチクラウドの環境を整備しました。また、スノーフレークを用いたデータ分析基盤の構築も推進しています。スノーフレークは、ベンダー管理下のデータを直接利用できるため、社内のデータ管理負担を減らし、低コストのデータ処理が可能です。2024年度中には、独自情報や最新情報を活用したRAGを用いたサポートツールを提供する予定です。
キーワードは「独自情報の蓄積」と「技術による活用」の組み合わせです。「目指す姿」の実現とその中での生存競争で勝ち残るために、常に新しいことへの挑戦を続けていきたいと考えています。
ディスクレーマー・重要な注意事項はこちらをご覧ください

