2025年9月26日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
日銀の日本株ETF売却と懐事情
植田総裁の100年計画とバランスシート危機
日銀は9月18、19日の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めるとともに、保有する日本株上場投資信託(ETF)の売却開始を決定しました。政策金利の動向に気を取られていた市場は意表を突かれた格好となり、この発表直後に日経平均株価は一時約1,200円も急落しました。デフレ脱却を背景とした日銀による金融政策の正常化は、今回のETFの売却決定により新たな段階に入ったと言えそうですが、気がかりな点がないわけではありません。というのも、今回発表された日銀のETF売却ペースが「あまりに遅い」からです。
1. あまりに遅いETFの売却ペース
■日銀の植田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、保有する日本株ETFを年間約6,200億円(簿価で約3,300億円)のペースで売却することを決定したと発表しました。現在、日銀は時価で約70兆円の日本株ETFを保有しているとされており、今回発表されたペースで売却を進めた場合、植田総裁がコメントしたように、売却完了までに「100年かかる」こととなりそうです。
■日銀によるETF売却は以前より噂となっていましたが、市場の関心が「政策金利の動向」に集まっていたこともあって、発表のタイミングとしては市場の意表を突く結果となり、株式市場は一時的に急落する場面も見られました(図表1)。とはいえ、発表タイミング以上に違和感があるのは、その「あまりに遅い」ETFの売却ペースではないでしょうか。
■日銀はこれまで、非伝統的な金融緩和政策の一環として東証株価指数(TOPIX)と日経平均株価に連動するETFを購入してきましたが、その購入ペースは年間約6兆円に達し、コロナ禍で株価が乱高下した2020年には年間約12兆円も購入したと伝えられています。
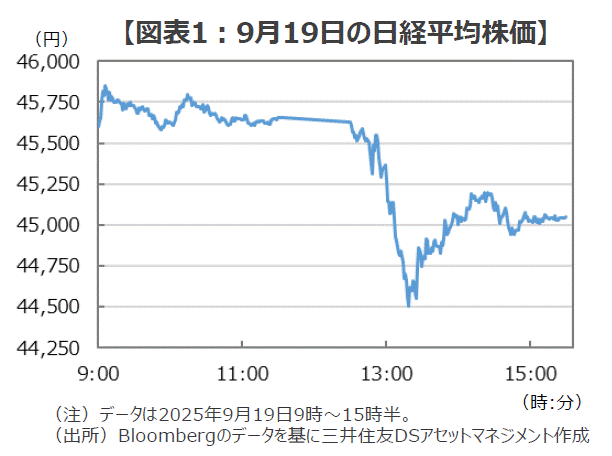
■一方、今回決定したETFの売却ペースは年間約6,200億円にとどまるため、ETF購入時の約10分の1のペースに留まる事となります。もちろん、株価が上昇して批判する人よりも、下がった場合に非難する人の方が多いでしょうから、日銀が慎重になるのも理解できます。とはいえ、昨今の株価の上昇から東京証券取引所に上場する企業の時価総額は2010年代の倍以上に増加し、1日の売買金額もかつての2~3兆円の水準から5兆円前後まで増えています。つまり、今回決まったETFの売却金額が日々の売買に占める「占有率」は、ETF購入時の「約20分の1」にとどまる計算になります。
■植田総裁はこうした売却ペースについて、「市場に影響を与えないため」としていますが、マーケットインパクトを避けるためにここまで売却ペースを落とす必要があるのでしょうか。
2. 金融引き締め局面の日銀の台所事情
■日銀のETF売却ペースが遅い背景について、やや斜に構えて勘ぐっていくと、2つのことに思い当たります。まず1点目は、ETFがもたらす分配金(配当金)の大きさです。現在、日銀は時価で約70兆円の日本株ETFを保有しているので、今期の東証プライム指数の予想配当利回り(約2.27%、9月19日時点)で試算すると、年間約1.6兆円の分配金を受け取る計算になります。ちなみに、2025年3月期の日銀の決算を見ると、売上に相当する経常収益は約4.6兆円、うち国債の利息収入が約2.1兆円、ETFの分配金が約1.4兆円となっており、ETFが日銀にとって重要な収益源となっていることが確認できます(図表2)。
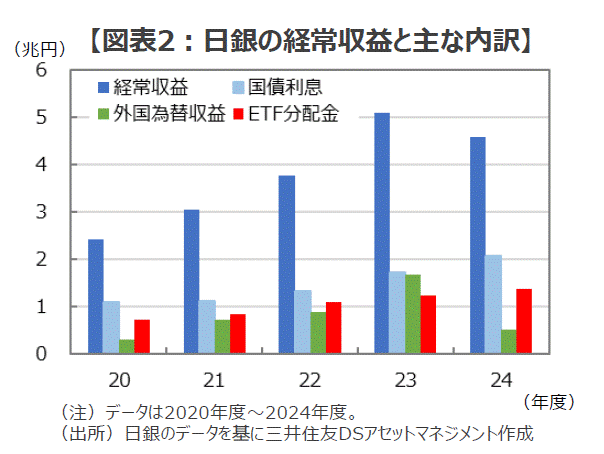
■日銀にとって何ともありがたいETFの分配金ですが、その重要性は今後さらに増すこととなりそうです。というのも、今後、日銀による利上げが続いた場合、民間金融機関から預かる法定預金準備額を超える当座預金(超過準備)に対する利息の支払いが急増する可能性が高いからです。
■この超過準備に対する「付利」は2025年3月期には前年度比約6.6倍の約1.3兆円に急増して(図表3)、日銀が保有する長期国債利回りをこの付利の金利が上回る逆ザヤが初めて生じたと伝えられています。日銀の企画局企画調整課は2024年12月に公表した日銀レビュー「日本銀行の財務と先行きの試算」の中で、バランスシートの縮小局面では、①当座預金(超過準備)が減少するにつれて支払利息が減少する一方、②保有国債は利回りの高い国債に順次入れ替わるため、③一時的に赤字が発生する可能性はあるが、いずれは収益が回復していく、としています。
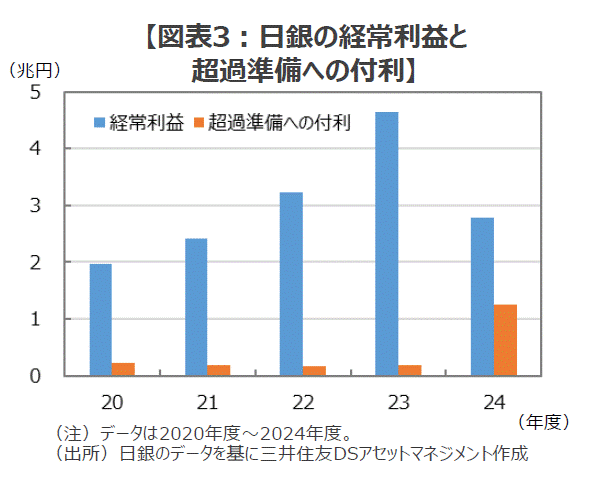
■とはいえ、このシミュレーションについては、日銀自身が認めるように、短期金利が1%を超えて大きく上昇し、利上げ局面の終盤によく見られるように長短金利差が縮小していくようなら、支払金利が大きく上昇する一方、受け取る債券からの利息が思ったように上がらないことで、収益的に厳しい状況になりかねません。
■ちなみに、この超過準備への「付利」は政策金利が0.75%へ引き上げられれば年間約3.8兆円、1%なら約5兆円超にまで増え、日銀の決算が赤字になりかねないとする試算も一部で伝えられています。今後、日銀は自ら行う利上げにより期間損益の大きな悪化を招きかねない状況にありますが、そんな日銀にとって約70兆円のETFがもたらす分配金は、財政悪化を防ぐバッファーとなっているのは間違いなさそうです。そう考えると、植田総裁がETFを相応のペースで売却していくことに躊躇するのも、致し方ないように思えてきます。
3. ETFが救う日銀のバランスシート危機
■日銀がETFの売却を急がない理由の2点目として考えられるのは、金利上昇局面における日銀のバランスシートの悪化をETFがカバーする働きを見せていることです。日銀は過去の大規模金融緩和の過程で積極的に国債を買い入れてきましたが、その残高は2025年3月末時点で約574兆円、含み損は約▲28.6兆円(前年比約▲19.2兆円の損益悪化)にも膨らんでいると伝えられています。
■こうした市場金利の上昇による国債の含み損の拡大をカバーしているのが、ETFの含み益です。日銀が保有するETFはTOPIXや日経平均と連動するインデックス投信なので、このところの日本株の上昇を受けて含み益が2025年3月末には約33兆円にまで拡大して、2年前の2023年3月末の約16兆円からほぼ倍増していると報じられています。
■資産運用の世界では、景気や金利の動向に対して異なった反応を見せる株式と国債の「併せ持ち」は、ポートフォリオ戦略の基本ですが、図らずも日銀のバランスシートにおいてもこの「オーソドックスな分散効果」が発揮された格好です。今後、日銀が利上げを継続し、国債買い入れを減額させていくことで長期金利が上昇していくなら、日銀の保有する国債が抱える含み損はさらに大きく膨張する可能性が高そうです。
■日銀としては、「国債を満期まで保有するので評価損益は問題にならない」というのが建前のようですが、時価で見たバランスシートの健全性が大きく損なわれるような事態になれば、中央銀行としての信認に響きかねないのも事実でしょう。そう考えると、景気と正の相関の傾向があり、インフレヘッジの効果も期待される日本株(ETF)は、利上げ局面における「日銀のバランスシート危機」を回避する上で、重要な役割を果たすことが期待できそうです。
■「非伝統的な金融緩和策」として少なからず批判もあったETFの購入ですが、デフレ脱却時の日銀のバランスシート危機を回避する「仕掛け」として組み込まれていたのであれば、その判断はまさに「慧眼(けいがん)」と言えそうです。そして、ETFの保有による「金利上昇へのヘッジ効果」は、今後、金融政策の正常化が本格化する局面で、その重要性はさらに増してくるように思われます。つまり、表立っては言いづらいものの、日銀による巨額のETF保有については、今後も強い経済的なインセンティブがあるように思われます。
■ちなみに、TOPIXは過去10年間に平均で年率約7.2%、日経平均は同約8.5%上昇してきました(2015年8月末~2025年8月末の幾何平均、配当除く)。もし、保守的に見て日本株が今後も年率5%のペースで上昇を続けると仮定すると、たとえ毎年6,200億円分のETFを売却しても、日銀の保有するETFの時価残高は増加を続け、現在約70兆円の残高は2030年には約86兆円、2035年には約106兆円に達する計算になります(図表4)。
■こうした数字を確認していくと、今回の日銀による発表は「ETFの売却宣言」というよりも、むしろ「保有宣言」にすら聞こえてきます。このため、日銀のETF売却による需給悪化懸念は杞憂であるばかりか、日銀の真意を取り違えた「早とちり」にすら思えてきます。
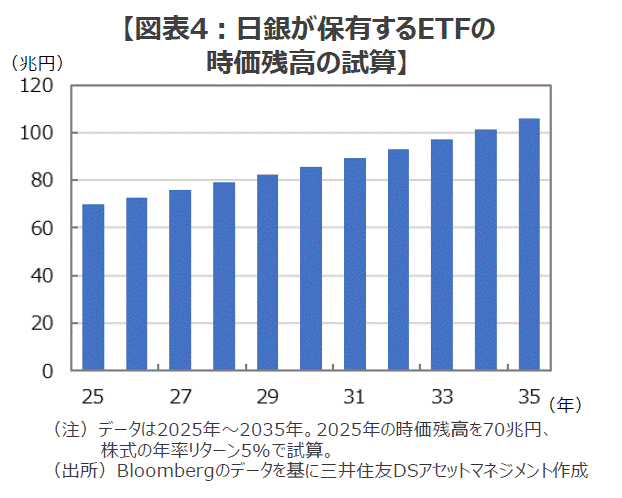
まとめに
日銀が先日の金融政策決定会合で決めた日本株ETFの売却方針は、金融政策正常化への大きな一歩と言えそうですが、売却ペースがあまりにスローである点が何とも気になります。
金融政策の正常化・バランスシートの縮小局面では、日銀は民間金融機関から預かる当座預金に高い利息を支払う必要が出てきますが、ETFの分配金(株式の配当金)がそうした日銀の苦境を緩和することとなりそうです。
市場金利が上昇すると日銀が保有する国債の含み損が急激に膨らむ可能性がありますが、株式市場の上昇によるETFの含み益拡大が、バランスシートの悪化を緩和することが期待できそうです。このため、日銀によるETFの積極的な売却はその財務リスクをむしろ高める可能性があるため、株式市場の需給悪化を招くほどのETF売却が行われる可能性が低いばかりでなく、期間損益やバランスシートに負荷がかかる利上げ局面では、積極的に保有を続ける方が合理的であるように思われます。



