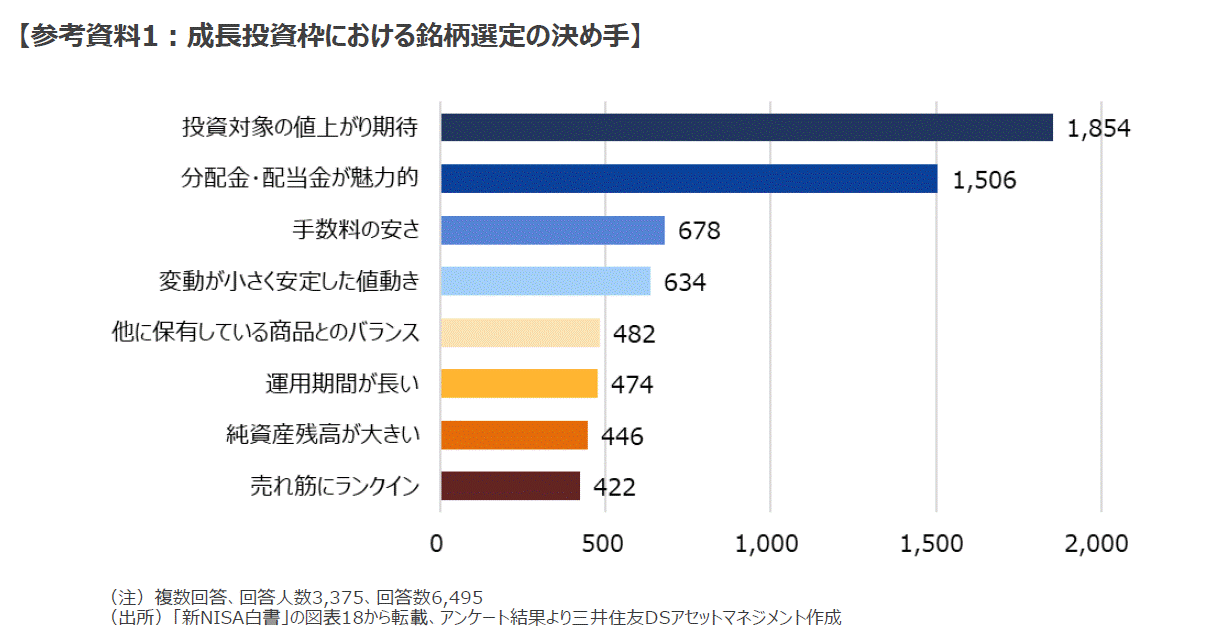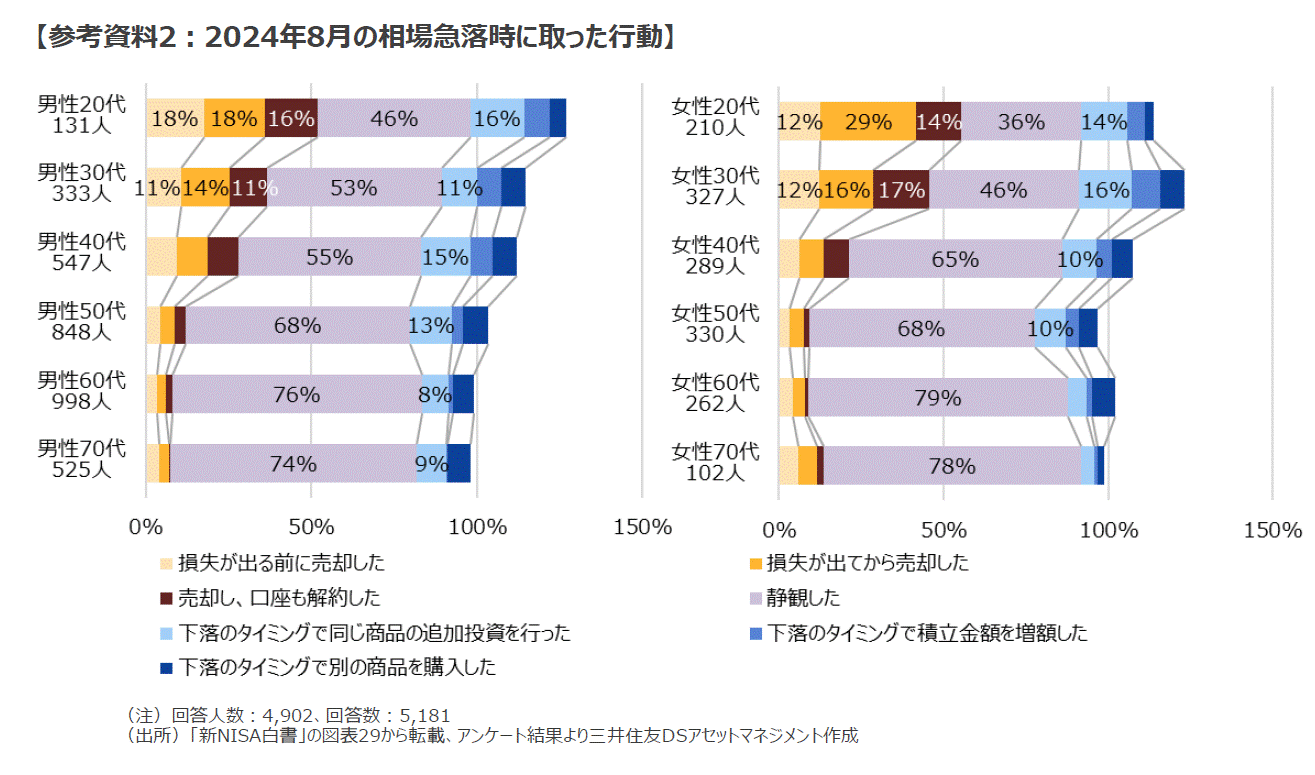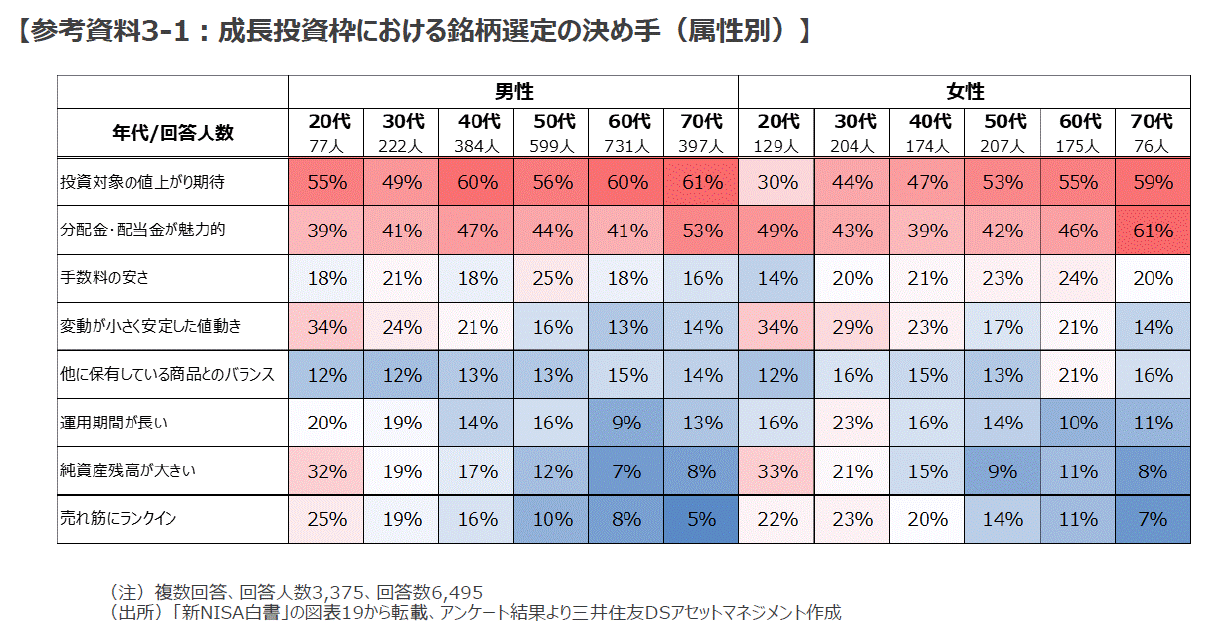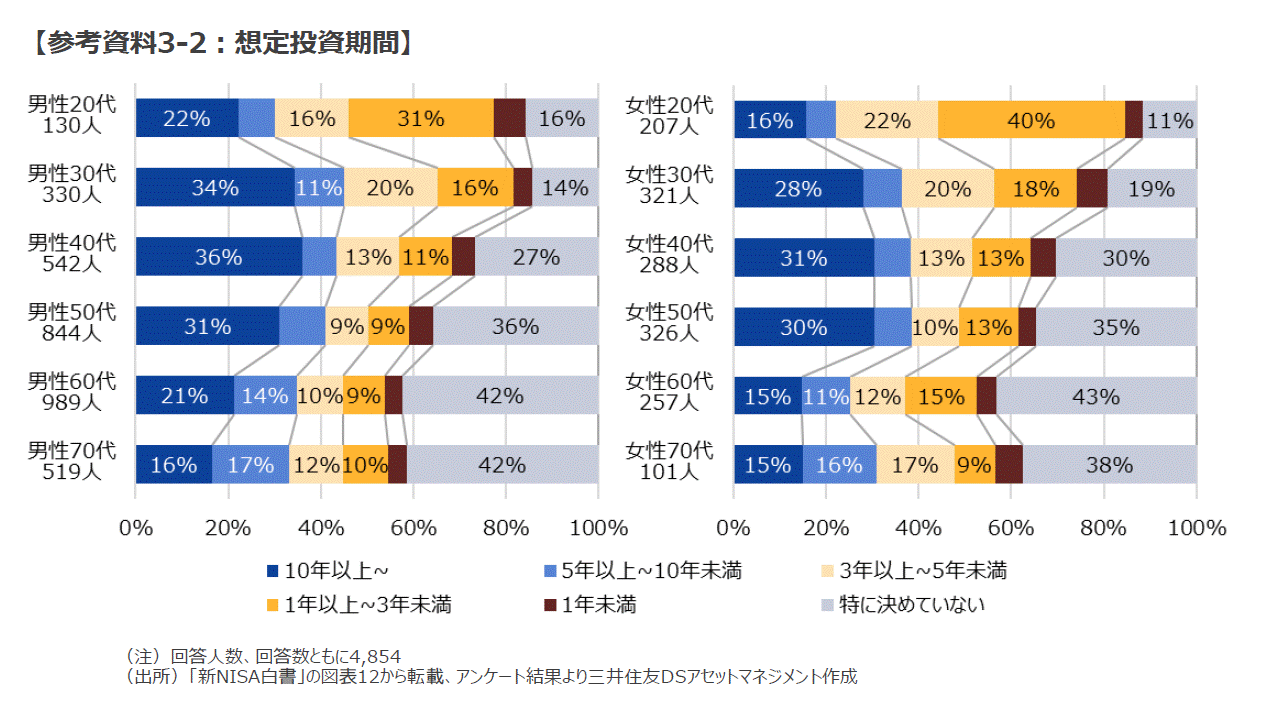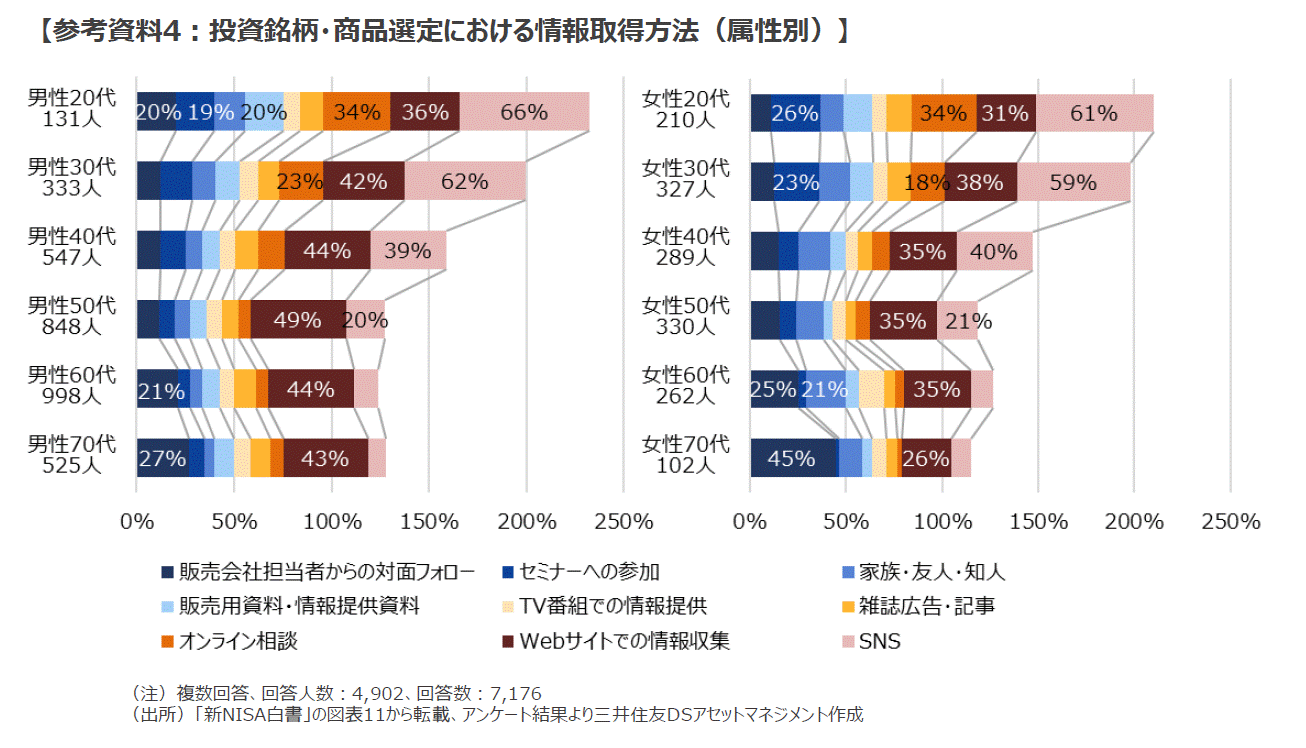2025年8月15日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
「新NISA白書」に見る投資の「ダークパターン」
個人投資家が陥りがちな「3つの残念な取引」
弊社では新NISA(少額投資非課税制度)がスタートして約1年が経過したタイミングで、個人投資家や金融機関を対象に大規模なアンケートを行い、その調査結果を「新NISA白書」として刊行しました。税制面でのメリットが大きい新NISAは今や個人投資家の資産運用には欠かせない存在となっていますが、この「新NISA白書」を読む中で気づかされるのは、ヒトの神経を逆なでする「相場という心理戦」との付き合いの難しさです。そこで今回は、「新NISA白書」から浮かび上がる投資家が陥りがちな「3つの残念な取引」と、その回避策について考えてみたいと思います。
1.心理的なクセや弱みに付け込む「ダークパターン」
■ネット通販で偶然気に入った商品を見つけた時に「品切れ間近」と購入を急かされたり、購入した際に知らないうちに定期購入を組まされてしまった、といったような経験がある方はいないでしょうか。そんな消費者を誤った行動に誘導する仕組みは「ダークパターン」と呼ばれ、被害額は日本だけでも年間1兆円を超えるそうです。
■ヒトの心理的なクセや弱みに付け込む「ダークパターン」はネットの世界だけでなく、リアルの世界でも数多く存在すると感じている方も少なくないでしょう。中でも、時々刻々と変化する価格がヒトの「興奮」、「落胆」、「恐怖」などの感情を掻き立てる相場の世界は、ヒトの心理的なクセや弱さが判断ミスを招く、広い意味での「ダークパターンの宝庫」と言えそうです。そして、投資家を残念な取引に引き込む「ダークパターン」が要注意なのは、ネット通販での変な買い物とは比べ物にならないほど、その経済的なダメージが大きくなる可能性が高いからです。
「新NISA白書」から浮かび上がる3つの「ダークパターン」
■弊社では新NISAについて投資家や金融機関を対象に大規模なアンケートを実施し、その結果をまとめて今年7月に「新NISA白書」を刊行しました。そして、この調査結果を読み解く中で気づかされたのは、少なくない投資家が「3つの残念な取引」をしてしまっている、という事実です。
■具体的には、①投資先を決める際の理由が「将来の値上がり期待」と「分配・配当金」に極端に偏っていること(巻末:参考資料1)、②「令和のブラックマンデー」と呼ばれた2024年8月の相場の急落局面で投資をあきらめてしまう人が意外に多かったこと(巻末:参考資料2)、そして、③若い世代ほど「想定している投資期間が短期」で、投資先の選択に「変動が小さく安定した値動き」を重視する傾向が強いこと(巻末:参考資料3-1、3-2)の3つです。こうした考え方や投資行動が「残念でならない」のは、いずれも投資のセオリーや常識的な考え方に反する、投資家の「ダークパターン」以外の何物でもないからです。
2.心理的なバイアスと「残念な取引」
■投資の際に将来の値上がりを期待するのは当たり前ですし、マーケットが悪化すれば冷静になるため「いったん投資を取りやめる方が良い」と考える人がいてもおかしくないでしょう。また、若い方々が投資に際して「目に見える短期的な利益」や「安定性」を求めるのは、コスパやタイパ(タイム・パフォーマンス)を重視するシビアな価値観を持つ彼らからすれば当然なのかもしれません。しかし、一見すると合理的なこうした考え方や振る舞いは、こと投資に関する限り、「合理的に間違える」結果となりかねない点には注意が必要でしょう。
「値上がり期待」と「高配当」で決めて何が悪い?
■投機的な短期売買を旨とするヘッジファンドなどを除けば、機関投資家と呼ばれる国内外のプロの投資家たちは、短期的な相場予測が極めて難しいことを骨身にしみて実感しているため、こうした相場見通しに基づいて投資先を大きく動かすことはほとんどありません。では、彼らが一体何をやっているのかと言えば、株や債券など様々な投資対象の長期的なリスクとリターンを慎重に検討した上で、値動きの異なる投資対象を組み合わせて、「リスク・リターン」の観点から有利なポートフォリオを長期間保有し続けることに徹しているのです。
■金融のプロの世界では様々なプレーヤーが高額の報酬で人を集め、プロ仕様の投資情報に大金を支払い、さらに、最新のAIや強力なコンピューターを使って市場を分析してしのぎを削っています。このため、個人投資家の皆さんが彼らに先んじて有望な投資先を発掘するのは並大抵ではないですし、「有望だ」として飛びついた投資先に既に大量の買いが入ってしまって割高になっている場合も少なくないでしょう。ましてや、SNSでインフルエンサーが拡散する「有望銘柄」や、物知り顔の知人が耳打ちする「早耳情報」を参考に売買しても、上手くいかないことが殆どではないでしょうか。
■また、株式の個別銘柄の選別に当たって「分配・配当金」を重視し過ぎるのも、あまり得策には思えません。というのも、配当利回りが高いからと言って投資家が手にする投資成果(株価の値上がり益+配当)が高いとは限らないからです。
■例えば、米国の大手ハイテク企業などは配当よりも将来に向けた投資を優先する傾向が強いため、一般に配当利回りは低くなりがちです。一方、業績が伸び悩み将来にむけた有望な成長機会を見いだせない企業は、本業の儲けの多くを配当として払い出すため配当利回りは高くなりがちです。こうした2つの企業を比べた場合、長期的にどちらが投資対象として魅力的かは、配当利回りだけでは決まらないのは言うまでもないでしょう(図表1)。
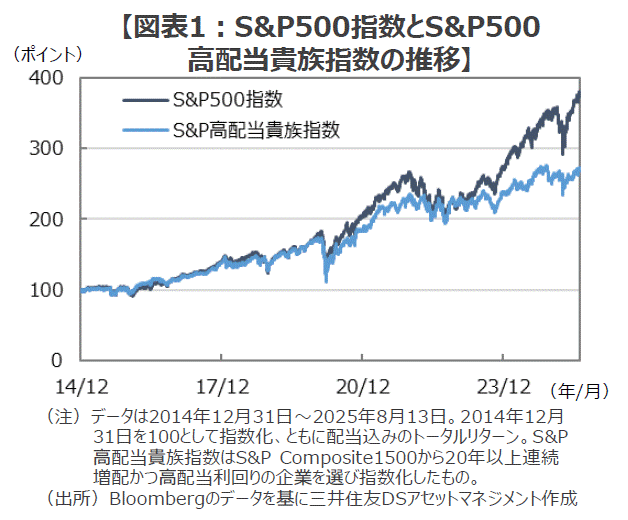
■こうしてみると、投資先の選択理由が「値上がり期待」や「配当」に大きく偏っていることは、有利な資産運用を目指す上ではバランスを欠いているという意味で残念に思えてなりません。こうした「値上がり期待」や「配当」にばかり目が行ってしまうのは、人間の心理的なクセが原因で生じる非合理的な投資行動を研究する「行動ファイナンス」で言う「過信バイアス(自分の予想や過去データを過度に信じてしまうこと)」や、「メンタル・アカウンティング(企業価値の一部を配当として払い出しているだけなのに「得した」と感じてしまうこと)」の典型例と言えそうです。
リスク資産に「とどまり続けること」が重要なワケ
■相場に調整は付き物ですが、2024年8月に世界の株式市場は米国の景気減速懸念の高まりを受けて大幅に調整して、新NISAを利用して投資を開始した方々に「マーケットの洗礼」を浴びせる結果となりました。この「令和のブラックマンデー」と呼ばれる相場の下落局面で、若い方々を中心に新NISAを利用して始めたばかりの投資をあきらめてしまった人が少なからずいたようです。こうしたことが残念でならないのは、株式投資などのリスク資産は投資期間を長くとるほどに勝率が上がり、複利効果で投資成果が大きく膨らむ傾向があるからです(図表2)。
■頭では理解しているはずなのに、こうした「残念な取引」をやってしまうのは、行動ファイナンスで言うところの「損失回避(とにかく損するのは嫌という心理)」や「感情的取引(怒りや、興奮、恐怖などに突き動かされて冷静な判断ができない状態での売買)」が背景にありそうです。
■こうした相場の調整局面での「投げ売り」が残念なのは、単にその投資が失敗に終わるだけでなく、その後に相場が戻した際に高値で買い戻すことへの精神的な抵抗感が更に大きくなるため、結果的に将来の投資機会も逃してしまい「二重に残念な取引」となってしまう恐れがあるからです。
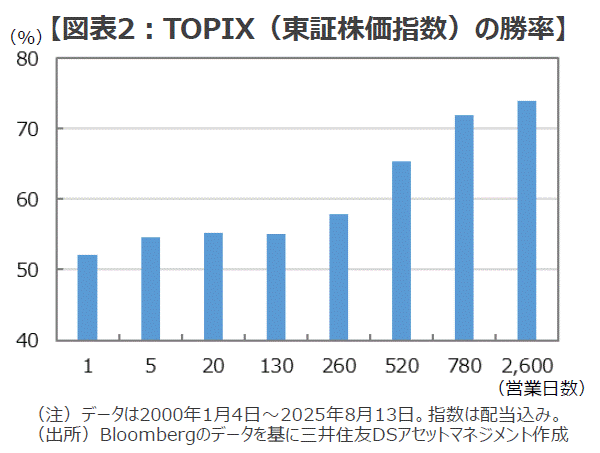
若さの特権は「たぶん長生きなこと」
■新NISAを利用している投資家の年代別の特徴を見ていくと、若い世代ほど「投資の想定期間が短く」、「変動が小さい安定した値動き」を志向する傾向が強いようです。こうした考え方が残念でならないのは、本来なら若い世代ほど年長者よりも平均余命が長いため、投資期間を長くとることが可能なはずだからです。先にも見たようにリスク資産への投資は期間を長くとるほど有利になる傾向があるため、若者ほど長期目線でリスク資産に積極的に投資を行うことで、有利に資産運用を進めることが可能になるはずなのです。
■「青春の特権といえば、一言も以ってすれば無知の特権」と言ったのは文豪の三島由紀夫ですが、こと投資に関する限り若さの特権は「高いリスクを長期間とることができること」ことに尽きます。このため、若い方々の投資における「短期・安定志向」は単なる経験不足に加え、行動ファイナンスでいう「現在志向バイアス(遠い先の老後よりも目の前の損益に強く引きずられる心理)」の結果といえそうです。
■このため、若い方々ほど必要以上にリスク水準を抑えてしまったり、相場の調整局面で投資を投げ出してしまう傾向が強いことは、なんとも「もったいない」としか言いようがありません。そして、後に年齢を重ねて様々な経験を経ることでこうした「若さの特権」に気づいたとしても、「時すでに遅し」となってしまうことには注意が必要でしょう。
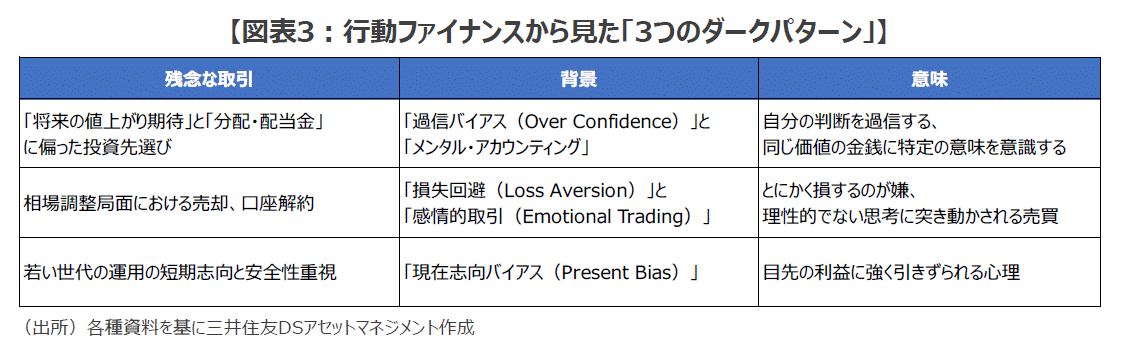
3.「ダークパターン」の回避策
■「新NISA白書」から浮かび上がるこうした投資家の「ダークパターン」を回避するには、どうしたらよいのでしょうか。「敵を知り、己を知れば百戦危うからず(知彼知己、百戦不殆)」と説いたのは中国春秋時代の軍略家の孫子(そんし)ですが、戦(いくさ)を資産運用に置き換えて整理してみましょう。
まず、敵を知る
■投資という戦を有利に進める上で重要なのは、リスク資産の代表格である株式という「敵」の性質をしっかり理解することではないでしょうか。株式市場の長期的な傾向(1999年末以降)を見ると、日本株の代表的な指標である配当込みの東証株価指数(TOPIX)の平均リターンは年率約6.5%、標準偏差が約21.8%ですから、統計的に一般的な正規分布に従うと仮定すると、1年間の投資リターンは約68%の確率で+6.5%を中心に▲15.2%~+28.1%の範囲に分布することが予想されます。
■さらに、学術的な実証分析から株式市場のリターン分布のテールファット(極端な結果が正規分布より多く発生すること)が確認されているため、株式に投資するということは、「それほど大きくないリターンを得るためにビックリするような上下の値動きに翻弄されること」を覚悟する必要があります。
■先に見たように、株式市場では長く持ち続けることで勝率が上昇して、「投資した意味」が出てきます。つまり、上下に大きく暴れる株式市場の動きを受け流して、一喜一憂せずに市場のリスクを取り続けることが、「敵」を熟知した上で「戦」を有利に進めるポイントと言えそうです。
次に、己を知る
■長く相場に関わる仕事をしていて実感するのは、わたしたち個々の投資家の情報収集力には自ずと限界があって、世界中の暗黙知の集合体ともいうべき「市場」を出し抜いて利益を上げるのは、相当ハードルが高いということです。しかし、一部の個人投資家の方々は、みずからの相場観を頼りに果敢にチャレンジされているようです。もちろん、趣味として知的なゲームとして相場をエンジョイしている方を止めるつもりはありませんが、純粋に資産形成を目指しているのであれば、あまりお勧めしたくはありません。
■特に気になるのは、「新NISA白書」にもあるように、20代や30代の方々を中心に投資判断の材料としてSNSを利用する割合が高いようです(巻末:参考資料4)。しかし、ファクトチェックがされていない情報をうのみにし、更に、エコーチェンバー効果(信じたい情報ばかり集まってしまうこと)が加わることで自身の相場観を「これが真実だ」とばかりに過信して思い切った投資をしてしまうのは、冒険を通り越した危険な賭けにも思えてきます。嫌味な言い方にはなりますが、相場という怪物に対して、私たちはあまりに無力であることを知る必要があるのではないでしょうか。
投資に相場予想は必要ない?
■相場という「敵」を知り、わたしたち投資家の限界という「己」を知れば、金融市場はわたしたちの資産形成を進める上での力強い味方になる可能性があります。では、具体的にどうすればよいのでしょうか。それは、相場予測によらず、リスクリターンの観点から有利なポートフォリオを組んで、「長期・分散・複利」の運用を継続することではないでしょうか。「私は相場が読める」などと考えるのはやめて、日々の相場の動きから視線を外し、タイミングはとらず、相場の上げ下げに翻弄される人たちを横目に彼らとは違う「ルール」で行動し、心穏やかに長期運用に耐えうるポートフォリオを「ほったらかし」にしておくのが良いのではないでしょうか。
■誤解を恐れず言えば、長期の投資を有利に進める上では短期的な価格の上げ下げを追いかけるような「相場予想」は必要ないばかりか、余計な売買を誘う悪魔の誘いとなりかねないでしょう。つまり、短期の値動きを獲りに行く「戦術」ではなく、自分の投資目的、投資期間、リスク許容度(どれぐらい損したら我慢ならないか)をしっかり考えた上で、長期の目線で運用を継続する一貫した「戦略」こそが、投資を実りあるものにする上で最も重要なのではないでしょうか。そして、短期の相場を巧みに立ち回ろうとする「下心」、相場が急落した時の「恐れ」、そして、思いがけず大きなリターンが得られた時の「過信」といった感情こそが、わたしたちを「ダークパターン」に引き込むそもそもの原因となっているのではないでしょうか。
まとめに
弊社では新NISAを利用する投資家や金融機関への大規模なアンケート結果をまとめて「新NISA白書」を刊行しましたが、その内容から読み取れるのは、投資家が陥りがちな「3つのダークパターン」の存在でした。
期待される投資利益にばかり目を奪われる一方で、相場の思わぬ動きに動揺してしまったり、また、長期目線で取るべきリスクを取らないことで、投資をあえて難しくしてしまっている人が少なくないようです。
こうした「残念な投資」を避けるには、相場に立ち向かうのではなく、自分自身としっかり向き合ったうえで「長期・分散・複利」の投資に徹することに尽きるのではないでしょうか。こうした長期投資の成否を決めるのは、短期の相場予想に基づく「戦術」ではなく、心穏やかに相場の喧騒をやりすごすための、腹落ちする合理的な「戦略」ではないでしょうか。
関連レポート