2025年7月31日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
日米の「とんでもディール?」で上昇する日本株
出遅れ日経平均の挽回相場と上値目途
7月22日に日米関税交渉が急転直下で決着したことを受けて、日本株が大きく上昇しています。交渉の長期化は不可避との見方が大勢でしたが、早期の決着や予想外の自動車関税の引き下げが文字通り「ポジティブサプライズ」となった格好です。今回の日米交渉については、「よくやった」と好意的な反応が多いようですが、その内容を冷静に見ていくと、首を傾げたくなるものも少なくありません。そこで今回は、日米交渉の顛末やその内容を確認しつつ、今後の日本株の展開について考えてみたいと思います。
1.自称「ディールの天才」の面目躍如
■今回の日米関税交渉については、関係筋の話として7月中旬には日米間で大筋合意していたと報じられています。しかし、トランプ大統領は参院選直前まで「日米通商交渉合意の可能性は低い」などと日本への不満表明ともとれるコメントを連発し、更に、日本の相互関税を24%から25%に引き上げるとの書簡を送付して内外に交渉の不調を印象付ける態度に終始しました。しかし、7月20日の参院選での連立与党の大敗が確定すると、間髪を入れずに赤澤大臣を米国に呼びつけ、さらに、予定外のベッセント財務長官やトランプ大統領との「直接交渉」をセットし、一気に日米交渉をまとめて見せました。
■今回の関税交渉の決着により、日本に課される相互関税は書簡で事前通告されていた25%から15%へ引き下げられ、自動車の関税も27.5%から15%へ引き下げられることとなりました。一方、日本は①自動車や農作物の市場を開放し、②米国製防衛装備品や航空機の購入を拡大し、さらに、③5,500億米ドル(約80兆円)の対米直接投資を約束することとなりました。
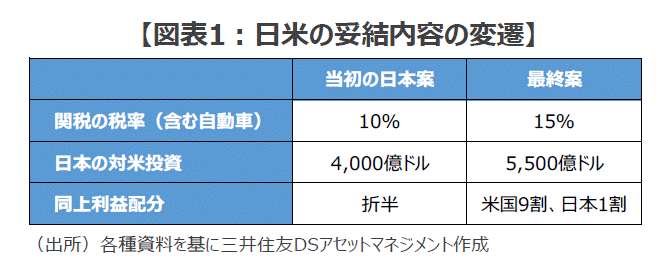
交渉の土壇場で飲まされる「無理難題」
■日本側は今回の交渉にあたり、①日本に課される関税は10%、②対米投資は4,000億ドル(約58兆円)、③投資リターンは日米で折半、としていたようです。しかし、トランプ大統領との土壇場の交渉で、①関税は10%から15%へ引き上げられ、②対米投資は5,500億ドルに増額され、さらに、③投資リターンの90%は米国に帰属する(The United States will retain 90% of the profits from this investment)という厳しい条件を飲まされることとなりました(図表1)。
■ちなみに、ホワイトハウスの公式サイトを見ると、今回決まった対米投資について「トランプ大統領の指示(President Trump’s direction)により米国の戦略的産業基盤の再活性化に投資される。米国はこの投資利益の90%を保持し(retain 90% of the profits)、アメリカの労働者、納税者、そして地域社会が圧倒的な恩恵を受けることを確実にする」とされています。
■投資の世界では、投資家は出資割合に応じて利益配分を受ける一方、失敗した場合には投資資金を失うことで「株主責任」を負うのが一般的です。しかし、ホワイトハウスの公式発表をそのまま読むと、今回のスキームではトランプ大統領が投資の決定権を持ち、投資が失敗に終われば金銭的な損失は日本の負担に、そして、成功した場合には利益の9割を米国が受け取ることとなりそうです。仮に、ホワイトハウスの公式発表が正しいのであれば、投資の常識では考えられない「とんでもディール」と言われても仕方がないでしょう。
■一連の交渉経緯や顛末を見ていくと、窮地に追い込まれた日本が足元を見られる形で不利な条件を飲まされたようにも見えてきます。今回のディールをトランプ大統領は「史上最大のディール」と自画自賛していますが、ホワイトハウスの公式発表をそのまま読むと、自称「ディールの天才」が高笑いするのも解るような気がします。
2.日米合意で動き出す日本株の「挽回相場」
■何とも評価の分かれそうな日米合意ですが、日本株への影響に絞って考えれば、長期化が不可避と思われていた日米交渉が早期に決着し、相互関税の税率が15%に留まり、そして、日本経済の屋台骨を支える自動車の関税が大方の予想に反して15%に引き下げられたことは、素直にポジティブサプライズと言えそうです。
■また、今回の交渉結果の影響として見逃してはならないのは、為替市場で「円安圧力」が生じる可能性が高いことです。というのも、①日本の市場開放や15%の関税により対米貿易黒字が減少に向かうこと、②日本政府による対米巨額投資や日本企業による米国現地生産の拡大のためドル調達ニーズが高まること、そして、③防衛費増額など日本の財政政策がリフレに転換する可能性が高まったからです。
日本株の動きは米株とドル円次第
■日本の株価は直感的、経験的に米国株と為替レートに大きな影響を受けているものと感じている人は多いのではないでしょうか。そんな日本株の動きを統計的に分析すると、米国株とドル円レートの動きでほとんどの動きが説明できることが確認できます。
■2012年末以降の市場データを用いて日経平均株価(日経平均)の動きをS&P500種指数とドル円レートを使って統計的に分析(重回帰)すると、モデルの説明力の強さを示す決定係数(補正R2)は約0.96となり、その動きの実に約96%をS&P500とドル円の変動で説明できることが分かります(図表2)。
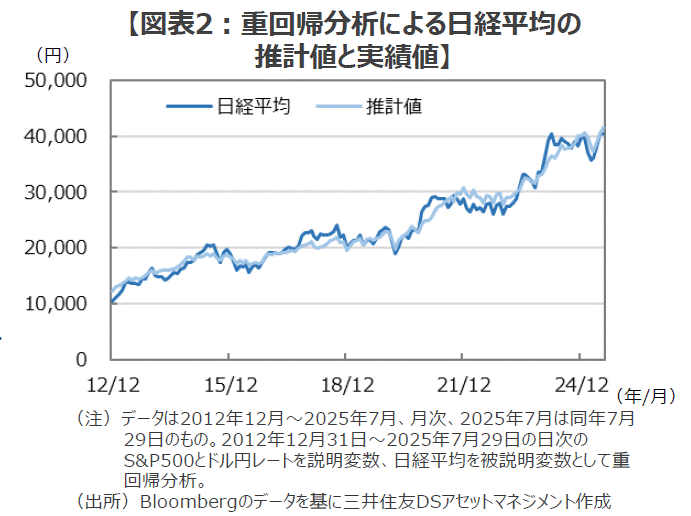
■世界の株式市場に目を転じると、トランプ関税にまつわる不透明感の後退から、米国株式市場はS&P500種指数が7月28日にかけて6日連続で史上最高値を更新するなど、復調が鮮明になっています。こうした米国の株高に為替市場での円安が加わるなら、日本株についても長らく続いた取引レンジを突破して再び上昇トレンドに回帰してもおかしくないでしょう。日経平均は2024年7月11日に付けた高値42,224円02銭に肉薄してきていますが、より広い市場をカバーする東証株価指数(TOPIX)は既に7月24日に史上最高値を更新しています。こうした流れを見ていくと、今後日本株が本格的な「新値更新相場」に移行しても、決して不思議ではないでしょう。
3.日本株の挽回相場の「上値目途」
■仮に、日本株が米国市場に追随して新値を更新していくような「挽回相場」へ移行した場合、どれほどの上昇余地を見ておけば良いのでしょうか。日経平均の過去の値動きを振り返ると、長らく続いた取引レンジの上限が突破された場合、次の上値目途は少なく見積もって約10%、通常なら25%ほど切り上がることが多いようです(図表3)。
■あくまでも経験則ですが、日経平均が2024年7月11日につけた直近高値の42,224円02銭を上抜けて新たな取引レンジへ移行する場合、その上限は控えめに見積もって46,446円(直近高値から10%)、自然体で見れば52,780円(同+25%)との試算になります。
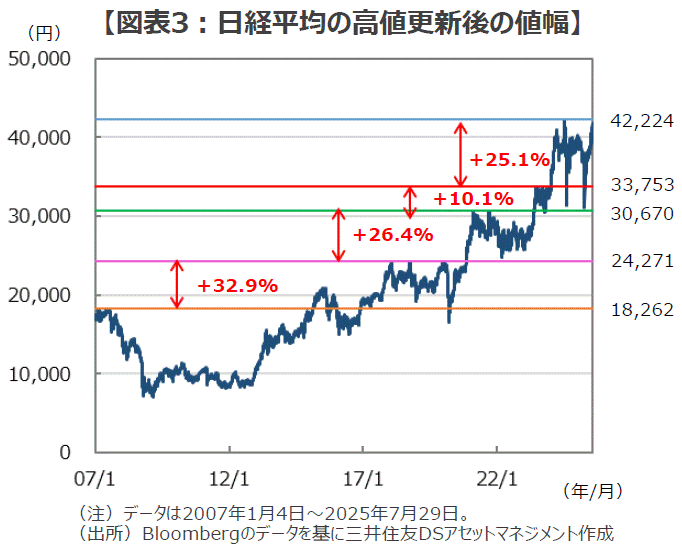
最悪期を脱し切り上がる日本の企業業績
■こうした強気な数字を見ると、「企業業績が心配」と感じる人も少なくないでしょう。そこで、日本企業の業績予想の動向を見ると、東証株価指数(TOPIX)12カ月先予想一株当たり利益(EPS)は、6月27日を底に徐々に改善傾向に向かいつつあることが確認できます(図表4)。また、アナリストによる業績予想の上方修正と下方修正の割合を指数化したリビジョンインデックスも、足元で急速にマイナス幅が縮小してきています(図表5)。こうした足元の業績修正のトレンドと予想外の低率で妥結した関税交渉の結果を考えると、今後は輸出企業を中心にアナリストの業績予想の上方修正が続く可能性が高まっているように思われます。
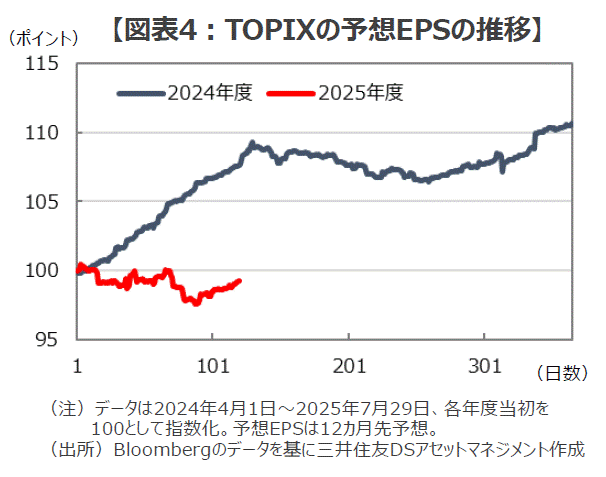
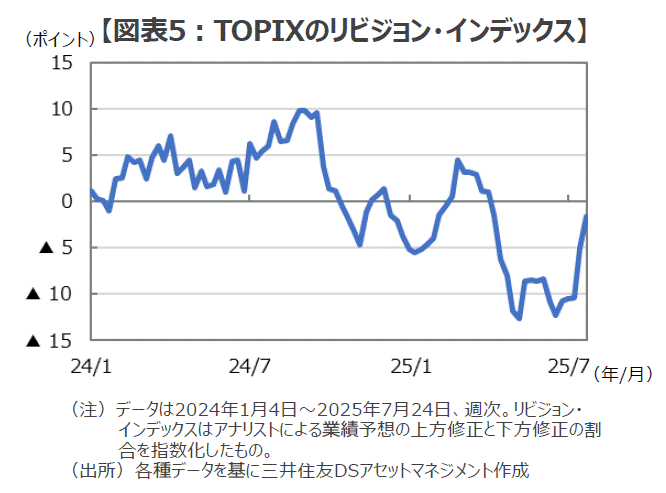
上昇相場における「割高感」と「過熱感」との付き合い方
■次に、現在の日本株の水準を企業業績との見合いで確認してみましょう。代表的なバリュエーション指標であるTOPIXの12カ月先予想株価収益率(PER)を見ると、足元の水準は約15.3倍(7月29日)まで上昇していて、2010年以降の平均値である約14.5倍を上回る水準にあります。こうしたバリュエーション指標を取り上げて「現在の株価は高過ぎる」とする市場参加者も少なくないようです。しかし、長らくレンジ取引が続いた後に相場が上放れる場合、短期的な株価の割高感や過熱感にとらわれていると、相場のトレンド転換や大きな流れに乗り損ねてしまうことが少なくない点には注意が必要でしょう。
■例えば、2012年の後半に始まった所謂「アベノミクス相場」では、日経平均が10,000円から2013年5月に15,000円台に急騰する過程でTOPIXの12カ月先予想PERは約17.0倍まで上昇しました。しかし、その後も株価は堅調を続けて2015年の春には20,000円を突破することになりますが、この間、相場の上昇に遅れて業績予想の改善傾向が続くことで、TOPIXの上昇をサポートする結果となりました。
■同様に、2020年3月のコロナショックにより16,000円台に急落した日経平均はその後大きく上昇に転じましたが、2020年の戻り相場の過程ではTOPIXの12カ月先予想PERは過去平均を大きく上回る18~19倍台で推移し、2021年春に30,000円台に到達する場面では、予想PERは19.5倍まで上昇しました(図表6)。こうした相場のトレンド転換や水準訂正の前例から浮かび上がるのは、市場の変動に遅れがちなアナリストの業績予想の修正を待っていては、相場の大きな流れを取ることができない、という反省点ではないでしょうか。
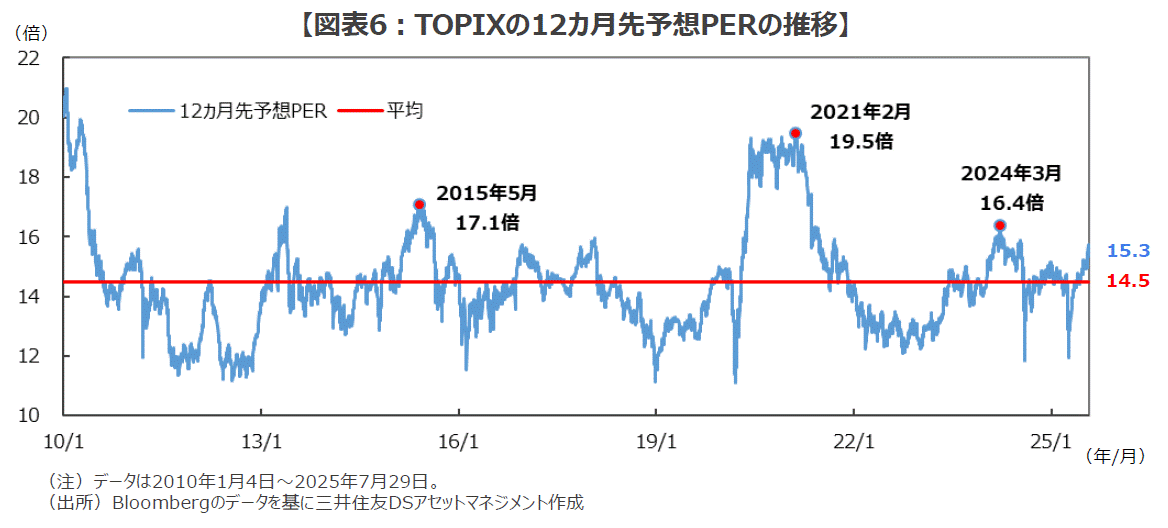
■過去の大きな相場上昇局面に共通するのは、環境変化の中で、①株価のバリュエーションがあまり有効に機能せず、②バリュエーションの割高感はその後のファンダメンタルズの改善により正当化されることが多く、そして、③過熱感や割高感を理由に売り方に回った投資家の買戻しが「更に上昇相場を加速させる」、といったところでしょうか。こうした相場の傾向に加えて、日本企業の業績予想が今後改善してくる可能性が高いことを考えると、足元の相場の過熱感や割高感に必要以上に神経を尖らせるのは、あまり得策には思えません。
■過去10年あまりの主要な上昇相場におけるTOPIXの12カ月先予想PERのピークをみると、①2024年3月の16.4倍、②2015年5月の17.1倍、そして、③2021年2月の約19.5倍、となっています(図表6)。そこで、こうしたピーク時のバリュエーションと現在の予想EPSを使い、NT倍率(日経平均とTOPIXで割って求められる倍率)を掛けて日経平均の上昇余地を計算すると、①予想PER16.4倍で上昇余地+7.2%:上値目途43,611円、②17.1倍で同+11.8%:同45,473円、③19.5倍で同+27.5%:同51,855円となり、偶然の一致とはいえ、テクニカル的な分析から想定される新たなレンジ上限に近い数字になります。
■弊社では、メインシナリオとして、日経平均は2026年3月末の着地で42,300円、レンジ上限を46,600円と想定しています。しかし、仮に、米国株の復調や円安傾向を背景に日本株の「挽回相場」が始まるようなら、もう少し早いタイミングで目標水準が達成されても決して不思議ではないでしょう。
■こうした相場展望は、37,000円~40,000円を中心としたもみ合いに慣れた投資家には、何とも高すぎるように感じられるかもしれません。しかし、①トランプ関税の決着により市場が最も忌み嫌う先行き不透明感が大きく後退したこと、②米国株高や円安により日本株が長らく続いた膠着相場を脱しつつあること、③企業業績が改善傾向を見せていること、そして、④市場参加者の多くが疑心暗鬼に駆られて「上げ相場に乗り切れていない」ように見受けられることから、日本株の挽回相場は意外な推進力を見せるように思えてなりません。
まとめに
日米の関税交渉は想定外の自動車関税の引き下げなど、日本株にとってはポジティブサプライズとなりました。しかし、ホワイトハウスの公式発表を見る限り、その中身は投資の常識からはかけ離れた「とんでもディール」と言われても仕方がないでしょう。
日米間のディールの結果、為替市場では円安圧力が高まりつつあります。さらに、経済の先行き不透明感の後退から米国株の復調が鮮明となっているため、日本株の「挽回相場」がいつ始まってもおかしくないでしょう。
日経平均は新値更新によりレンジを大きく切り上げる可能性があります。こうした上昇相場にバリュエーションの「割高感」や「相場の過熱感」は付きものですが、神経質になり過ぎると「合理的に間違える」ことにもなりかねないため、注意が必要でしょう。



