2014年を振り返るキーワード 「QE(量的金融緩和)」の縮小と拡大 (グローバル)【キーワード】
2014年12月24日
<今日のキーワード>
中央銀行は、主に政策金利の上げ下げで市中の金利水準などを調節します。しかし、政策金利がゼロ近くで更なる利下げが困難になると、非伝統的な金融緩和手段として、国債などを直接購入して市中の資金量を大量に増やすQE(Quantitative Easing)を実施する場合があります。
【ポイント1】米国は効果浸透とともにQEを終了、ユーロ圏は開始、日本は拡大
QEを通じて景気回復や脱デフレを支援
■米国の連邦準備制度理事会(FRB)は、リーマンショック後で3度目となるQEを2012年9月から開始しました。2014年1月から、資産購入額を徐々に縮小し、10月に終了しました。
■日銀は2013年4月、2年で2%の安定的な物価上昇を目標としてQEの拡充を決定しました。“量的・質的金融緩和“として、国債購入額を拡大、対象年限を長期化するとともに、ETF・REITなどリスク性資産の購入を開始しました。さらに2014年10月、デフレマインドの転換が遅れる懸念があるとして、これらの政策を一段と拡充しました。
■欧州中央銀行(ECB)は2014年9月、利下げ実施とともに資産担保証券(ABS)など民間資産の購入方針を発表し、10月から開始しました。11月には、追加策に前向きな姿勢を明らかにしました。
【ポイント2】政策の方向性の違いから米ドル高に
主要先進国の長期金利は低下
■米国では景気の回復や雇用情勢の改善が進んでおり、FRBがQE終了後の政策として、現在ほぼゼロ近くの政策金利をいつ引き上げるかが注目されています。
■日本のQE拡大が市場予想よりも早い段階で実施されたことから、12月に一時1米ドル=120円を超えて円安が進み、株式市場は大きく上昇しました。
■ECBは12月の会合で2015年1-3月期にQEの効果などを検証すると発表し、追加策導入が見込まれています。
■金融政策の方向性の違いなどから、米ドルが円やユーロに対して上昇しました。また、主要先進国の物価上昇は総じて限定的で、長期金利は低下しました。
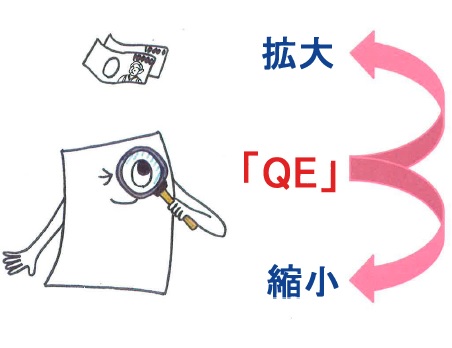
【今後の展開】米国と日欧の金融政策の方向性の違いは、今後も市場の注目点に
■FRBは来年半ばに利上げ開始の見込み
米国では雇用情勢の改善が進み、景気が着実な回復傾向にあることから、FRBは来年半ばに利上げを開始するとの見方が強まっています。足元で原油価格が大幅に下落しており、FRBはこれが景気の押し上げになると指摘しています。
■日銀とECBは金融緩和姿勢を続ける見込み
日本と欧州の景気は勢いを欠く状況が続き、物価上昇率は足元で低下傾向になっています。日銀とECBの金融緩和姿勢は当面続くと見られます。こうしたことから、米国と日本・欧州の金融政策の方向性の違いは今後も市場の注目点になりそうです。



