日本でもインフレが定着する日
2022年9月14日
1.世界で上昇するインフレ、日本は低水準だが2008年以来の高さ
2.日本のインフレは徐々に落ち着きを取り戻す見込み
3.見落としがちなインフレ高止まりのリスク
日本の消費者物価指数(CPI)上昇率は7月に前年同月比+2.6%、生鮮食品を除いたコアCPIで同+2.4%となりました。世界各国・地域のCPIが大きく上昇していますが、日本のCPIも高止まる可能性があるのでしょうか。今回は、日本のインフレについて整理したいと思います。
1.世界で上昇するインフレ、日本は低水準だが2008年以来の高さ
■2021年以降、世界のCPIは大きく上昇し続けています。今回のインフレの特徴は、先進国での上昇が際立っている点です。米国のCPI上昇率は6月に前年同月比+9.1%と40年ぶりの高水準に達しました。8月も同+8.3%と依然高い上昇率です。ユーロ圏、英国も高い上昇率となっています。ユーロ圏のCPI上昇率はブラジル、メキシコ、南アフリカといった主要な新興国よりも高くなっています。
■大幅な物価上昇は、ロシアのウクライナ侵攻と西側諸国の経済制裁等によって、食料・エネルギー価格が上昇し、また、サプライチェーンの機能低下が長引くといった供給制約が主因です。加えて、コロナ禍から経済が回復に向かう過程で多くの国・地域でサービス需要が再度拡大したことも影響していると考えられます。
■日本のCPI上昇率も加速しています。自給率が低いため、インフレを輸入しているとも言える他、進行する円安がそれに拍車をかけています。
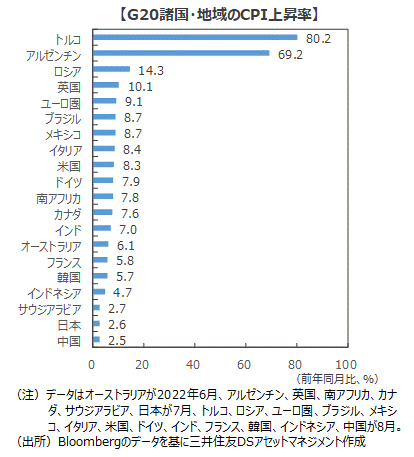
■日本のコアCPI上昇率は7月に前年同月比+2.4%となりました。消費税率引き上げの影響を受けた局面を除くと、2008年以来の高水準です。
■2008年も今回と同様、原油価格が大きく上昇し、高いインフレにつながりました。当時は、同年9月のリーマン・ショックとその後の世界的な金融危機によって需要が急減したことから、原油価格は急落し、CPI上昇率は急速に減速しました。
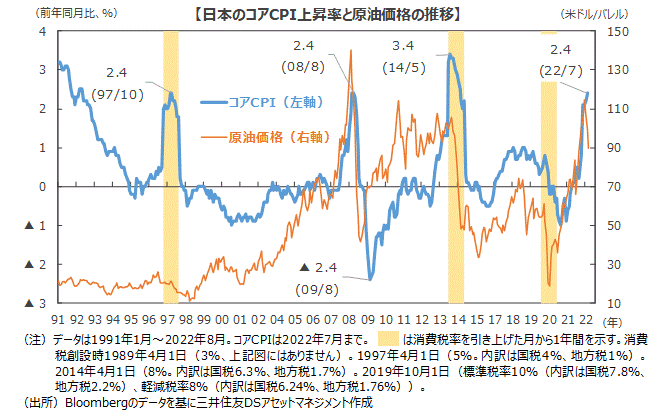
2.日本のインフレは徐々に落ち着きを取り戻す見込み
■次に弊社の今後の物価見通しを簡単にまとめます。予想の前提は原油価格がWTI原油先物価格で95米ドル/バレル、円/米ドルレート(以下、円ドルレート)は135円です(8月現在)。
■前述の通り、7月のコアCPI上昇率は前年同月比で+2.4%で、2008年ぶりの高さです。この上昇をけん引したのはエネルギー、生鮮食品を除く食料と携帯電話機などです。食品は穀類、菓子類、料理食品、外食と幅広い品目で値上げが反映されました。また、携帯電話機は円安を受けたiPhoneの値上げが影響したと見られます。当面は、円安がエネルギーや食料品に広く影響を与えており、コアCPIの上昇モメンタムは続く見通しです。また、国内企業は原材料を輸入に依存している側面が強く、輸入物価指数(円ベース)の影響を受けやすくなっています。
■コアCPI上昇率は22年終盤にかけて前年同月比+2%台後半まで加速する公算が高いと見ています。続く23年以降については、コストプッシュの影響が緩和されることやエネルギー価格の騰勢が次第に鈍化すると見られることから、コアCPI上昇率は同+0.8%まで低下すると見込んでいます。
※個別商品に言及していますが、当該商品を推奨するものではありません。
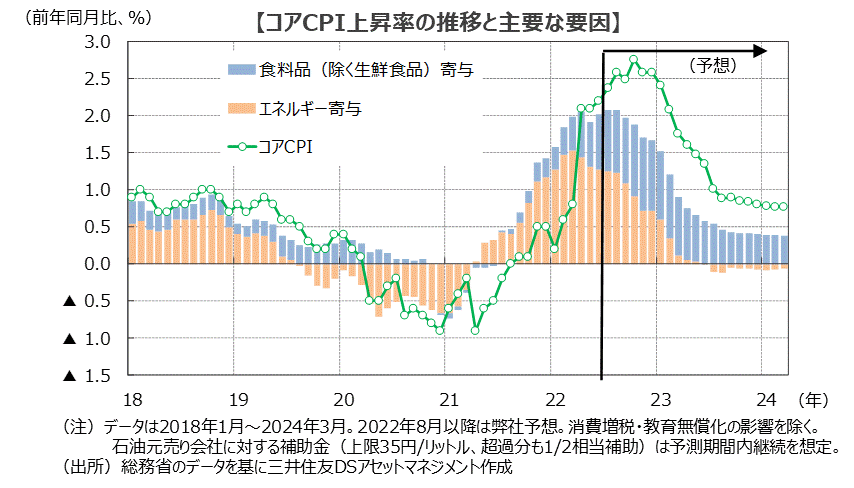
3.見落としがちなインフレ高止まりのリスク
■これまで見てきた通り、弊社では2023年から24年にかけてコアCPIの上昇率は+0.8%に低下すると予想しています。但し、予想以上にインフレを押し上げる要因がいくつも考えられます。今後、物価が高止まる可能性について考えてみます。
(1)円安モメンタムが持続する+輸入インフレが継続する
■弊社の分析によると、円ドルレートと日本のコアCPI上昇率の間には、長期的にみて安定的な関係があることがわかりました。円ドルレートとコアCPIとの関係を調べると、10円の円安により日本のコアCPI上昇率は約0.4%上昇する可能性があります。
■弊社では、円ドルレートの前提を135円として、23年12月のコアCPI上昇率を+0.8%と予想しています。前述の関係を当てはめると、円ドルレートが23年12月に150円になるとコアCPI上昇率は+1.4%、160円で+1.8%と推計されます。コアCPI上昇率が+2.0%となる円ドルレートは165円です。これに加えて、世界のインフレが高止まりしていれば、多くの品目を輸入に依存する日本は、インフレを輸入すると考えられます。
■逆に120円まで円高が進んだ場合は+0.2%となり、さらに115円を下回ればマイナス(デフレ)に逆戻りとなります。
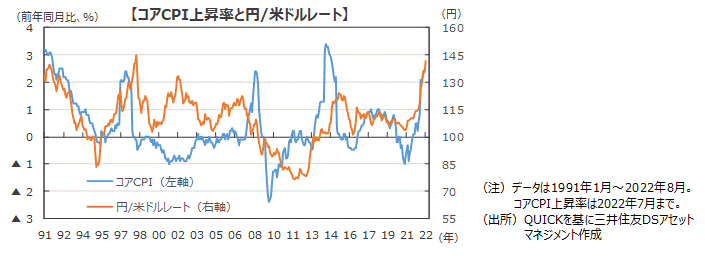
(2)グリーンフレーションとエネルギー危機
<グリーンフレーション>
■足元で原油価格は低下していますが、再度上昇し高止まる可能性はあると思われます。その背景の一つとして、再生可能エネルギーの利用を推進するグリーン・イノベーションに伴うコストの上昇(グリーンフレーション*)が指摘できそうです。
*グリーンフレーション:脱炭素など、環境に配慮し持続可能な開発・発展の実現を目指す動きと資源価格が継続して上昇する状態を指します。
■再生可能エネルギーの弱点の一つはエネルギーの源が自然・気候であり、悪天候などの気候変動は、安定供給のネックとなる点です。安定供給という経済合理性を優先すれば、石油・石炭に比べて環境への負担が相対的に軽い天然ガスへの需要が増加すると思われます。結果的に、脱炭素化の流れの中で石油や石炭に加えて、天然ガスの価格も上昇してしまうという、連れ高現象が起こる可能性があります。
■このように脱炭素化は、その移行期間において思った以上の資源価格の高騰を呼び込むことで企業や最終消費者に負担を強いるものとなるかもしれません。グリーンフレーションの影響は、日本では原油価格の高騰となって、再度物価上昇の要因として浮上するリスクが想定されます。
<エネルギー危機>
■ちなみに、脱炭素化への転換を進める欧州連合(EU)にとって頭の痛い問題が地政学リスク(ウクライナ情勢)と異常気象(干ばつ)です。地政学リスクや異常気象を背景としたエネルギー危機によって、EU諸国の物価水準は引き続き大幅な上昇を余儀なくされる見通しです。
■EUをはじめ世界的なエネルギー危機は、日本のエネルギー資源確保のためのコスト上昇や輸入物価の上昇を通じてCPIの上昇要因となるだけに、注視が必要です。
(3)賃上げと物価上昇の好循環が起こる
■国内の状況を考えると、人手不足の進行と好調を続ける企業業績が賃金に与える影響について吟味する必要があります。今後は人手不足が一層深刻化し、企業は労働生産性を向上させるためにデジタルトランスフォーメーション(DX)投資や人的資本投資に本腰を入れる必要があります。岸田政権は「新しい資本主義」でこれらの投資を重視する姿勢を打ち出しています。税制措置などの政策が奏功すると期待されます。
■さらに、足元の物価上昇が来年以降の労使交渉に強い影響を与え、賃上げと物価上昇の好循環が始動する可能性があります。幸いにも上場企業の業績は好調を維持すると見込まれ、過去最高を更新する見通しです。こうした状況下で、近年にない物価上昇に直面し、労働組合の賃上げ要求も先鋭化する可能性があります。賃上げ率が大きく上昇すれば、高い物価上昇率も許容できるようになると考えられます。
まとめ~物価上昇は意外に長引くリスクがあることに注意
■円安モメンタムの継続を考慮すれば、1%台の物価上昇は視野に入りそうです。1%台の物価上昇は米国に比べれば低位であり、日銀が目標として掲げる2%にも及びません。その意味では高止まりと言えるような水準になる可能性は低そうです。但し、デフレ局面が長かった日本の場合、1%台での推移は決して低い物価水準ではありません。さらに、今回みてきたようにグリーンフレーションやエネルギー危機の影響による資源価格の持続的な上昇や今後の賃上げ圧力の高まりの可能性を考えれば、23年はもう一段の物価上昇が起きるかもしれません。
■今後、更なる値上げラッシュが来ることが予想されています。物価上昇は意外に長引くリスクがあることに注意した方がよさそうです。
関連マーケットレポート
- 日々のマーケットレポート
- 日々のマーケットレポート



