ロシア・ウクライナ情勢を受けた世界経済・金融市場の見方の整理
2022年2月28日
1.制裁は供給制約要因で、経済は下振れ、物価には上昇圧力
2.今後のウクライナ情勢のシナリオについて
3.金融市場の見通し
はじめに
2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻が続く中、欧米諸国は対ロ経済制裁を強め、26日には米欧の共同声明で、一部のロシア金融機関を国際銀行間通信協会(SWIFT)から除外するとともに、ロシア中央銀行の外貨準備の運用を制限することなどを発表しました。ロイター通信によると(日本時間28日朝時点)、エネルギー関係の取引については除外される可能性があるとのことですが、停戦交渉の行方やウクライナにおける被害状況の深刻さによっては経済制裁の内容、強さ、そして期間が変わる可能性があり、グローバル経済への影響も変わり得る状況とみられます。
このように、状況は予断を許しませんが、経済への影響、事態の先行き、金融市場の見通しについてまとめます。
1.制裁は供給制約要因で、経済は下振れ、物価には上昇圧力
■米欧日などによる対ロ経済制裁の影響は主に、①ロシア・ウクライナ向け輸出の減少、②ロシア・ウクライナが重要な供給者になっている原油・天然ガス、穀物、一部の希少金属の供給不安(供給制約要因)、そして③ロシア金融機関向け貸し出しの不良債権化による金融機関への影響、の3つに大別されます。
■このうち、対ロシア・ウクライナ向け輸出の減少については、両国のGDP規模がロシアが1.6兆ドル前後(世界GDPに占める比率は1.7-1.9%)、ウクライナは0.2兆ドル弱(同0.2%前後)とともにあまり大きくないことから、それほど大きな影響は生じないものと思われます。また、中国を除く世界各国からの対ロシア輸出がゼロになった場合の経済への影響を試算すると、世界GDPへの影響は▲0.38%となりますが、エネルギー、食糧関係など一部の貿易は維持される可能性を考慮すると、その影響は更に限定的なものにとどまるものとみられます。
■また、金融機関への影響ですが、対ロシア向け債権の規模はデリバティブや保証などを含めないベースで約1,050億米ドル、デリバティブや保証を含めても約1,500億米ドル前後にとどまります。もちろん、債権者の規模により影響は多少変わる可能性はありますが、これらが不良債権化した場合の金融システムに与える影響は管理可能と考えられます(日本の不動産バブルやリーマン危機などでは金融機関の損失は米ドルで兆の単位でした)。
■世界経済を考える上で最大の注目点は供給制約要因といえます。ロシアは鉱物性燃料と穀物で世界輸出で8%程度のシェアがあります。またウクライナも穀物では存在感が大きく、これらの供給が減少することによる原油・天然ガス価格と農産物価格の上昇がどの程度になるかが、最大の注目点といえます。原油価格の10%の上昇(現状では1バレル当たり10ドル前後の上昇に相当)は米欧日のケースで見ると消費者物価が+0.2%(コア消費者物価ではその半分)程度、GDP成長率への影響は▲0.1%弱程度。原油価格が120ドル前後までの上昇であれば、インフレへの影響は+0.4-+0.5%(コアはその半分程度)、GDP成長率への影響は▲0.2-▲0.3%と試算されます。
■但しこれらは、先進国に関する試算であり、新興国の一部では影響が大きくなる可能性があります。また、先進国についても、インフレ圧力の高まりを受けて中銀の利上げ幅が拡大したり株価が下落するなど、その影響は増幅される可能性があります。原油・天然ガスや穀物以外でも、ネオンガス、パラジウムなどでもロシアのシェアが大きいことから、半導体生産への影響についても一応の注意が必要とみられます。
■以上から、対ロ経済制裁の世界経済への悪影響は、単純化すると供給ショックであり、成長率を押し下げ、インフレ率を押し上げます。様々な不透明要因を考慮しつつ、全体として幅をもって評価すると、原油価格のイメージで110-120ドル前後までのインパクトであれば、世界経済は耐えられるとみられますが、それを大きく超える上昇(たとえば原油のイメージで150ドル超になりそれが続く状況)となった場合は、2022年後半以降の景気回復シナリオについて検討しなおす必要が出てくると考えられます。
2.今後のウクライナ情勢のシナリオについて
紛争はしばらく続くが、制裁の効果によって事態の収拾が図られる見込み
■今後のシナリオは、この種の問題の常として、短期と長期に分けて考える必要があるでしょう。
■短期的(3~6カ月)には、ロシア・ウクライナの交渉、ロシアの軍事行動とそれに対する米欧の対応によりますが、ロシア(プーチン政権)は一定の成果を挙げることを意図して軍事行動による圧力を維持する公算が大きいと考えられます。中国がロシア寄りのスタンスをとる一方、西側諸国はウクライナ支援の姿勢を強める中で、重要都市を巡る攻防にせよ、ゲリラ戦的な様相になるにせよ、紛争がしばらく続き、商品市況の上振れを通じて金融市場に断続的にストレスがかかる時期がしばらく継続する可能性があります。ただし、政治的な妥協が難しい一方、長期化すれば経済へのダメージが双方に蓄積していくため、何らかの戦況の区切り(膠着、どちらかの優位の明確化)で当面の事態収拾が図られ、商品市況などは世界経済が吸収可能な範囲に戻る、というのがメインシナリオとなります。この場合、2022年のマクロ経済は悪化(成長率低下、インフレ率上振れ)しますが、経済再開による回復トレンドという構図は維持可能であり、中国が欧米との対立を極端に強めなければ、アジアは相対的に安定を維持できると見込みます。
■メインシナリオに対する楽観ケースとしては、上記の想定よりも双方が早期に収拾を図るケース、悲観シナリオとしては、ロシアがより強硬(新たな武器の投入なども含めて)になる、あるいは中国がロシア寄りのスタンスをとる中で、制裁・報復という動きが欧米と中国の間でも発生するケースなどが考えられます。
長期的には、グローバライゼーションの後退により、高めのインフレが継続しよう
■長期的にみると、ロシアと欧米諸国の関係改善には長い時間を要するとみられ、国際政治・経済が質的に変わってしまった面があります。これに中ロの接近を考え合わせると、こうした安全保障の枠組みの変化が、サプライチェーンの見直しを促進する可能性が高いと見られます。換言すると、トランプ時代から始まっていたグローバライゼーションの後退というトレンドの加速につながっていくとみられます。世界経済(特に中国と他の国々)の相互依存関係は密接になっているため、冷戦時のような隔絶は発生し得ないと見られますが、パンデミック前と比較すると、商品市況やインフレが高めのレンジに定着する要因となるでしょう。
3.金融市場の見通し
金融政策は、足元の大幅利上げの可能性は低下も、中立への修正は継続
■米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)の金融政策運営は、景気のダウンサイドとインフレの上振れの両面を考慮することになります。柔軟性を確保していく観点から、FRBによる利上げ幅も一部で言われていたような0.5%となる可能性は当面下がったとみられます。しかし、現状の金利水準がゼロないしマイナスで超緩和的な状態にあるため、景気の大幅悪化が確認されない限り、中立水準に向けての利上げの動きは続くでしょう。今回の問題を受けて中期的にも商品市況が高止まりし、半導体の供給制約もやや長引く可能性があることなどを考慮すると、事態が小康を得た後は、利上げが追加的に前倒しになる可能性(ECBなどに注目)が考えられます。
株式は、原油価格等が上振れるリスクを意識した後、回復へ
■金融市場については、過去において今回のような地政学イベントが発生した際は、イベント発生時が株価などのボトムになることが多かったことは事実です。ただし、70年代の中東戦争時などを除くと、世界的に資源や製造業の供給余力がありインフレ圧力が弱い時期の経験であったことに注意が必要と考えます。
■今回の危機は、グローバライゼーションが後退し、環境規制強化などのトレンドが明確化し、そしてインフレが上振れている中で発生しています。このため、上述のように、供給制約とインフレ圧力がどの程度強まるかで、一定期間市場の動揺は続くものとみられます。株価については、短期的には原油価格などがオーバーシュートするリスクが意識され、世界経済の下振れが1%に接近する可能性が意識される局面でダウンサイドを追加的に織り込む動きとなるものと思われます。しかしその後は、商品市況が落ち着きを取り戻すにつれ、株式市場も回復するというパターンが想定されます。
長期金利は緩やかな上昇が、為替は一旦は米ドルと円の堅調が見込まれよう
■長期金利は、インフレのレンジが上方シフトし、FRBやECBが中立水準に金利を戻す動きを続けるとみられるため、レンジを切り上げていくとみられますが、成長の下振れや市場のリスク許容度の低下が上昇ペースを抑える要因となるでしょう。為替については、当面はリスクオフの下で米ドルと円が堅調になったのち、ECBの政策変更の余地が大きいことからユーロがリバウンドし、商品市況上昇による貿易収支悪化を考慮して円はじり安に向かうというのが引き続きメインシナリオとなります。しかし、今回のロシアとの関係変化はユーロ圏の安全保障コストの上昇(エネルギー、軍事など。ドイツの国防予算の増額は象徴的)を意味します。これが、ユーロにとってどの程度の抑制要因となるか、検討していくことが必要になります。
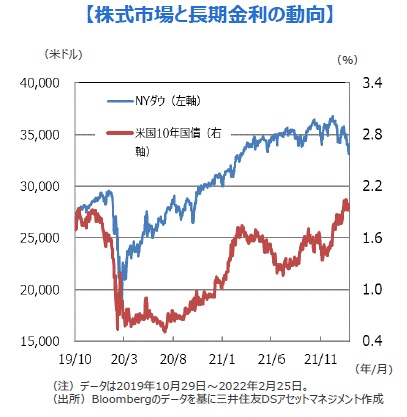
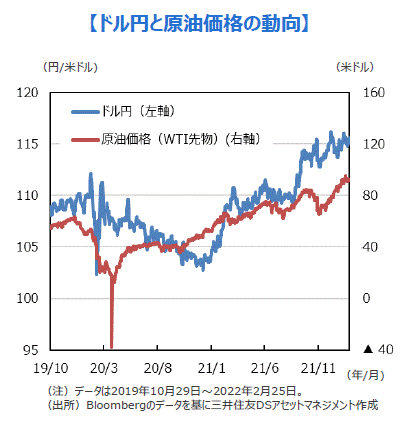
関連マーケットレポート
- 市川レポート
- 日々のマーケットレポート



