2025年9月18日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
巨額の対米投資と円安ドル高リスク
「逆プラザ合意」と「デット・エクイティ・スワップ」
日米両政府は9月4日、関税交渉に関する日米合意の共同声明を発表するとともに、日本による対米投資についての覚書を公表しました。その詳細が不明だった5,500億ドル(約81兆円)の対米投資ですが、1対9とされる日米間での投資リターンの配分もさることながら、市場関係者をざわつかせていたのは「80兆円もの資金が日米間で動いたらドル円レートはどうなってしまうのか」という不安でした。というのも、私たちが米国に投資をする場合、証券投資であれ、不動産投資であれ、そして、設備投資であれ、手持ちの円をドルに交換する必要があるからです。
1. 対米巨額投資という「逆プラザ合意」
■日米の関税交渉の結果、日本に課される関税が25%(自動車は27.5%)から15%へと引き下げられる一方、日本は米国に「5,500億ドルの投資」を行うこととなりました。この対米投資について、トランプ大統領は「野球選手の契約金のようなもの、我々が自由に使える資金」と発言しました。また、投資リターンが日米間で1対9の割合で配分されると伝えられ、さらに、日米政府の説明内容に微妙な食い違いがあったことから、様々な憶測を呼ぶ結果となりました。
■今般の日米政府による共同声明と覚書の公表により、対米投資の概要がようやく明らかになりましたが、金融市場として気がかりなのは、米国が主導する投資プロセスや米国に有利な利益配分もさることながら「これだけの巨額資金が日米間で移動した場合、為替市場にどんな影響が出るのか」という心配でした。というのも、80兆円という金額があまりに大きい数字だからです。
あまりに大きい「80兆円」
■「80兆円」という数字の大きさを理解するために、日本の貿易や対米直接投資の数字を確認してみましょう。日本は2024年の1年間に約107兆円分のモノを輸出し、一方で約112兆円分を輸入しました。そして、輸出の約50%、輸入の約67%を米ドルで決済しています(2025年上期)。つまり、おおまかにいうと、1年間に輸出業者は約54兆円分のドルを売り、輸入業者は約75兆円分のドルを買い、ネットでは貿易取引に伴い約21兆円分のドル買いが生じている計算になります。

■また、2024年の日本から米国への直接投資は、日本銀行の統計によれば約13.4兆円になります(図表1)。こうしてみると、今回本決まりとなった「80兆円」という投資金額がいかに大きい数字であるかが容易に想像できるでしょう。もし、これだけの金額がトランプ大統領の残りの任期中に日本から米国へ送金されることになれば、その為替市場への影響が気になるのは、至極当然と言えそうです。
国際協調による「逆プラザ合意」?
■ここで注意しなくてはならないのは、こうした対米投資は日本に限った話ではなく、欧州連合(EU)は6,000億ドル(約88兆円)、韓国は3,500億ドル(約51兆円)の対米投資を、関税引き下げの見返りに実施することです。仮に、これだけの巨額投資を賄うために日本、EU、韓国がドルを為替市場で手当てするようなことがあれば、ドルは対主要通貨で大きく跳ね上がり、かつて国際協調でドルの大幅切り下げを行ったプラザ合意とは真逆の「逆プラザ合意」となりかねないでしょう。
2. 対米投資のドル円へのインパクト
■こうした懸念に対して、「今回の対米投資は政府系金融機関の国際協力銀行(JBIC)が行うので為替市場には影響しない」とする見方があるようです。JBICは日本政府が100%出資する政府系金融機関で、国際的な経済協力や日本企業の海外展開を支援するために融資・保証・出資などを行っています。そして、このJBICが米ドルの資金調達を行う場合、政府の外為特別会計(外為特会)からの借り入れや、政府保証の付いた外貨建ての債券を発行するのが一般的なので、「ドル調達・ドル運用」となるため、ドル円の為替取引は発生しません。
■「それみたことか、驚かすなよ」といった声が聞こえてきそうですが、気になることがないわけではありません。というのも、繰り返しになりますが、「80兆円」という資金規模があまりに大きいのです。
JBICによるドル調達スキームへの不安
■2025年8月現在、日本の外貨準備は約1.3兆ドル、うち、外貨建て証券が約9,831億ドルです。仮に、この8割が米国債で運用されていると仮定すると、日本の外為特会には約7,860億ドルの米国債が保有されている計算になります。このため、もし、JBICが政府の外為特会から5,500億ドルの資金拠出を受けるなら、日本政府は外貨準備で保有する米国債の約7割を売却する必要に迫られます。
■外貨準備は円安が行き過ぎる局面では「円買いドル売り介入」の原資となります。また、リーマンショックのような金融危機の際は、主要国間での「通貨スワップ(互いに自国通貨を融通し合う仕組み)」を行う際の信用の裏付けとなるので、おいそれとは売るわけにいかないでしょう。そう考えると、「JBICは外為特会(外貨準備)から資金調達するので為替市場にはインパクトが出ない」とする見方は、あまり説得力がないように感じられます。
■外貨準備で保有する米国債の大半を処分するのが難しいなら、政府保証でドル建て債券を発行して資金調達すればよいのでしょうか。JBICは民間金融機関と異なり自己資本規制はありませんが、財務の健全性を維持するための独自のリスク管理ルールがあるため、政府の強い要請とはいえ身の丈に合わない巨額の資金調達・投融資を行うことは容易ではないでしょう。
■JBICの財務データを確認すると、資本金が約3.5兆円、昨年度1年間に実行した出資・融資・保証の合計が約1.5兆円、そして、昨年度末の与信残高が約15.4兆円となっています。つまり、現在の自己資本比率(総与信に対する資本金の割合)を維持しつつ80兆円の新規資金を手当てするには、約18.1兆円の資本増強が必要な計算になります。
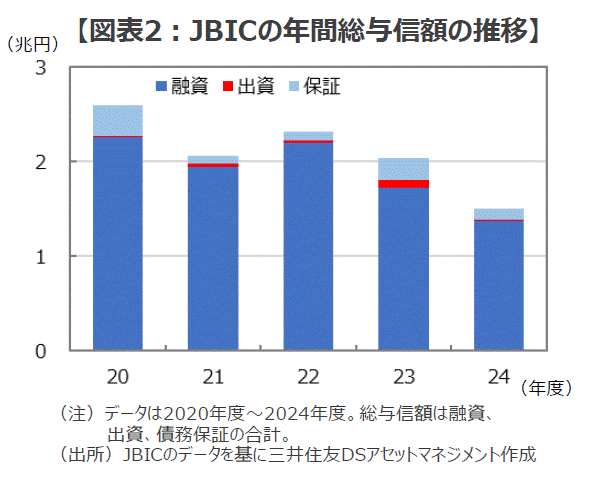
■そもそも、日本政府は為替リスクや国債の安定消化への懸念から、ドル建ての国債を発行していません。そして、現在のJBICによる外債発行残高は総額約6.1兆円にとどまります(図表3)。このため、政府保証付きとはいえ80兆円ものドル建て外債を、「まともな金利」で「市場を荒らすことなく」発行するのは、現実的にはかなりハードルが高いように思われます。
■仮に、JBICが外為特会からの借り入れや外債発行で80兆円分のドル資金を手当てすることが難しい場合、日本政府であれJBICであれ、いずれかが円をドルに交換した上で米国に送金することとなります。そして、為替市場には「桁外れ」の円売りドル買いフローが流れ込むことになりかねないでしょう。
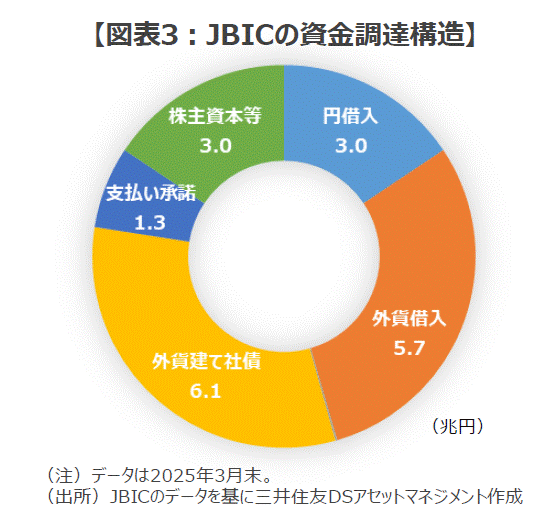
3. 「対米投資80兆円」の真の意味?
■先に見たように、今回の日米合意に基づく対米投資は、概算で日本の外貨準備が保有する米国債の7割前後にも達するようです。ちなみに、韓国は同じく3,500億ドルの対米投資を求められていますが、韓国の外貨準備は約3,853億米ドル、うち、外貨建て証券は約3,642億ドルとなっています(2025年7月末)。こうして日本や韓国による対米投資の規模と外貨準備で保有する米国債の残高を眺めていくと、偶然の一致かもしれませんが、米国政府が「何を見て、何を狙っているのか」が、おぼろげながら伝わってくるような気がします。
「掟破り」のデット・エクイティ・スワップ
■仮に、日本政府が米国との約束を律儀に守り、外貨準備で保有する米国債の売却、ないしは、米国債を担保にした借り入れによりドル資金を調達し、米国政府が設立・管理・運営する特別目的事業体(SPV)に80兆円を送金するなら、それは日本から米国への「貸付(米国債)」を「投資」に振り替えることと、ほぼ同義といってよいでしょう。
■一般に「貸付」を「投資」へ振り替えることは「デット・エクイティ・スワップ」と呼ばれ、金融機関が経営不振企業の再建を支援するスキームの一つとされています。仮に、こうした見立てが見当違いでないなら、日本という国の信用を脅かすリスクには注意が必要でしょう。というのも、日本にとって「虎の子」の外貨建て資産が信用力抜群の米国債から、元本の回収やリターンが定かでない「投資」に入れ替わってしまうからです。
■ちなみに、今回発表された投資スキームでは、日本は通常の株式投資のようにリスクに見合った大きなリターンが得られるわけではなく、大きく儲かった時の利益配分は日米で1対9の割合となります。このため、米国に対する債権者である日本にとっては、より条件の厳しい「掟破りのデット・エクイティ・スワップ」とすることができそうです。
対米巨額投資と円安ドル高リスク
■日本は世界でもあまり類を見ない巨額の政府債務を抱えていますが、①巨額の対外純資産、②外貨準備、そして、③経常収支の黒字が、国の信用を支えているとされています。そんな、日本の信用を支える三本柱の一つである「外貨準備」についてケチがつくようなことがあれば、ただでは済まないかもしれません。
■ちなみに、日本の外貨準備は巨額と言われますが、外貨準備の適正な規模を測る指標の一つである「外貨準備対短期対外債務比率(国の外貨準備が短期間で返済が必要な対外債務をどの程度カバーしているかを示す指標)」は約39%にとどまり(外貨準備:約1.23兆ドル、対外短期債務:約3.14兆ドル、2024年末時点)、一般に適正水準とされる100%を大きく下回っています。
■こうしてみると、対米投資により巨額の円売りドル買い需要が発生する可能性もさることながら、今回の対米投資スキームが日本の外貨準備や信用を損ねるリスクの方こそ、長期的にはドル円レートに大きな影響を与えかねないでしょう。
■最近のドル円レートを取り巻く環境を確認すると、①米国の雇用失速による米連邦準備制度理事会(FRB)による大幅利下げ期待の台頭、②ドルの信認を傷つけかねないFRB内部のゴタゴタ、そして、③予想外の日本経済の堅調さを受けた日銀による利上げ前倒し観測などから、大きく円高ドル安が進んでもおかしくない状況にもかかわらず、ドル円は140円台半ばから後半でのもみ合いの展開が続いています(図表4)。
■もし、こうしたドル円の「粘り腰」の背景に、巨額の対米投資に起因する「円安ドル高リスク」があるならば、FRBによる利下げ開始後も大方の予想に反してドルが堅調に推移してもおかしくないでしょう。
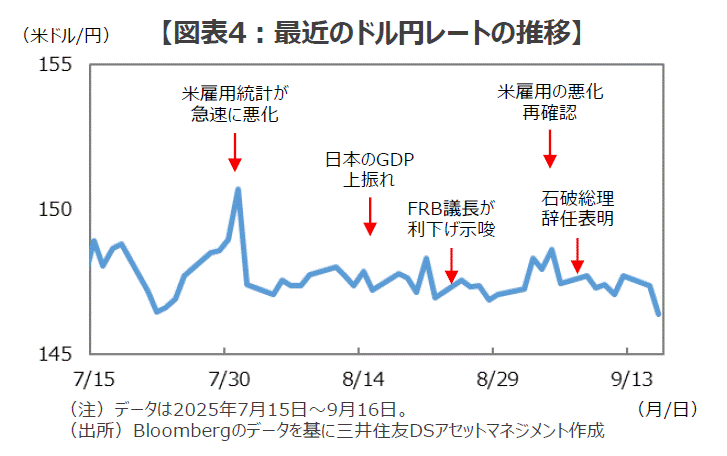
■もちろん、円安ドル高は海外投資を積極化させてきた日本の投資家にとっては追い風といえますが、その背景が日本の大切な資産の売却や信用の低下によるものであるとすれば、素直に喜ぶわけにはいかないでしょう。
まとめに
ドイツの思想家カール・フォン・クラウゼヴィッツは著書『戦争論』の中で、「外交は内政の延長(戦争は他の手段をもってする政治の延長)」と喝破(かっぱ)しました。安定した政権基盤を持たない政府は国内での利害調整に手こずり、外交相手から軽んじられることが少なくないからです。
今回の日米関税交渉は、連立与党が参議院選挙に敗北した直後に急転直下で決着しましたが、まさに「内政」で追い込まれた日本政府の苦境を見透かすような「ディール」と言ったら言い過ぎでしょうか。
日米合意に基づく80兆円の対米投資は、日本が外貨準備で保有する米国債の約7割にも達する金額です。このため、その実行には巨額のドル買いフローが発生する可能性があるだけではなく、その扱いを誤ると日本の信用低下に繋がりかねないため注意が必要でしょう。



