2025年9月17日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
そろそろ、この上げ相場の「答え合わせ」をしましょう 景気不安、減益、割高でも日本株が上がるワケ
日本株の上昇が勢いを増してきました。7月31日付の当コラム「日米の「とんでもディール?」で上昇する日本株」では、①米国株とドル円レートの動き、②企業業績、③バリュエーションの3つの視点から、日経平均株価がレンジ上限を上放れて、大きく上昇するシナリオをお伝えしました。一般に、株価は経済指標などに先んじて動く「先行指標」とされていますが、今回はこの7月末時点で立てた「日経平均の大幅上昇」という仮説について、その後明らかになったデータなどを確認しながら「答え合わせ」をしていきたいと思います。
1. 景気不安でも上がる株
■このところの日本株の上昇相場は、参議院選挙の3日後の7月23日に急転直下で日米の関税交渉が決着したことをきっかけに始まりました。しかし、エコノミストを始めとする市場関係者の多くは、「トランプ関税の影響が本格化するのはこれから」として、日本経済の行く末を懸念する意見が大勢でした。このため、にわかに動き始めた株価について、「景気不安の残る中での不自然な株高」との見方が多数派だったように思われます。
■しかし、関税交渉の結果が想定よりは「まし」だったこと、そして、市場が最も忌み嫌う「先行き不透明感」が後退したことから、市場関係者の心配をよそに日本株は大きく上昇を続けることとなりました。さらに、その後発表された経済指標では、4‐6月期の名目GDP成長率が大幅な伸びとなり、7月の実質賃金が7カ月ぶりにプラスに転換するなど、日本株の好調と足並みをそろえるような「ポジティブニュース」が市場を駆け巡る事となりました。
■中でも、税収や企業業績、そして、株価と高い相関があるとされる名目GDPが前期比年率で+6.6%の大幅な拡大へと改定されたことは、市場に根強かった日本経済への不安を吹き飛ばすには十分なインパクトがあったように思われます(図表1)。

株価は景気の「先行指標」
■米国の主要な経済指標の一つに、コンファレンスボード社が発表する「景気先行指数」があります。経済の先行きを占うこの指標には、企業の景況感などとともに米国の代表的な株価指数である「S&P500種指数」が含まれています。つまり、株価は単に景気や企業活動の現在地を測るバロメーターにとどまらず、「先行指標」として有効であることに気付いた先人たちの知恵が、こうした「経済指標」にも活かされていると言えそうです。
■冷静に考えれば、実体経済の動きに遅れて発表される経済指標を見ながら、その先行指標ともいうべき「株価」を予測するのは、バックミラーだけを見ながら車を運転するようなものかもしれません。そして、最近の日本経済についてのニュースと株価の関係について「答え合わせ」をしていくと、急な上げ相場に戸惑う専門家たちの「警戒論」よりも株価の「先見性」の方が正しかったと言って良さそうです。
2. 今期減益でも上がる株
■このところの株価の上昇過程で、上げ相場に乗り切れない市場参加者の多くから聞こえてきたのは、「今期減益なのに、この株高はおかしい」という声でした。こうした意見は一見的を射ているように聞こえますが、大事な点を見逃しているようです。というのも、2014年や2019年に実施された消費税増税による物価押し上げ効果が一時的であったように、トランプ関税の影響についても一過性とする見方が少なくないからです。さらに、今年度の企業業績が減益となった反動から来年度は一転して増益になる可能性が高く、時間の経過とともに市場のフォーカスが「今期の減益」から「来期の増益」にシフトしていくのは、ある意味自然な流れだからです。
■前掲の7月31日付の当コラムでは、①6月27日を底に12カ月先予想EPSが既に底打ちしていること、②アナリストの業績予想のトレンドを示す「リビジョンインデックス」がマイナス圏から急回復していること、そして、③トランプ関税の想定より良好な決着から、業績予想はこの先改善に向かうことで株価を押し上げる材料となる、との仮説を提示しました。
今期減益でも大きく伸びる12カ月先予想利益
■そして、その後の今期予想EPSと12カ月先予想EPSの推移を見ると、低下トレンドは6月末を底に大きく反転していて、直近のピークだった4月のトランプ関税発表直前の水準を大きく超えて、日本企業の「業績改善トレンド」が鮮明になっています(図表2)。
■こうして企業業績と株価の関係について「答え合わせ」をしていくと、ここでも株価はその後のアナリストたちの業績予想の上方修正に先行していたと言って良さそうです。そして、経済紙などに掲載される会社予想に基づく「遅いデータ」を見ながら株高に疑問を呈していた向きは、株高に後追いする形で企業業績への見方を大きく修正することとなりそうです。
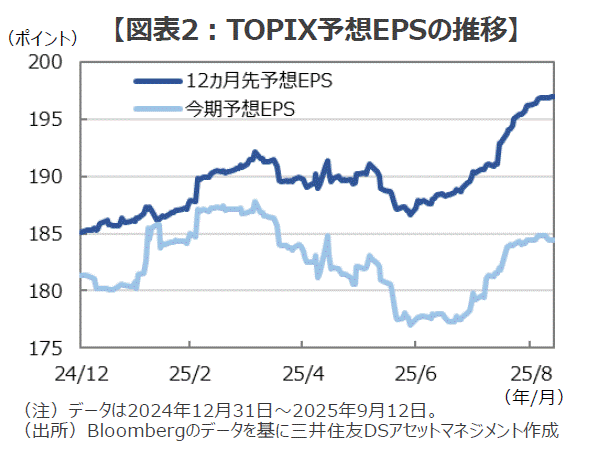
3. 割高でも上がる株
■今回の株高については、一株当たり利益(EPS)の今期予想が冴えないため、「株価収益率(PER)の主導となっていて続かない」という意見もよく耳にしました。これも、至極まっとうな意見に聞こえますが、どこがいけなかったのでしょうか。ちなみに、前掲7月31日付当コラムでは、レンジを上放れて始まる相場の「大きなトレンド転換」にあっては、バリュエーションはあまり有効に機能せず、株価の上昇の結果生じる「バリュエーションの割高感」は、その後のファンダメンタルズの改善で正当化されることが少なくないことをお伝えしました。
切り上がる株価、落ち着きどころを探るPER
■そこで、このところの株価上昇局面におけるTOPIXの12カ月先予想PERと株価の推移をみると、株価が大きく加速する一方、それまで歩調を合わせて拡大してきていた12カ月先予想PERは、業績予想の改善もあって足元では株価の推移から乖離しつつあります。(図表3)。仮に、今後もアナリストによる業績予想の上方修正トレンドが続く一方、先んじて上昇してきた株価が上方にシフトした新しい取引レンジでの落ち着きどころを探る展開に移行していくと、バリュエーションの割高感は過去の大きな株価上昇局面がそうであったように、株価が大きく調整することなく平凡な水準へと収斂していくのではないでしょうか。
■こうして見ると、先行した株価の上昇を、ファンダメンタルズの改善が追いかける展開が続いているようにも見えてきます。このため、株価とバリュエーションの関係について「答え合わせ」をしていくと、割高感を心配する専門家たちの心配をよそに、またしても「株価が正しかった」とすることが出来そうです。
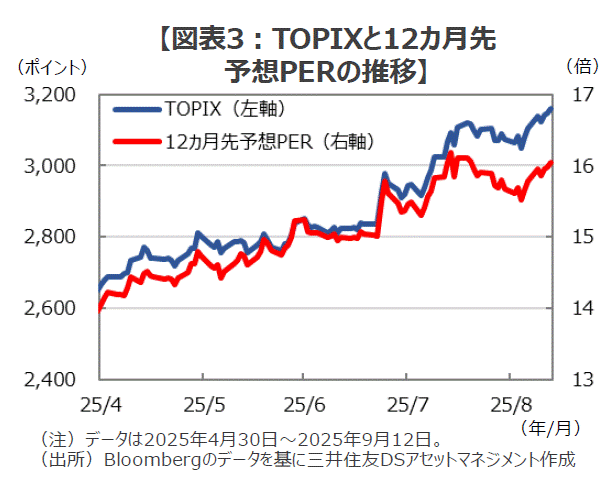
まとめに
日本株が大きく上昇しています。このところの株高については、「景気」「業績」「バリュエーション」の観点から疑問を呈する向きが少なくありませんでした。しかし、そうした「弱気な見方」は、市場参加者の知見の集合体である市場の「先見性」の前に、あえなく屈することとなったのではないでしょうか。
市場はファンダメンタルズの変化に先んじて動く傾向があるため、市場の「先見性」にヒントをもらいながら相場展開を考え、後に、経済指標や企業業績などのデータでその「答え合わせ」をしていくのが、市場参加者としての「謙虚なお作法」とすることができそうです。
確かに、市場も時には読み違え、事の成り行きを大きく見誤ることがあるのも事実でしょう。そう考えると、相場に対峙する上で大切なのは、バックミラーを見ながら将来を予測するような「不思議なチャレンジ」ではなく、市場が送るサインを察知し、仮説を立て、日々答え合わせをしながら仮説をアップデートし続ける(ポジションを変えていく)ことではないでしょうか。



