2025年9月9日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
「適温相場」から「金融相場」へ移行する米国株式市場
2019年のデジャヴと過渡期相場の「凌ぎ方」
9月5日に発表された米雇用統計は、非農業部門雇用者数(NFP)の増減が前月比2.2万人増加にとどまり、失業率も2021年以来の水準となる4.3%に上昇するなど、改めて雇用環境の失速を印象付ける結果となりました。最近の米国株式市場は、関税交渉の進展、好調な企業業績、そして、米連邦準備制度理事会(FRB) による利下げ期待を背景に順調な戻り相場が続いてきました。しかし、内需主導の米国経済のエンジンともいうべき「雇用」の変調が鮮明になってきたことから、今後の米国株式市場は一筋縄ではいかない展開となりそうです。
1. 雇用の失速で終わる「適温相場」
■9月5日に発表された8月分の米雇用統計は、NFPが前月比+2.2万人(市場予想:+7.5万人)、失業率は前月の4.2%から2021年以来の水準となる4.3%に上昇(同4.3%)しました。また、6月分のNFPは、コロナ禍の最中の2020年12月以来の前月比マイナスとなる▲1.3万人へと改定され、「米雇用環境の失速」を印象付ける結果となりました(図表1)。
■今年の米国株式市場は4月のトランプ関税の発表を受けて大荒れとなり、S&P500種指数は高値から一時約2割調整する大荒れの展開となりました。しかし、①中国との関税報復合戦の収束や主要国との関税交渉の進展、②好調な企業業績、そして、③FRBによる利下げ期待などを背景に上昇に転じ、その後は長期の上昇基調に回帰してきました。
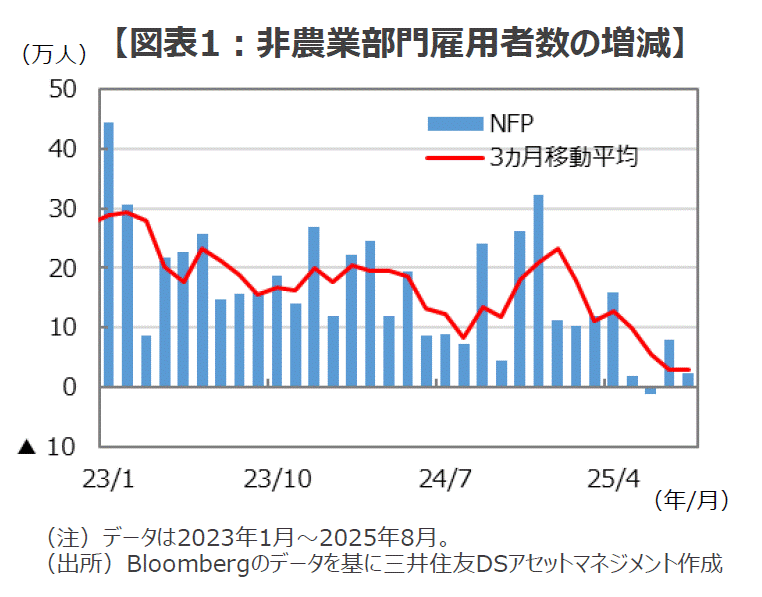
■こうした最近の戻り相場は「程よい経済成長」と「利下げ期待」が同居する、良いとこ取りの「適温相場」であったと言えそうです。しかし、8月と9月に発表された米雇用統計の結果を受けて、米国のGDPの約7割を占めるとされる個人消費を支える「雇用」の失速が確認されたことから、絶妙なバランスを保ってきた「適温相場」は継続が難しくなってきたように思われます。
2. 2019年のデジャヴ(既視感)
■現在の米国の政策金利は、先日のジャクソンホールでの講演でのパウエルFRB議長の言葉を借りれば「引き締め気味の水準」にあります。また、ベッセント財務長官が先日「どんな金利モデルで見ても、政策金利は1.5%~1.75%低い水準にあるべき」と発言しているように、ひとたび経済が変調をきたせば「相当な利下げ余地がある」とすることができそうです。このため、仮に、FRBが積極的な利下げに踏み切るなら、米国株式市場は最近の「適温相場」から、景気減速への懸念と金融緩和期待がせめぎ合う「金融相場」へ移行していくことが想定されます。
■こうした観点から、今年後半以降の米国株式市場を展望する上で参考にしたいのが、同じく米国の利下げ局面にあった2019年の相場展開です。というのも、当時の状況の相場を振り返ると、単に「利下げ局面であった」というだけでなく、①トランプ関税をきっかけに経済が変調をきたし、②嫌な気配を察知した株式市場(S&P500)がファンダメンタルズに先んじて大きく調整し、③その後、雇用環境が急速に悪化して、④FRBが連続利下げに踏み切ることとなったからです。
■そして、2019年の経済やマーケットの動きを時系列で追っていくと、不思議なくらい似通った展開、波及経路、時間経過をたどっていることに驚かされます(図表2)。
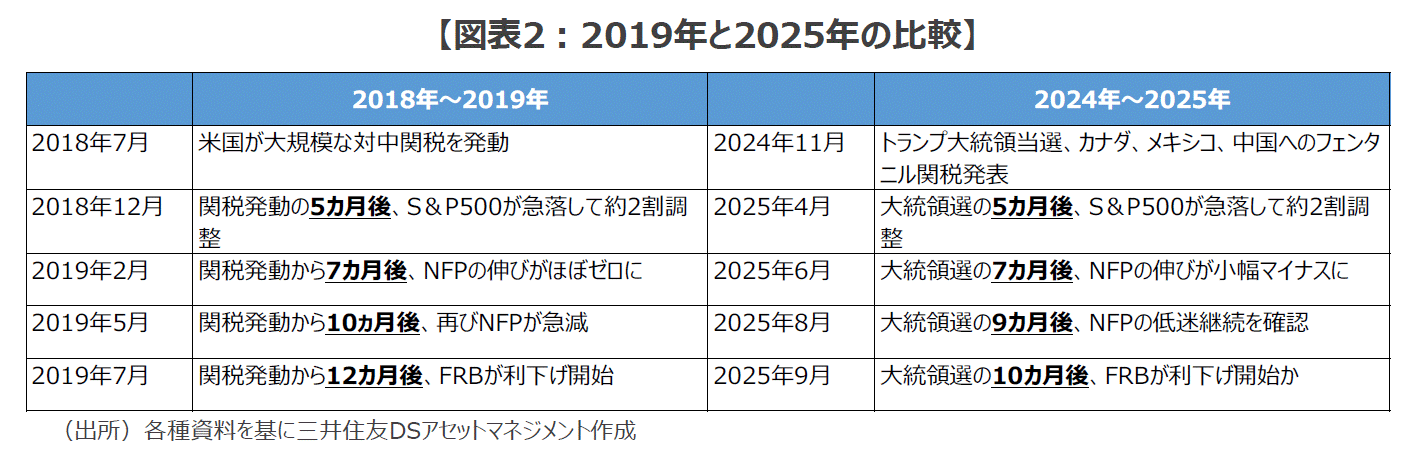
■もちろん、経済や株価を動かす要因は様々で、過度に単純化されたアナロジーを盲信するのは危険でしょう。とはいえ、株価はバリュエーション(PER)と企業業績(EPS)の掛け算ですから、PERに大きな影響を与える金融政策とEPSを左右する経済環境が近しいこと、そして、「関税」という同様な「外部的ショック」が一連の変化の起点となっている共通点を考えると、単なる「偶然」で片づけてしまうのも違うように思えてきます。そこで、次に、2019年の米国の株式市場を振り返りながら、今後の相場を読み解くヒントを探ってみましょう。
3. 2019年をヒントに考える投資戦略
■2019年の米国株式市場の推移を振り返ると、①年前半の1~4月は前年12月の急落からの戻り局面で、続いて、②5、6月は雇用不安から調整局面となり、その後、③7月末までは利下げ期待で堅調推移となるも、④8~10月にかけては利下げが「材料出尽くし」となって調整局面となり、最終的に、⑤年末にかけては「金融相場」に本格移行して上昇軌道に回帰する、といった展開でした(図表3)。
■2019年の相場展開からまず気づかされるのは、利下げが開始されると「材料出尽くし」となることに加え、金融緩和の効果が実体経済に波及するまで時間を要するため、「金融相場」による本格的な相場上昇に移行するまでタイムラグが生じることです。
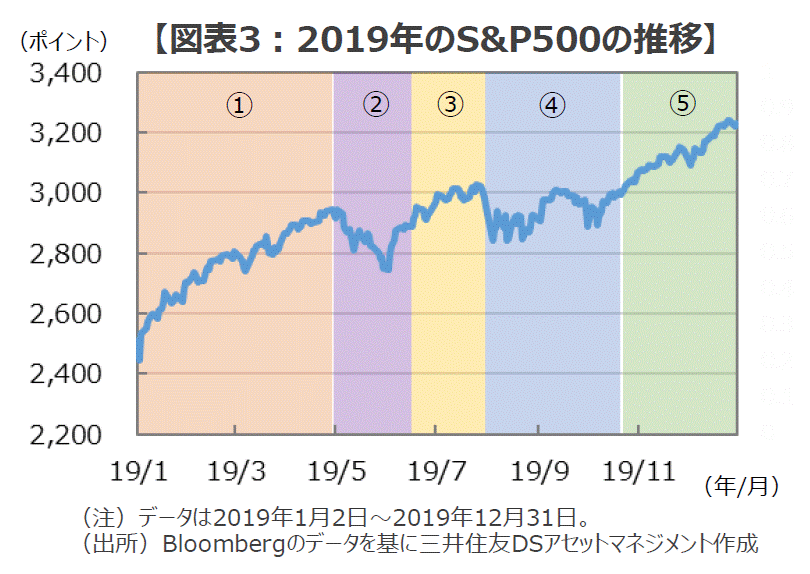
■こうした移行期間は、投資家としては冴えない経済指標や企業業績の発表に耐える、「凌ぐ時間帯」と言い換えることができるかもしれません。ちなみに、2019年7月末のFRBによる利下げ開始以降のVIX指数(市場が織り込むS&P500種指数の変動率)を見ると、そうした市場の「不安感」を映してしばらく高水準で推移していることが確認できます(図表4)。
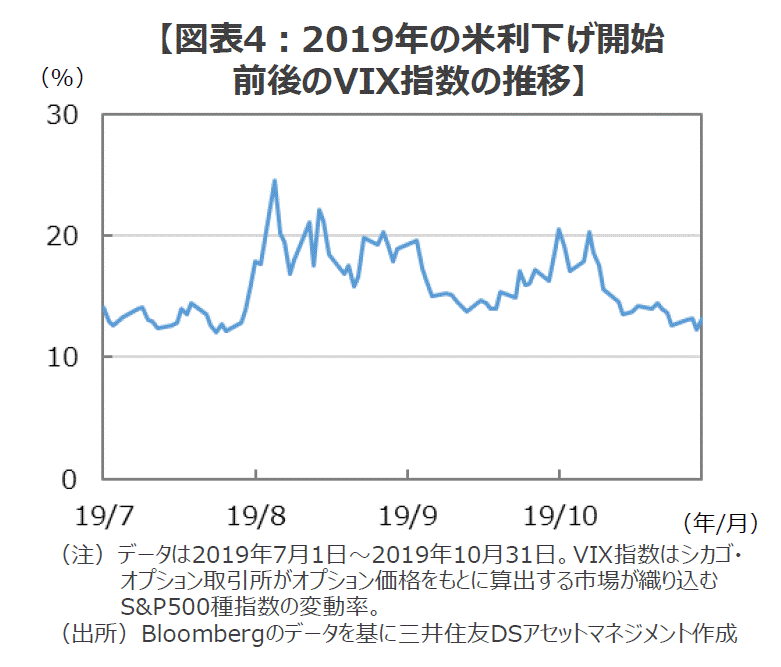
金融相場の業種動向
■次に、FRBによる利下げが開始された2019年7月31日以降、同年12月末までのS&P500の業種別の騰落状況を確認すると、①ハイテク株を含む「情報技術」が好調な一方、②「エネルギー」「資本財・サービス」「素材」といった、いわゆる「景気敏感株」が不振でした。また、③「ヘルスケア」が好調な一方で「生活必需品」が冴えないなど、「ディフェンシブ株」の中でも明暗が分かれる展開となりました(図表5)。
■こうした物色動向は、典型的な「金融相場」の特徴と言ってよさそうです。というのも、景気への不安と金利低下が同居する「金融相場」では、①景気変動の波を乗り越えていく独自の成長要因を持ち、②長期の成長期待への株価評価が金利低下で膨らむことで、大手ハイテク株や新薬開発による将来の利益成長が期待されるヘルスケア株などへの追い風の相場環境となり易いからです。
■こうした「金融相場」における相場の反応が極端な形として表れたのが翌2020年で、「コロナ禍」という極限状態が市場の不安感を高める一方、大幅な金融緩和が「金融相場」の特徴を増幅することで、極端な「ハイテク相場」が出現したことは皆さんご記憶の通りです(図表6)。
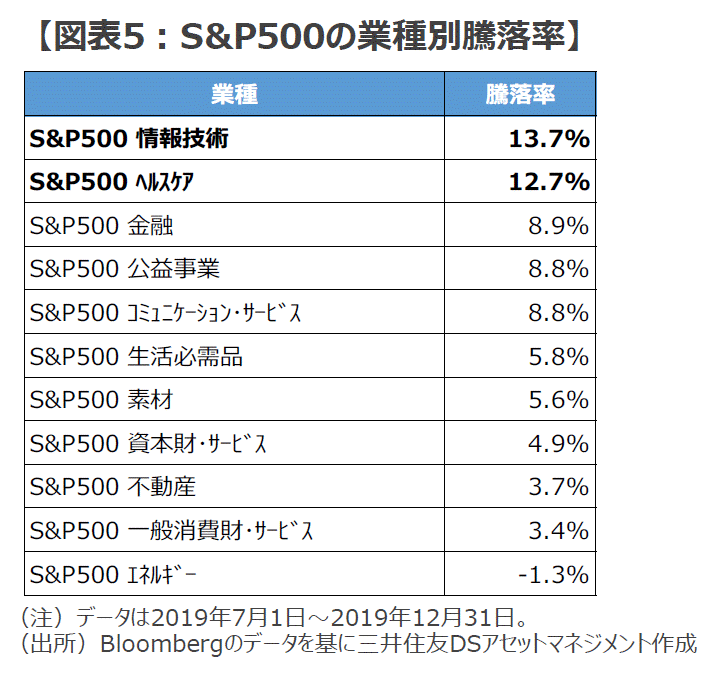
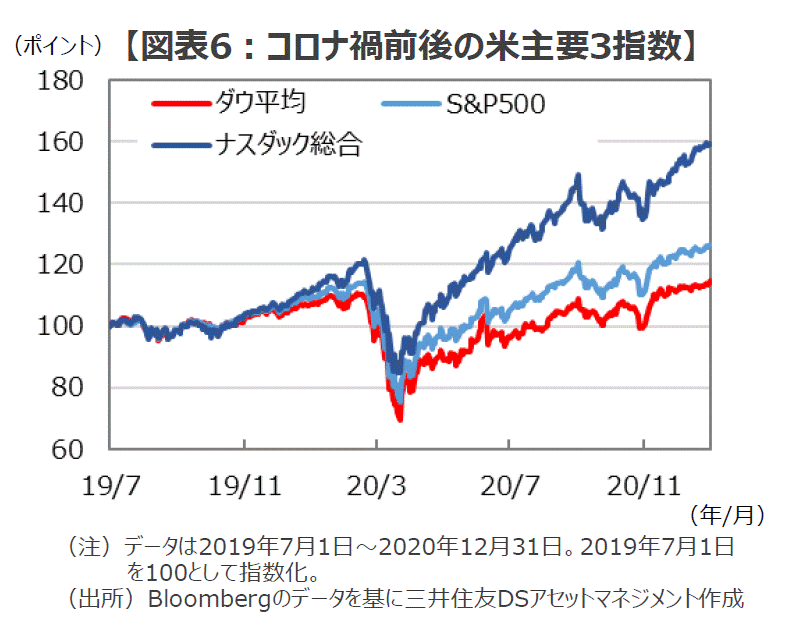
ビッグテックの間でも分かれる「明暗」
■2019年の大手ハイテク株の値動きをみると、一口に「ビッグテック」といってもその事業内容には個性や各社固有の成長ストーリーがあって、株価は相当なばらつきがありました。例えば、2019年7月末のFRBによる利下げ以降の株価推移をみると、ウェアラブル端末やサービス事業が好調だったアップルや、戦略分野のクラウドビジネスが好調だったマイクロソフトは株価が好調に推移しました。その一方、広告やネット通販など景気敏感な側面がある本業の減速懸念から、アルファベット、メタ・プラットフォームズ、アマゾン・ドット・コムの株価は見劣りする展開となり、同じ「ビッグテック株」の中でも、市場選別、メリハリが効いていたことがうかがわれます。
■こうした相場の傾向を最近の状況に置き換えるなら、米中の覇権争いの最前線となっているAI関連や、AI向け大規模データセンターで電力需要が急増する電力関連ビジネスなどが、「個社の成長要因」として引き続き注目を集める一方で、そうした戦略分野での事業展開で見劣りする銘柄は、ハイテク株といえども景気変動の影響を少なからず受けることとなりそうです。
金融相場の「バリュエーション」の考え方
■2019年、2020年のような「金融相場」では、①金利低下が株主の期待するリターン水準(資本コスト)を低下させ、②長期の利益成長を織り込むグロース株のバリュエーションを拡大させ、さらに、③そうした銘柄が上昇して市場全体の時価総額に占めるウエイトが上昇することで、主要な株価指数の予想PERは大きく上昇する傾向が見られます(図表7)。
■最近、市場関係者の間では、米国株式市場の上昇につれてPERが拡大していることを懸念する向きも多いようです。しかし、「金融相場」を動かすメカニズムを理解していれば、こうした平時と比べて高めのバリュエーションについて、あまり神経質にならない方が良いことがご理解いただけるのではないでしょうか。
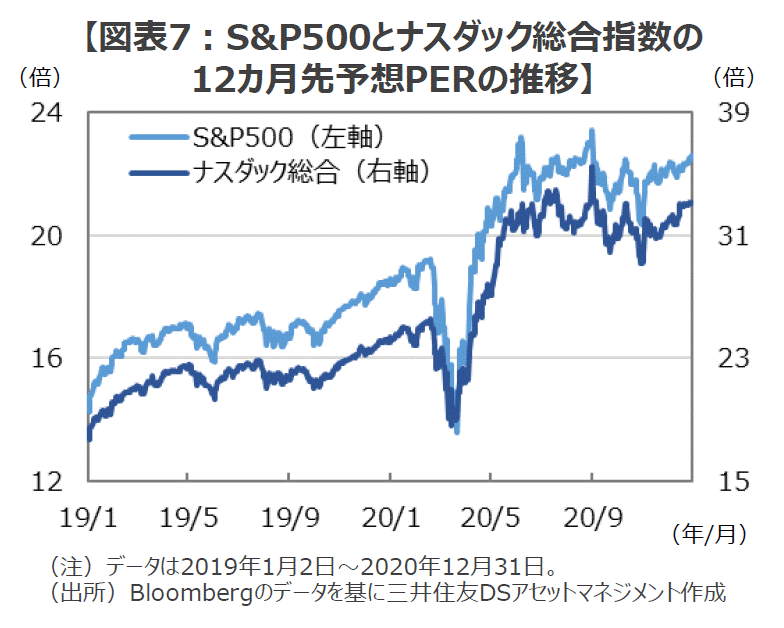
まとめに
米国の雇用環境の悪化と今後期待されるFRBによる利下げにより、今後の米国株式市場は「適温相場」から「金融相場」へ移行する可能性が高そうです。
今年後半の相場を展望する場合、トランプ関税、株価の大きな調整、雇用環境の減速、そしてFRBによる連続利下げがあった、2019年の相場展開が参考になりそうです。
もし、こうした見立てが的外れでないなら、今後の米国株式市場は、①利下げ後は「凌ぐ時間帯」に入り、タイムラグを経て上昇軌道に回帰すること、②独自の成長要因があって金利低下が追い風となるハイテク株がフォローの風を受けること、そして、③「金融相場」では株価バリュエーションは総じて拡大し易いこと、などを念頭に投資戦略を組み立てていく必要がありそうです。
※個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。



