2025年8月25日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
日本の財政は「ギリシャよりもよろしくない」のか
円金利上昇の実像と今後の展開
日本の長期金利が上昇しています。10年国債利回りは約17年ぶりに1.6%台まで上昇し、30年債は1999年の発行開始以降で初の3.2%台まで上昇しています。そんな日本の国債市場をざわつかせているのが、「財政悪化」懸念です。特に、一連の選挙結果を受けて野党主導の消費税減税への警戒感が広がっているようです。日本の財政については巨額の政府債務の存在が度々取り上げられますが、少なからず誤解されている部分もあるようです。そこで今回は、日本財政のファクトチェックを行いつつ、今後の円金利の動向へのヒントを探ってみたいと思います。
1.高水準の日本の政府債務
■日本の財政といわれてすぐ思い浮かぶのは、巨額の政府債務の存在でしょう。その総額(国、地方、社会保障基金の合計)は2025年4月で約1,466兆円、対GDP比で約235%に達し、主要先進国の中では群を抜いて悪い状況にあるとされています(図表1)。
■こうした状況を意識してか、石破首相は今年5月19日の参議院予算委員会で、「日本の財政状況はギリシャよりもよろしくない」と発言して、国内外に波紋を広げることになりました。しかし、ギリシャの政府債務の対GDP比は2020年の約210%をピークに低下傾向にあり、2025年には約142%まで低下してきていると推計されています。つまり、こと政府の債務残高に関する限り、日本の状況はギリシャよりも遥かに悪く、引き合いに出すのはむしろギリシャに失礼と言って良さそうです(図表2)。
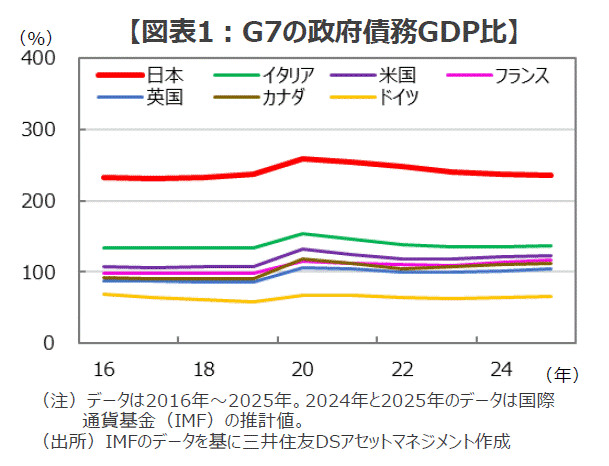
■2024年の衆議院選挙、2025年の東京都議選、そして、同年の参議院選挙と連立与党が3連敗し、さらに衆参両院で過半数を失った結果、日本政府は野党の協力なしに予算を編成できない状況に追い込まれています。このため、野党の多くが主張する消費税減税を始めとする積極的な財政政策が実現する可能性が高まることで、市場参加者の一部には巨額の政府債務を抱える日本財政の持続性を材料視する向きが増えつつあるようです。
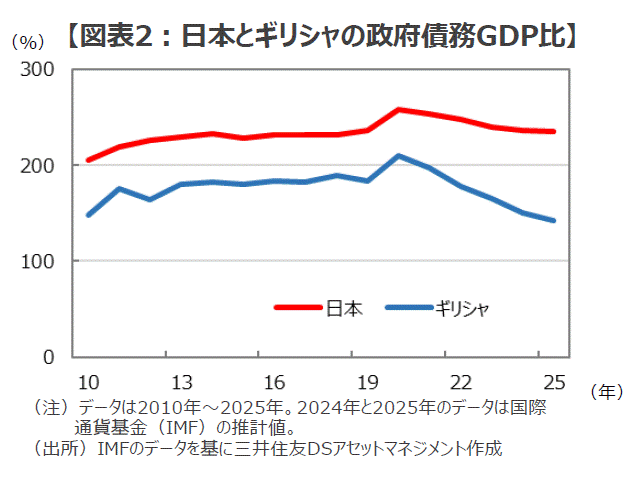
2.日本財政のファクトチェック
■巨額の政府債務を抱えているにもかかわらず安易な減税策が採られれば、信用不安で2011年の「ギリシャ危機」や2022年の英国の「トラスショック」のように(図表3)、日本の長期金利が急騰してもおかしくないでしょう。しかし、日本の長期金利の指標である10年物国債利回りは、なぜか7月20日の参院選後も比較的落ち着いた動きが続いています。
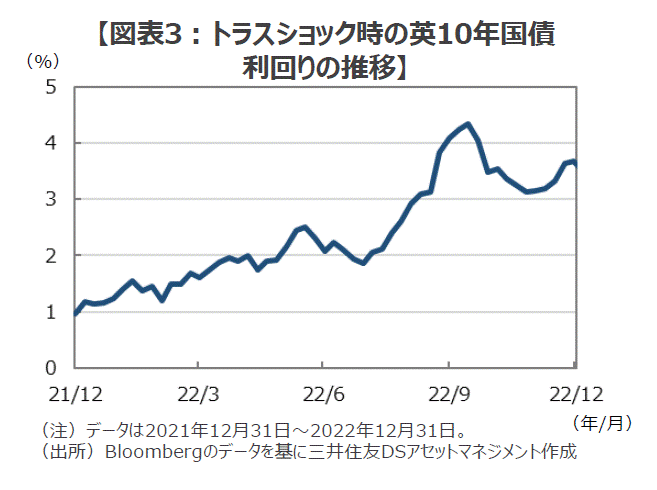
ネットの政府債務残高
■「相場が先んじて与党の敗北を織り込んでいた」と見ることもできますが、もう一つ考えられるのは、日本の財政が「政府債務のGDP比」が示すほどには悪くない、とする仮説です。そこで、日本の財政状況を債務だけでなく保有資産も勘案して見てみましょう。というのも、個人や会社の借金が過大かどうかを判断する場合、単なる借金の規模を見るのではなく、資産と借金を両方見た上で判断するのが普通だからです。そして、お隣の田中さんが1億円のローンを組んで豪邸を建てたとしても、銀行預金が2億円あれば単に羨ましいだけで何の問題もないでしょう。
■そこで、政府債務からその保有資産を引いた「ネット政府債務のGDP比」を見ると、日本の数字は約134.2%とイタリアとほぼ同水準で、欧米の主要国よりもやや悪い程度、ということが確認できます(図表4)。
■さらに、この「ネット政府債務のGDP比」の推移を時系列で見ると、日本の財政状況は着実に改善傾向にあり、90%台で高止まりするG7平均に向かって収斂しつつあることが確認できます(図表4)。
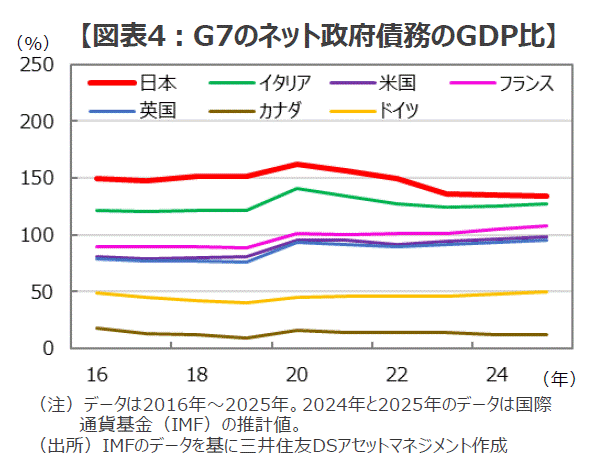
連結財務諸表でみる日本財政
■日本の財政を大まかにとらえると、税収を財源に教育・防衛・社会保障などの支出を計上する「一般会計」と、保険料や使用料などを財源に年金やエネルギー政策などへの支出を計上する「特別会計」で構成されています。これに国立大学や公立病院などの独立行政法人を加えた、国の連結財務諸表に相当する「連結財務書類」を財務省が毎年度集計し、公表しています。
■この「連結財務書類(令和5年度)」を見ると、日本の政府資産は計約1,048.9兆円、債務は計約1,576.8兆円で、負債から資産を引いた「ネット政府債務」は約527.9兆円と前年から約53.9兆円も減少して、2024年の日本の名目GDP約609.3兆円の約86.6%に低下しています(図表5)。
■ちなみに、同様な数字を諸外国と比較すると、「連結のネット政府債務のGDP比」は、米連邦政府は約136.7%、英国は約88.1%となっています(図表5)。つまり、企業会計では当たり前の子会社を含む「連結財務諸表」で見る限り、「日本の債務水準は概ね英国並みで、米国よりはかなり健全」と言ってよさそうです。
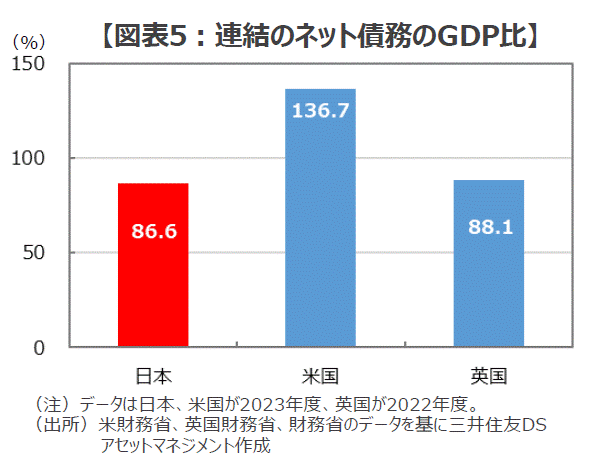
デフレ脱却で現実味を増す日本の財政健全化
■資産を考慮すれば日本の財政はそれほど悪いわけではないと話を振ると、「バランスシートでは確かにそうだが、高齢化で社会保障費がかさみ財政赤字が深刻だ」と仰る方も少なくないでしょう。そこで、国の財政の健全性を見る代表的な指標である基礎的財政収支(プライマリーバランス、歳入から利払いを除く歳出を引いた収支)を見ると、政府の直近の試算では2025年度は約3.2兆円の赤字が見込まれています。
■「それ見たことか、ひどいものだ」と言われそうですが、日本のプライマリーバランスの対GDP比は2024年の実績値で▲2.2%、G7中では7カ国中4位、そして、G7平均の▲2.34%より僅かとはいえ健全な水準にあります。ちなみに2024年は約13.9兆円の補正予算を組み、政府支出で約21.9兆円もの大規模な経済対策を行ったにも関わらず、プライマリーバランスの対GDP比がG7の平均値並みであったことから、先進国の中では財政的にかなり余裕があるようにも思えてきます(図表6)。
■さらに意外なことに、日本のプライマリーバランスは今後大きく改善していく可能性が指摘されています。というのも、今年8月7日の政府経済財政諮問会議に提出された内閣府の資料「中長期の経済財政に関する試算」を見ると、国と地方合算の日本のプライマリーバランスは、2026年度には対GDP比で0.5%程度の黒字化が見込まれているからです(図表7)。
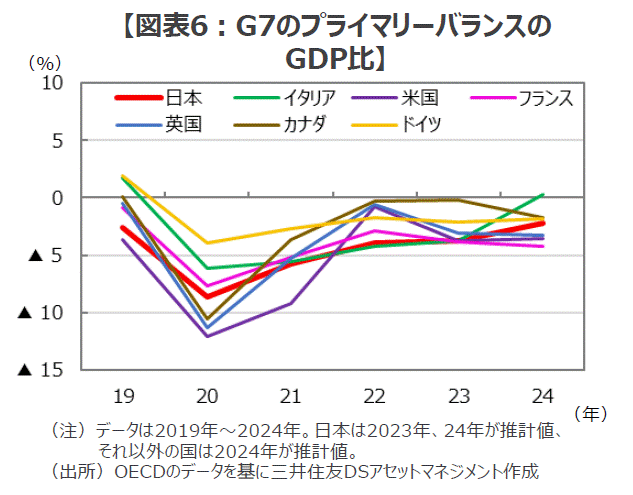
■この政府試算は過去の日本の経済成長率(名目GDPで年率1%弱のプラス成長)が続く「過去投影ケース」に基づくものですが、名目GDP成長率が3%前後で推移する「成長移行ケース」では、日本のプライマリーバランスのGDP比は2026年度に黒字化した後、2034年度にかけて+1.9%まで改善するものと試算されています。
■8月15日に発表された2025年4-6月期の日本の経済成長率は、名目GDPが前期比年率で+5.1%となりました。こうした名目GDPの成長は一時的な現象ではなく、日本の物価上昇が鮮明になった2022年4月以降に、インフレの高止まりとセットで継続していることが確認できます。
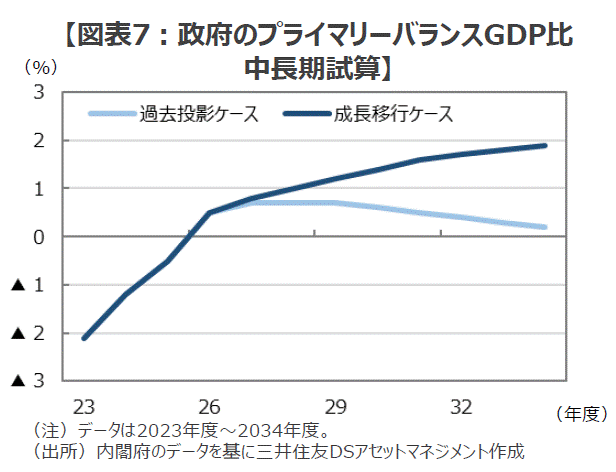
■仮に、今後もデフレ脱却により日本の名目GDPが3%前後の成長を続けるようなら、政府の言う「成長移行ケース」が現実となり、現在はG7平均並みの日本のプライマリーバランスは、相対的に上位にランクアップする可能性が高まりそうです。
3.日本の長期金利の今後
■これまで見てきた点を整理すると、日本の財政は①保有資産を考慮すると単純な政府債務の残高が示すほど悪くはなく、②政府の連結バランスシートやプライマリーバランスを見る限り財政悪化の深刻度は他のG7諸国との比較でそれほど悪い状況にはなく、③デフレ脱却で名目GDPの成長が定着すれば、プライマリーバランスのGDP比も黒字化が定着する可能性が高くなる、といったところでしょうか。
■こうした数字を見る限り、「財政悪化懸念で日本の長期金利が上昇する」というストーリーは、かなり大げさなものに聞こえてきます。こうした「日本財政の悪化懸念」への違和感をさらに強めているのが、債券の信用リスクの保険料に相当する日本のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の動きです。指標となる5年物の推移を見ると、2011年3月の東日本大震災の直後に一時的に大きく上昇したことはありましたが、それ以降は低下傾向が鮮明で、近年は低水準での推移が続いています(図表8)。
■つまり、損得勘定にシビアな市場が冷静に判断する日本の財政破綻リスクは、極めて限定的と言えそうです。
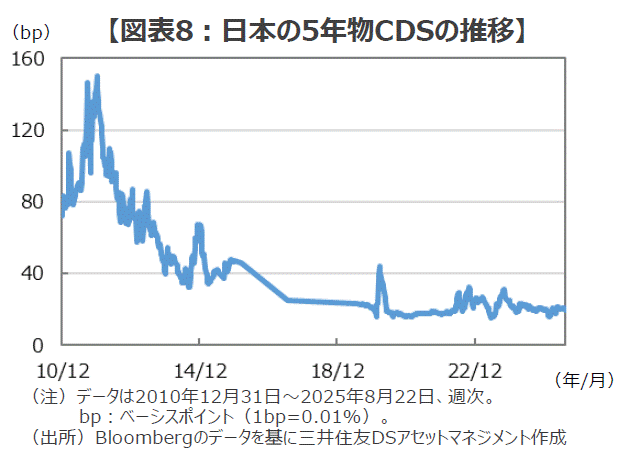
円金利上昇の実像
■では、いったい何が最近の日本の長期金利上昇をドライブしているのでしょうか。債券市場の動きに目を凝らしていくと、3つの大きな力が働いていることが確認できます。
■まず一つ目は、日銀による金融政策の正常化です。日本の10年国債の実質金利(国債利回りから市場が織り込む期待インフレ率を引いたもの)を見ると、日本で2022年以降にインフレ圧力が顕在化する中で長期金利を意図的に低く抑え込んだ結果、2021年1月にはゼロ%近辺であった実質金利が大きくマイナスとなり、その後の金融政策の正常化の過程で再び大きく上昇してきたことが確認できます(図表9)。
■つまり、長期金利を抑え込んできた「イールドカーブコントロール」に代表される異例の大規模緩和政策が解除されることで、実質金利が徐々に普通の水準へ向かって上昇してきたことが円金利上昇の一つ目のドライバーであるとすることが出来そうです。
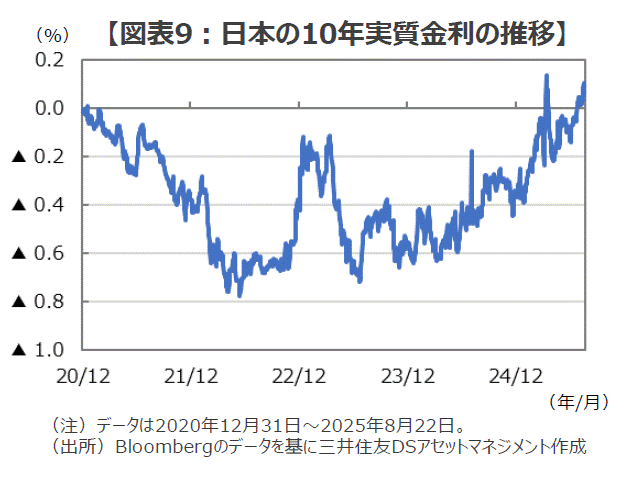
■二つ目の要因として挙げられるのは、日銀に金融政策の正常化を迫る事になった、デフレ脱却にともなうインフレ傾向の定着です。日本の消費者物価指数(CPI)前年比上昇率は2022年4月に2%を突破して以降、既に3年以上も高止まりが続いています。このため、緩和的な金融政策による弊害、例えば極端な円安や、資産価格の上昇といった副作用が目立つようになってきたことで、日銀による金融政策の正常化への強い圧力となり、円金利の上昇をドライブしてきたとすることが出来そうです。
■そして、円金利上昇の三つ目の要因は、こうしたインフレの高止まりと政策金利の正常化への動きが「ニューノーマル」として認識されるようになることで、市場が織り込む期待インフレ率が徐々にCPIにさや寄せする形で押し上げられてきていることです。ちなみに、市場が織り込む10年の期待インフレ率は、2021年の初頭から緩やかに上昇を続け、これまでに約1.6%まで上昇してきています(図表10)。
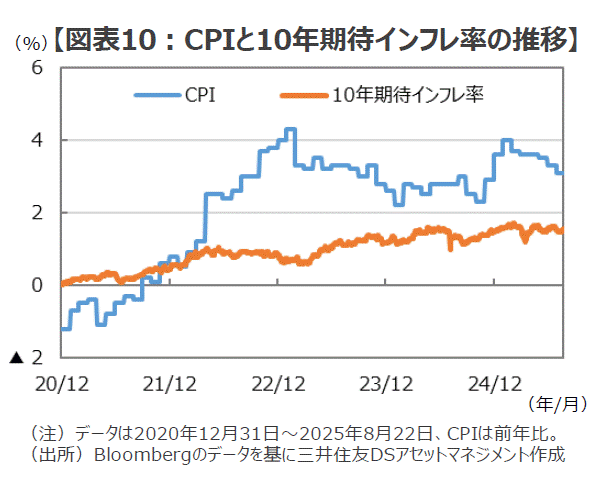
■つまり、日本の金利上昇をドライブしてきたのは、①人為的な長期金利のコントロールが終了したことによる実質金利の復活、②日銀の金融政策の正常化を促したインフレの定着、そして、③市場の織り込む期待インフレ率がCPIの高止まりを見ながら上昇してきたこと、とすることが出来そうです。
■一方で、ここ数年の日本の長期金利上昇局面では、日本の財政事情はこれまで見てきたように緩やかな改善傾向にあります。一般に、インフレの時は借り手に有利、貸し手に不利とされますが、日本でインフレと名目GDPの成長トレンドが定着しつつある中で、日本の財政事情は数字上、緩和方向への構造的な圧力がかかる事となります。このため、最近の金利水準に至る過程では、財政悪化懸念と長期金利の上昇にはあまり関係がないように思われます。
今後の円金利の展望
■現在の円金利の上昇が①金融政策の正常化、②インフレの定着、そして、③市場の期待インフレ率の上昇に起因しているとすれば、今後も円金利には継続的に上昇圧力がかかることとなりそうです。というのも、政府と日銀は連携しながら大規模金融緩和からの出口戦略を「ゆっくり、慎重に」進めていくことで、今後も継続的に「金融政策の正常化」による金利上昇圧力がかかり続ける可能性が高いからです。
■また、日本の実質長期金利を主要先進国と比較すると、ゼロ%付近まで上昇してきたとはいえ依然として極端に低い水準にあることは変わりません(図表11)。このため、米国並みとはいかないまでも、欧州の主要国並みに上昇すると仮定すると、実質金利が正常化するだけでも更に1%前後は金利上昇余地があることになります。
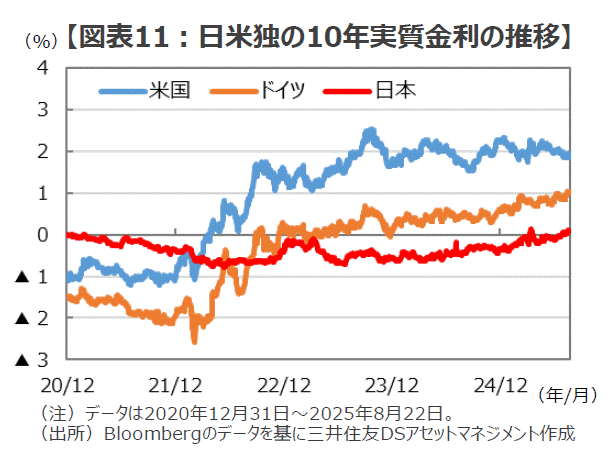
■さらに、市場が織り込む期待インフレ率とCPIの乖離を見ても、日本の期待インフレ率が国際比較で突出して低いことが確認できます(図表12)。これは、日本の市場参加者の多くが、いまだに「日本のデフレ脱却」に半信半疑であることがその背景にありそうです。とはいえ、食品インフレの深刻化などもあって、なかなかCPIが下がってこない中で市場参加者の「インフレ目線」が切り上がっていくことで、期待インフレ率と実際の物価指数の乖離は今後も徐々に解消に向かうのではないでしょうか。
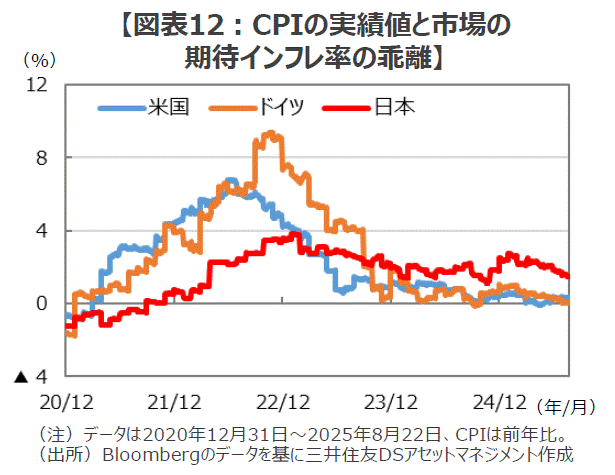
■つまり、①金融政策の正常化が今後さらに進展し、②その過程で実質金利が上昇し、さらに、③期待インフレとインフレの実績値の乖離が収斂していく中で、日本の市場金利には更に上昇圧力がかかり続ける可能性が高いように思われます。その一方で、日本の財政事情はこれまでも円金利の上昇をドライブする主たる原動力とはなっておらず、今後、デフレ脱却と名目GDPの成長が定着することを想定した場合、税収の上振れや日本経済の規模拡大から、円金利への影響は限定的なものに留まるのではないでしょうか。
■このため、仮に、日本の「比較第一党」と「第二党」の連携により、大規模な消費税減税が回避されたとしても、円金利の上昇トレンドを押しとどめることは難しいのではないでしょうか。
まとめに
今から約16年前、人口減少による税収減などから「財政再建団体」に指定された北海道夕張市は、職員の削減と約2割の給与(基本給)カットによる歳出削減を柱とする財政再建策に着手しました。一方、人事院は今年度の国家公務員の給与改定で、平均+3.62%の賃上げを勧告しました。もし、日本の財政が本当に危機的な状況にあるならば、こうした34年ぶりの賃上げが実施されることは何とも不可解と言わざるを得ないでしょう。
政府が公表している国の保有資産を考慮したネットの負債残高や、プライマリーバランスの改善傾向を見る限り、日本の財政事情は巷で語られる悲惨なイメージとはかなり乖離があるように思われます。
日本の長期国債利回りが上昇してきた主因は、デフレ脱却による金融政策の正常化、マイナスの実質金利の解消、そして、インフレ傾向の定着による市場の期待インフレの上昇が主因であって、財政悪化はあまり関係がないように思われます。こうした円金利上昇にまつわる原因と結果を誤解したまま市場でリスクテイクしてしまうと、想定外の動きに足元をすくわれかねないため注意が必要でしょう。



