2025年7月2日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
景気は足踏み、業績は不透明でも
日本株の「意外高」が続くワケ
日経新聞は6月26日、中国系企業が日本を経由して米国に合成麻薬フェンタニルの原料(前駆体)を密輸していた疑惑を大々的に報じました。仮に、この報道が事実であったならば、日本にとって大きな問題に発展する可能性があります。というのも、現在日米両政府は関税・通商交渉の最中にありますが、米国は合成麻薬及び、その前駆体の密輸を理由にカナダ、メキシコ、中国の3カ国に対して高率の追加関税を課しているからです。仮に、日本が合成麻薬の密輸に関与していたと見なされれば、日米関係の「新たな火種」になりかねないでしょう。
1.日経スクープ報道の衝撃
■日経新聞(以下、日経)が「独自」の調査報道で、中国系企業が日本から合成麻薬フェンタニルの原料(前駆体)を米国へ密輸していた疑惑を報じました。日経は米国におけるフェンタニルの取引に関する裁判記録の中からの日本に関する記述を発見し、それをきっかけに詳細な調査を実施して今回のスクープに繋げたと伝えています。
■この日経報道は、日本政府の関税交渉を難しくする可能性があります。というのも、米国では合成麻薬の乱用が深刻な社会問題となっていて(図表1)、トランプ政権はフェンタニル対策を最重要の政策課題として取り組んでいるからです。そして、米国は合成麻薬の流入を理由に2025年2月には中国に10%、同年3月にはカナダとメキシコに25%の追加関税を発動しています。
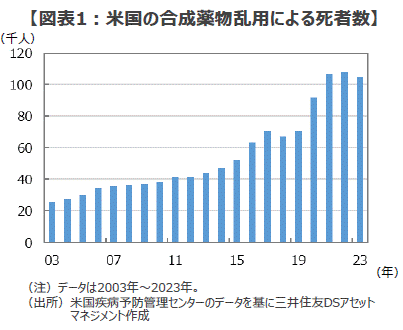
重要な政治日程直前の調査報道
■この報道を目にしてまず考えさせられるのは、なぜ「このタイミング」でこの調査報道が出たのか、という点です。日経報道が出た6月26日は国連が定める「国際麻薬乱用・不正取引防止デー(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)」ですが、それ以上に重要なのは、6月24日に日本政府が決定した参議院選挙(7月3日公示、7月20日投開票)の直前という「政治日程」です。
■ちなみに、26日の日経報道の当日、グラス駐日米大使は「中国からの合成麻薬前駆体の密輸には中国共産党が関与」し、「日米が協力して日本経由での前駆体の密輸を防ごう」と公式アカウントでツイートして、日本側を攻撃するような姿勢は今のところ見られないようです。とはいえ、7月9日の関税発動の猶予期限を目前に、トランプ大統領が、「日米交渉合意の可能性は低い」「関税発動の猶予は考えてない」「日本の相互関税は30~35%」などと発言し、日本を突き放すような姿勢を鮮明にしている点は大いに気掛かりなところです。
2.すれ違う日米関係
■重要な政治日程を前に大きな影響が懸念される調査報道が出た背景に、米国側の意図を汲み取ろうとするのはある種の「陰謀論」と言われても仕方がないため、厳に慎むべきでしょう。とはいえ、ここもとの日米関係にまつわる出来事を見ていくと、かなり「ぎくしゃく」していたことは間違いなさそうです。
■まず、トランプ関税の発表を受けてスタートした日米通商交渉ですが、日本側は石破総理と同郷で自民党総裁選で石破陣営の事務総長を務めた赤澤大臣を交渉担当に任命し、日米間での本格的な交渉が始まりました。そして、赤澤大臣が渡米して臨んだ第1回目の日米交渉ではトランプ大統領も顔を出し、さらに、米国は日本が警戒する「為替」についての議論を封印して、日本と連携して対中包囲網を構築したい米国側の友好ムードが漂う協議だったようです。
■しかし、日本政府は対中包囲網への参加はもちろん、早期のディールによる妥結を急ぐことはせず、日米交渉は思いのほか長期化して現在に至ります。そして、米中の関税合戦が過熱する最中、日本の与党大物政治家が続々と訪中して中国政府高官と会談を持ち、さらに、日中の有力政治家が仲良く「スクラムを組む」写真が世界中に配信されました。
■その後、イギリスを除く同盟国との対中包囲網の構築に手間取る米国は、4月上旬には「株、債券、米ドル」のトリプル安に見舞われ、対中交渉で大きな譲歩に追い込まれることになります(図表2、3)。こうした状況に、トランプ政権が不満を持ったとしても、決しておかしくないでしょう。
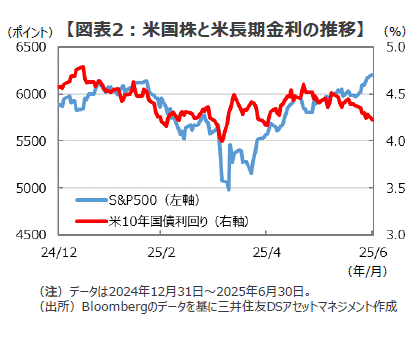
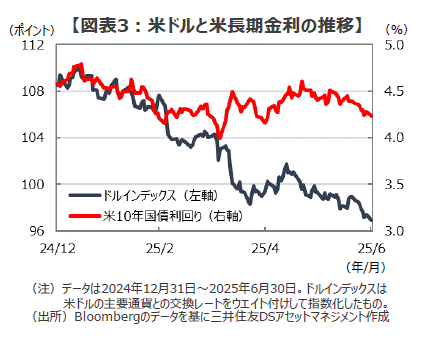
安全保障政策での西側諸国と日本の微妙な距離感
■こうした日本の「独自の立場」をさらに際立たせたのが、中東情勢への対応です。6月13日にイスラエルがイランへの空爆を開始すると、西側の主要先進国の多くがイスラエル支持を表明する中、日本政府は中国やロシアと同様に、イスラエルを厳しく非難しました。
■その後、6月15日にカナダで開催されたG7サミットでは各国がイスラエル支援を改めて表明、日本のイスラエル批判が際立つ結果となりました。さらに、G7の開催に合わせて米側から提案のあった2プラス2(日米の外務・防衛担当閣僚による安全保障協議)を日本側が断ったと報じられています。こうした報道が事実なら、国際情勢が緊迫化する中で同盟国との緊密な連携を確認したい米国側としては、相当な意外感を持って受け止められた可能性を否定できないでしょう。
■さらに、6月24〜25日にオランダ・ハーグで開催されたNATO首脳会議には、トランプ大統領をはじめG7の首脳が勢ぞろいしましたが、例年通り招待されていた石破総理は急遽出席を取りやめました。そして、同じタイミングで中国がかねてより反対していた「NATOの東京事務所開設」の検討中止が報じられました。
■日米交渉の長期化に加え、国際情勢が緊迫化する中での日米関係のすれ違いに、米国がいら立ちを募らせていたとしても決して不思議ではないでしょう。
3.日本株の「意外高」のワケ
■26日の日経報道に前後して、日本株の上昇が加速しています。これまで3万8千円台でもみ合っていた日経平均株価は、あっという間に4万円の大台をクリアして大きく上昇しています(図表4)。そんな日本株の突然の上昇に、驚いている方も少なくないでしょう。
■というのも、現在の日本経済はインフレの高止まりによる実質賃金の低迷からGDPの約半分を占める個人消費が伸び悩み、2025年1-3月期の実質GDP成長率(2次速報値)は前期比年率▲0.2%のマイナス成長となっています。また、トランプ関税の影響が懸念される輸出企業を中心に、日本の企業業績には先行き不透明感が強まっているからです。
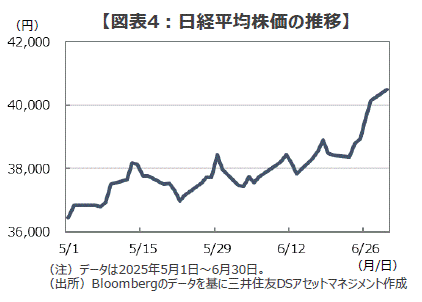
■しかし、今回の日経報道が日米交渉に取り組む日本政府に新たな難題を突き付けていると仮定すれば、話は少なからず変わってきます。というのも、日本政府は参院選直前というこのタイミングで「フェンタニル関税」という新たな交渉カードを突き付けられることで、米国の要求を飲まざるを得なくなる可能性が高まるからです。
■こうした事態は日本政府にとって厳しいものかもしれませんが、こと日本株に関する限りポジティブな影響が期待される点には注意が必要でしょう。というのも、これまで米国は日本に対して①対米貿易黒字の削減、②防衛費の拡大、そして、③消費税をはじめとした非関税障壁の撤廃、を要求してきました。
■もし、これらの米国の要求が現実のものになると、①対米貿易黒字の減少は円安要因に、②防衛費の拡大は景気刺激的な財政政策に、そして、③消費税のカットや廃止は個人消費を刺激して日本経済の成長要因となりそうです。つまり、いずれの要求が実現しても、日本株にポジティブに作用する可能性が高いと言えそうです。
日本株の長期トレンドと日米関係
■更に、日本株にまつわる大局観として指摘しておきたいのが、安定した政権のもとで良好な日米関係が続くことが、長期的な株価にポジティブな影響を与えてきたことです。
■例えば、日米関係を重視する第二次安倍政権が2012年12月に発足すると、日経平均株価はわずか2年半の間にほぼ倍に上昇しました。その一方で、時の総理が「日米中は等距離の正三角形の関係」と発言して日米関係がぎくしゃくした旧民主党政権下では、諸外国の株式市場が上昇を続ける中でも日本株は低迷を余儀なくされました(図表5)。
■これまで日本は米中という大国のはざまで対応に苦慮してきましたが、今回の調査報道の内容は日本を米国側に引き込む有効な「交渉カード」として作用する可能性が高そうです。そして、日本がそうした米国側からの「お誘い」を袖にするようなことがあれば、日米通商交渉の決裂などを通じて政府・与党は厳しい立場に立たされる可能性が高まりそうです。
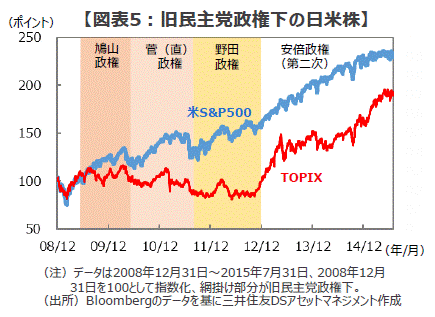
■仮に、そうしたシナリオが現実のものとなった場合、都議選での与党の記録的な敗北を考え合わせると、来るべき参院選の結果やその後の政局に、大きなインパクトを与える可能性を否定できないでしょう。
■米中の対立構図の中で「フェンタニル関税」をカードに日本を米国側に引き込むのが「プランA」なら、カナダとの関税交渉のように「協議打ち切り」で日本の国内政治にインパクトを与えようとするのが「プランB」とすることができそうです。そして、親米保守とされる自民党旧安倍派所属の「コメ担当大臣」の最近の大活躍を見るにつけ、「プランB」のための準備も着々と進んでいるように思えてなりません。
まとめに
日本経由で合成麻薬フェンタニルの前駆体が米国に密輸されていたとの疑惑を報じられたことで、対米交渉に腐心する日本政府は新たな難題に直面する可能性があります。
この調査報道が「図らずも」米国にとっての交渉カードになるとすれば、その背景には、日米政府に対する米国側の不満があったように思えてなりません。
今回の調査報道とタイミングを合わせるかのように、日本株の「意外高」が続いています。その背景には、日本側が米国の要求を受け入れることによる経済面でのポジティブな効果に加え、日米関係を改善させようとする米国の意思を市場が感じ取っているからかもしれません。



