2025年5月9日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
「ベッセントプット」で上昇相場に回帰する米国株
弱気筋が困惑する「想定外の株高」
主要メディアでは相変わらずトランプ関税による世界経済への悪影響を懸念する報道が続く一方、株式市場では米S&P500種指数が5月2日に約20年ぶりの9連騰を記録するなど大きく値を戻し、日本の主要株価指数も4月2日の米相互関税の発表前の水準を回復しています。思いがけない相場の戻りを目の当たりにして、「トランプ関税で景気が悪くなるのはこれからなのに、どうして?」と、その相場展開に違和感を覚える方も少なくないようです。弱気に傾く一部投資家の神経を逆なでするこうした「想定外の株高」の背景には、いったい何が有るのでしょうか。
1.景気悪化はこれからなのに株価大幅反発のワケ
■国内外の主要メディアは、ある種のキラーコンテンツであるトランプ大統領の予測不能な言動とその経済政策を、世界経済の悪化懸念とともに大々的に報じ続けています。このため、経済政策の不確実性に関する「メディア報道の数」などを指数化した米国の「経済不確実性指数」は高水準を続けており(図表1)、日米通商交渉や米中貿易摩擦などの行く末に気を揉む人々の不安を掻き立てる結果となっているようです。
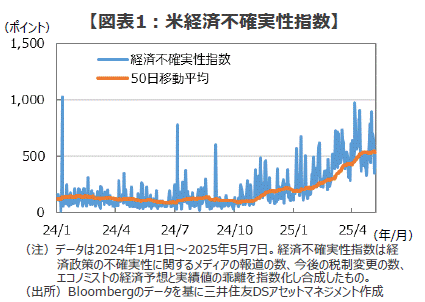
■一方、株式市場では米S&P500種指数が4月8日に前月末比で約11.2%下落して、一時的に5,000ポイントの大台を割り込みましたが、その後、4月9日に相互関税の一時凍結が発表されたことをきっかけに反発に転じ、既に4月2日の相互関税発表前の水準を回復しています。また、こうした動きは日本にも波及し、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)も大きく連れ高しています。
■メディアが声高に危機を伝え続ける中で株式市場が急速に値を戻した直接的な理由としては、トランプ政権が関税政策についての柔軟姿勢や金融市場への配慮を見せたことから、「これは大事には至らない」と市場が感じ始めたことが大きかったように思われます。このため、市場の不安感を示すとされるS&P500種指数のボラティリティ指数(VIX指数)は4月初旬のピークから大きく低下し、同じく米国債市場の不安感を示すMOVE指数も急落しています(図表2)。
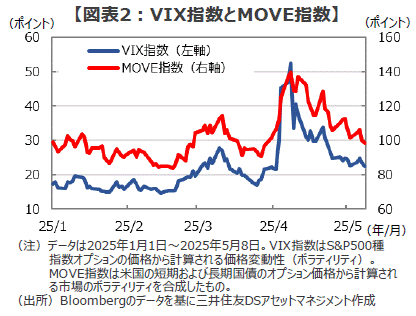
■こうしてみると、メディアではトランプ関税にまつわる騒動が引き続き大きく報じられる一方、市場は国益を重視するトランプ政権がとりうる関税措置の「限界」を見切ることでいち早く「通常モード」の相場に戻りつつあることが、弱気筋が困惑する「想定外の株高」を演出しているように思われます。
2.市場が気付き始めた「ベッセントプット」
■トランプ大統領が巻き起こす「喧騒(けんそう)」をよそに、金融市場が落ち着きを取り戻しつつあるのは、関税についてのトランプ政権の柔軟性を示すニュースもさることながら、そうした変化の背後に控えるベッセント財務長官の存在が大きいようです。ヘッジファンド業界出身で、マーケットのプロ中のプロとも言うべきベッセント財務長官ですが、市場の不安を鎮めようとする言動やホワイトハウス内での影響力の高まりから、ここへきて市場関係者から大きく注目されるようになってきました。
ウォール街の救世主、ベッセント財務長官
■例えば、①トランプ大統領が人民元安や円安を批判した時には「トランプ政権はドル高政策を堅持」と発言し、②4月2日に相互関税の詳細が発表された際には「報復がなければ今回発表の関税率が上限となる(ディールによる低下の可能性を示唆)」と発言、また、③4月上旬に一時的とはいえ米国の株式、債券、米ドルが揃って下げるトリプル安となった局面(図表3、4)ではトランプ大統領に相互関税の一部凍結を促し、さらに、④トランプ大統領がパウエル議長解任の動きを見せた際には思いとどまるよう働きかけた、と伝えられています。
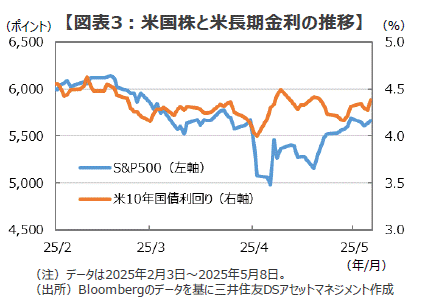
■金融市場が弱気に傾く場面で中央銀行や政府関係者が政策手段を用いて株価を下支えすることを、オプション市場での売る権利の取引になぞらえて「○○プット」と呼ぶことがあります。例えば、米国の中央銀行である米連邦準備制度理事会(FRB)が、金融市場が混乱する場面で利下げにより市場の不安を鎮めようとすることを「FRBプット」と呼ぶのはその典型例でしょう。
■こうした呼び方に倣うなら、トランプ大統領の関税政策についての意外な柔軟性や朝令暮改を通じ、「ベッセントプット」の存在が市場に認識されるようになったことが、ここもとの米国市場における混乱の収束や、株価反転の原動力となったように思われます。
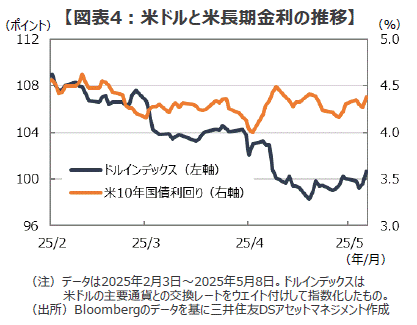
3.「ベッセントプット」で再起動する米国株
■米国株式市場の動きを長期的に見ると、多少のブレをともないながらも、概ね企業業績に連動して推移していることが確認できます(図表5)。このため、ベッセント財務長官の助言によりトランプ政権が、①米国のインフレ高進やサプライチェーンの混乱につながりかねない関税措置を柔軟に軌道修正し、②同盟国とのディールを通じて対中包囲網を構築し、③大きな代償を払うことなく対中戦略を推進できるなら、米国経済は深刻な景気悪化を回避するとともに、米国株式市場も長期のブルマーケットに回帰する可能性が高まりそうです。
久々のピンチだった4月の米国市場
■こうした観点からあらためて今年4月の相場展開を振り返ると、米国市場を襲ったトリプル安は、新政権発足後のトランプ政権が迎えた最大のピンチであったと言えそうです。というのも、①米株安は逆資産効果によりGDPの約70%を占める個人消費を直撃し、②米長期金利の上昇(米国債の価格下落)は住宅投資や設備投資を下押しするとともに海外投資家の資本逃避を誘発し、さらに、③ドル安は輸入物価の上昇を通じてインフレ圧力を押し上げかねないからです。こうして見ると、米国経済は金融市場のトリプル安により、景気後退とインフレが同時進行する「スタグフレーション」に追い込まれかねない状況にありました。
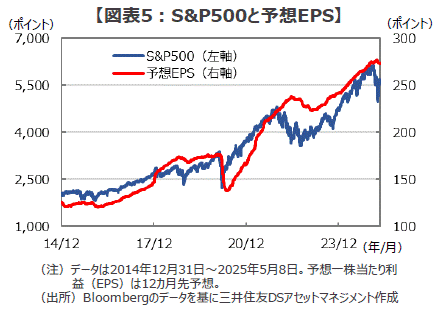
■こうした危機を回避するためにトランプ大統領に働きかけ、相互関税の一時凍結を決断させたのがベッセント財務長官だったとされています。そんなベッセント財務長官は、ヘッジファンド業界の大物として知られるジョージ・ソロスとともに、1992年の英ポンド危機では大量のポンド売りにより英国を欧州為替相場メカニズム(EMR)からの離脱及び、通貨切り下げに追い込み、約10億ドルを荒稼ぎしたとされています。
「毒をもって毒を制す」か?裏を知りつくした者の凄み
■話しは少し横道にそれますが、米国第35代大統領ジョン・F・ケネディの父、ジョセフ・P・ケネディは、インサイダー取引や株価操縦といった現代なら違法とされる証券取引で巨万の富を築いたとされています。そんなジョセフは晩年、株式市場を管理監督する米国証券取引委員会(SEC)の初代長官として辣腕を振るい、様々な不正取引の摘発を通じて、米国株式市場の近代化、適正化に大きく貢献したとされています。
■「毒をもって毒を制す」と言うと言い過ぎかもしれませんが、時には欧州の大国を窮地に追い込む「市場の怖さ」を知り尽くしたベッセント財務長官は、ユニークなトランプ大統領と神経質な金融市場の間を取り持つ適任者と言えそうです。マーケットのプロであるベッセント財務長官がホワイトハウス内での発言力を強め、トランプ大統領を誘導し、危機にあっては金融市場の不安を鎮める役割を担っていくなら、これを金融市場が好感するのはある意味当然のことと言ってよさそうです。そして、「ベッセントプット」がトランプ大統領がもたらす「不確実性」を中和するなら、米国株式市場は長期の上昇トレンドに回帰する可能性が高まりそうです。
まとめに
トランプ政権の経済政策がもたらす不確実性を懸念する報道が続く一方、株式市場では4月9日の相互関税の一部凍結をきっかけに相場が大きく戻しています。
金融市場が安定を取り戻しつつある背景には、トランプ大統領の意外な柔軟姿勢もさることながら、その背後に控えるベッセント財務長官の存在が大きいように思われます。自他ともに認める「市場のプロ」であるベッセント財務長官が、トランプ大統領を巧みに誘導して米国のトリプル安というピンチを切り抜けて見せたことで、市場では「ベッセントプット」への認識が広がりつつあります。
もし、「ベッセントプット」がトランプ大統領がもたらす「不確実性」を中和するなら、米国経済は深刻な景気悪化を回避するとともに、米国株式市場は長期の上昇相場に回帰する可能性が高まりそうです。
関連マーケットレポート
- マーケットの死角



