2025年4月28日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
「FRBの独立性毀損で米トリプル安」は本当か
FRB議長解任騒動の「危機の本質」
トランプ大統領が米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の解任に言及しながら利下げを迫ったことが嫌気され、4月21日連休明けのニューヨーク市場では米国株、米国債、米ドルが揃って下げる「トリプル安」となりました。翌22日にはトランプ大統領があっさり前言を撤回して市場は落ち着きを取り戻しましたが、「もし、FRB議長の解任が強行されていたら米国の信用はガタ落ちになっていた」とする解説が多いようです。しかし、改めて今回の騒動を振り返ると、わたしたちが警戒すべき本当の「危機」は、こうした指摘とは少しばかりズレたところにあるように思えてなりません。
1.軍神の名言とワイマール陸軍の組織論
■卓越した戦略と輝かしい戦績から「軍神」と呼ばれたフランスの皇帝ナポレオンは、「真に恐れるべきは有能な敵ではなく、無能な味方である」との名言を残しました。また、第一次世界大戦後にドイツ・ワイマール共和国陸軍を再興し、軍内部における絶大な影響力から「黒幕(Graue Eminenz)」と呼ばれたハンス・フォン・ゼークト大将は、配下の人間を①やる気のない有能、②やる気のある有能、③やる気のない無能、④やる気のある無能、の4つに分類した上で、適材適所の人材配置を行うことの重要性を唱えました。
■例えば、要領が良く周囲を使うのが上手い①「やる気のない有能」は指揮官に、なんでも自分でやってしまう②「やる気のある有能」はその補佐の参謀に、そして、言われたことを淡々とこなすだけの③「やる気のない無能」は兵卒に、といった考え方です(図表1)。
■そんなゼークトが危険人物として最も警戒していたのが、④「やる気のある無能」に分類される人間です。恐ろしい話ですが、ゼークトはそうしたタイプの人間は、「最前線に送り込んで早々に排除してしまえ」と言っていたと伝えられています(諸説あり)。というのも、こうしたタイプは、やる気はあるものの能力が伴わないため、見当違いの方向に暴走することが少なくありません。そして、周囲に迷惑をかけることで組織全体の効率を悪化させ、その士気までも低下させてしまいかねないからです。
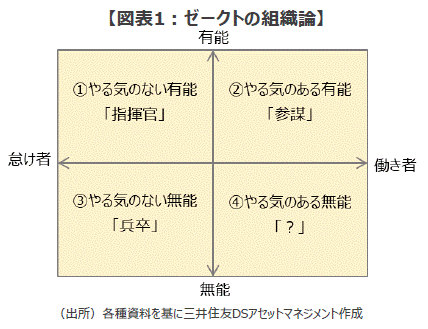
■もし「やる気のある無能」が戦場で大暴れしてしまうと、勝利がおぼつかなくなるばかりか戦略が機能しなくなることで、部隊全体の存亡すら危ぶまれる事態となりかねません。こうした考えは「ゼークトの組織論」として、現代でも企業の人材戦略に広く取り入れられているようです。そして、最近のトランプ大統領による「FRB議長解任騒動」を見る上でも、示唆に富んでいるように思われます。
2.パウエルFRB議長のトラックレコード
■トランプ大統領による攻撃の被害者として「時の人」となった観のあるFRBのパウエル議長は、2012年にFRBの理事に就任し、2017年からは同議長を務めます。FRBのトップとして8年目を迎えベテランの域に達しつつあるパウエル議長ですが、その経歴は金融政策を差配する中央銀行の総裁としてはかなり異色なものと言えそうです。というのも、そもそもパウエル議長はジョージタウン大学ロースクール出身の弁護士で、経済学や金融政策の専門家が多い歴代のFRB議長とはかなり毛色が違うからです。
■歴代のFRB議長を振り返ると、卓越した金融市場との対話力から「マエストロ」と呼ばれたグリーンスパン元議長は、経済学の博士号を取得した後にプロ相手の経済アナリストとして活躍していました。また、パウエル議長の前任のイエレン前議長は、イエール大学で経済学の博士号を取得した後に名だたる有名大学で経済学者として教鞭をとっていました。また、バーナンキ元議長にいたっては、2022年に経済学者としてノーベル経済学賞を受賞しています。
間違いを繰り返す異色の総裁
■そんなパウエル議長の異色の経歴も、中央銀行総裁としての輝かしい実績があれば「個性」として好意的に見る人もいるかもしれません。しかし、残念なことに、これまでのパウエル議長の決断は、芳しい結果を残したとは言い難いようです。例えば、パウエル議長は2018年後半に消費者物価指数(CPI)がFRBの目標値である2%に向けて下げ足を速める中、トランプ大統領などの反対にもかかわらず連続利上げを実施しました。しかし、その見立てに反して世界景気の減速が鮮明になり、更にインフレも目に見えて低下していくと、2019年夏には一転して利下げに追い込まれました。
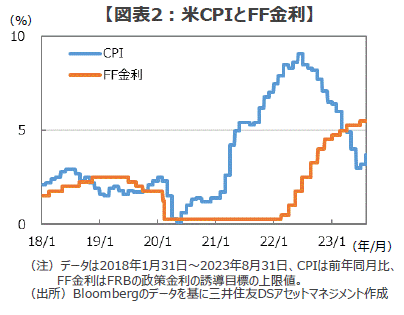
■また、2021年に始まるコロナ禍後の急激なインフレ局面では「物価上昇は一時的」と判断を誤り、その後、インフレが猛威を振るう中で通常の3倍速(会合毎に0.75%)となる大幅利上げに追い込まれました(図表2)。また、2024年9月には市場の予想を上回る0.5%の大幅利下げに踏み切りましたが、この時も景気や物価の基調判断を誤り、利下げ直後から米長期金利は大きく上昇することとなりました(図表3)。
■こうしてパウエル議長のトラックレコードを確認していくと、その表現の下品さには閉口するものの、トランプ大統領が「Mr. too late(のろま)」「Major loser(負け犬)」と厳しく批判するのも無理からぬものに思えてきます。
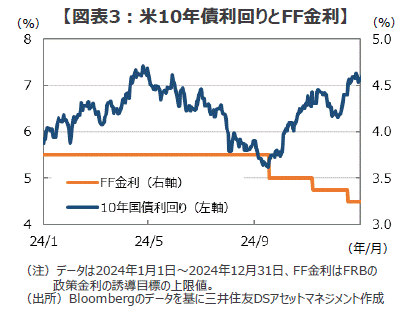
3.米国最大のピンチは議長が変な本気を出した時
■トランプ大統領に「無能」の烙印を押された格好のパウエル議長ですが、「やる気」の方は十分なようです。そして、トランプ大統領ばかりか金融市場からの「利下げ要請」にも応えることなく、「FRBの独立性」という金看板の維持に邁進しているように見受けられます。というのも、今回の相互関税発動後の米国株急落、米長期金利急騰、そして米ドルの独歩安が同時に起こる異例の「トリプル安」(図表4、5)に市場が大きく動揺する最中に、パウエル議長は「不透明感が晴れるまで静観する(We are well positioned to wait for greater clarity)」とコメントして、ホワイトハウスや市場関係者を驚かせたからです。
敏腕弁護士の暴走?が生む本末転倒
■金融市場の異常事態にあって、本来ならFRBは市場の期待をコントロールし、行き過ぎた不安やボラティリティを鎮めるためのコミュニケーションに努め、危機に際しては流動性の供給により「最後の貸し手」として金融システムの守護神として振舞うことが期待されます。事実、金融市場ではパウエル議長の態度とは裏腹に、FRBによる利下げ期待が高まっていきました。しかし、パウエル議長の言動からは、そうした市場が発する悲鳴に応える発信は確認することができませんでした。
■なぜこんな事になってしまったのかと言えば、言葉を選ばずに言えば、FRB議長としての専門性や実績に疑問符がついてもおかしくないパウエル氏が、有能な弁護士としての本性をむき出し、自己弁護やFRBの組織防衛に「本気」を出してしまったからかもしれません。
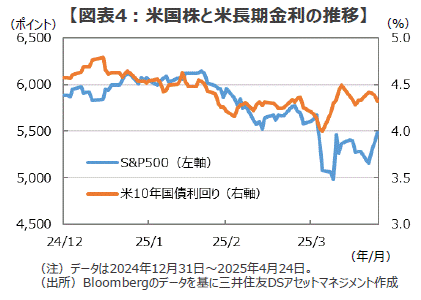
■FRB議長は大統領による指名と上院銀行委員会の承認により選任される、「政治任用」そのものともいえるポジションです。このため、過去のFRB議長はその職責を全うするのと同時に、政治との良好な関係を維持することに腐心してきました。もちろん、FRBの独立性の大切さは財政ファイナンスを始めとする過去の金融政策の苦い経験から私たちが学んだ叡智(えいち)ともいえます。しかし、市場の非常時に政府との連携や市場の安定よりもFRBの独立性を優先するとしたら、本末転倒と言わざるを得ないでしょう。
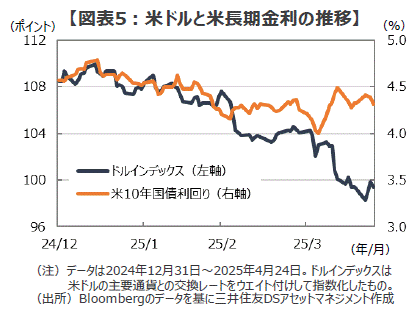
■市場の一部ではトランプ関税による景気減速と物価上昇圧力の高まりから「スタグフレーション懸念」がくすぶっています。そんな最中で起こった米国市場の「トリプル安」は、株価下落による個人消費への逆資産効果や、ドル安による輸入物価上昇がインフレ高進を招くことで、負のスパイラルに陥りかねない「緊急事態」ともいうべき状況でした。
■こうした危機感を背景にベッセント財務長官がトランプ大統領に進言をすることで、4月9日には「相互関税の一時凍結」が急遽決まったとされています。こうした対応は、金融市場を熟知するヘッジファンド出身のベッセント財務長官のバランス感覚が発揮された、「好プレー」と言えそうです。その一方で、市場の緊急事態に静観を決め込んでいたようにも見えるパウエル議長の「本気」が、先行きの不透明感に身構える市場を更に不安にさせたとしても不思議ではないでしょう。
■米国経済は2025年に入り減速傾向が顕著で、市場ではトランプ大統領が大々的に「利下げ要求」を始める以前から、FRBによる大幅な利下げを織り込む動きが鮮明となっていました(図表6)。もし、こうした状況下にあって、中央銀行総裁としての力量に疑問符のつくパウエル議長がトランプ大統領との対決に本気を出すことで、本来なら利下げが必要な状況でそのタイミングを逸するようなことが有れば、「オーバーキル」による米景気の失速と米国株の下落というリスクシナリオが現実化する可能性が高まります。こうした事態は、政治におもねりFRBの独立性という「金看板」がかすんでしまうことよりも、遥かに深刻な事態かもしれません。
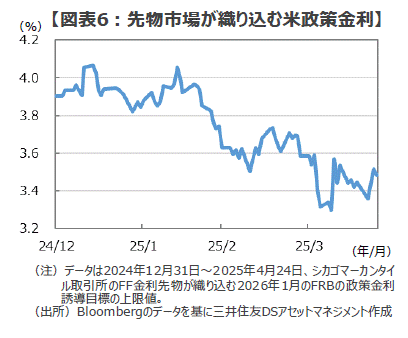
まとめに
2021年3月、トルコのエルドアン大統領が高インフレの最中に中央銀行の総裁を更迭して「利下げ」を強行した結果、通貨リラや同国株式市場は急落することとなりました。こうした事例を引き合いに、「中央銀行の独立性が大事」と説く解説を良く目にします。しかし、トルコの金融市場が混乱に陥ったそもそもの原因は、中央銀行の独立性が毀損されたためというよりは、インフレに利下げで対応するという「誤った金融政策」が強行されたからではないでしょうか。
第二次安倍政権下、積極的な金融緩和に難色を示していた白川日銀総裁は、任期途中で辞任に追い込まれました。しかし、政策のフリーハンドを確保した安倍首相は自ら任命した黒田総裁と二人三脚で強力な金融緩和を推し進め、その後の景気回復と日本株の上昇で世界の注目を集めることとなりました。
仮に、トランプ大統領がFRBの独立性を踏みにじり、FRB議長の解任を強行したとしても、トランプ政権の経済政策と整合的で適切な金融政策が実施される限り、米国の信認が著しく損なわれるリスクは限定的であるように思われます。むしろ恐れるべきは、FRBの独立性という「面子」が適切な金融政策よりも優先されることであり、異色のFRB議長が大暴れする事態こそ、金融市場にとっての最大のピンチに思えてなりません。
関連マーケットレポート
- マーケットの死角
- マーケットの死角



