2025年3月3日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
マッドマンセオリーが揺さぶる世界の金融市場
トランプ関税で大幅調整した日本株の今後
2月28日金曜日の東京株式市場は、ニューヨーク市場が大きく下げた流れを引き継ぎ大幅に調整し、約5カ月ぶりの安値水準で引けました。下落のきっかけはトランプ大統領による関税の発動で、日本株は外需関連を中心に終日売りに押される展開となりました。1月の就任以来、矢継ぎ早に自身の政策を進めるトランプ大統領に、変化を嫌う株式市場では不透明感と疑心暗鬼が渦巻いているようです。長らく横ばい推移が続いた日本株は今回の調整でレンジを下抜けした格好ですが、今回の株価下落の背景と今後の日本株の展望について整理したいと思います。
1. 日本株下落の背景
■先週2月28日金曜日の東京株式市場は、ニューヨーク市場がハイテク株を中心に大きく下げた流れを引き継ぎ、大幅な調整となりました。日経平均株価は心理的な節目とされていた38,000円の水準を明確に割り込んだことで損失覚悟の売りも加わり大幅安の展開となり、約5カ月ぶりの安値となる前日比1,100円67銭(▲2.88%)安の37,155円50銭で引けました。
■日本株が大きく下げた背景については、トランプ関税を含む主に3つの材料を挙げることができます。1点目が、冒頭でも触れたトランプ大統領による関税措置の表明です。トランプ大統領はカナダ、メキシコへの25%の関税と、中国への10%の追加関税(発動後は計20%)を3月4日から実施するとSNSで表明しました。市場ではこれまで、中国以外の関税措置がギリギリで回避されるとともに、一律関税より影響が限定的な相互関税が優先されると伝えられていたことから、今回の発表に意表を突かれた格好です。
■下落要因の2点目として、市場の動揺に拍車をかけているのが米景気の減速懸念です。ここもと、米経済をけん引してきた個人消費の減速を示唆する経済指標が続いていますが(図表1)、株式市場では景気減速による企業業績の悪化懸念がくすぶっていました。
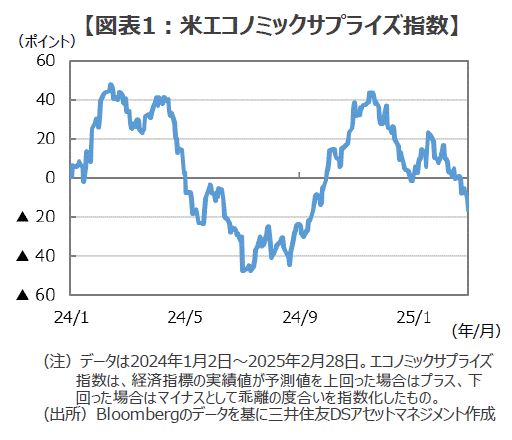
合わせ技一本で深くなる日本株の調整
■こうした米国株にまつわる不透明感に加えて、さらに日本株独自の下押し要因となっているのが、日銀による早期の利上げ観測の台頭と長期金利の上昇です。日本の消費者物価指数は2022年の春以降、日銀が目標とする年率2%を超える上昇が続いてきましたが、今年の春闘についても高水準での賃上げが実現する可能性が高まってきたことで、市場では日銀による早期の追加利上げ観測が高まっています。
■長らくデフレ下で大規模金融緩和が続いてきたこともあって、久しぶりの金融引き締めに身構える投資家の不安心理を、トランプ関税や米景気の減速懸念による米国株の調整が増幅した格好です。こうしてみると、今回の日本株の大幅な調整については、①トランプ関税に関わる不透明感、②米国経済の減速懸念、そして、③日本の金融引き締め観測、といった3つの要因が複合的に作用した「合わせ技一本」により、思いのほか深い調整となった可能性が高そうです。
2. 今後の日本株について
■トランプ大統領による関税発動の表明をきっかけに株式市場は大きな調整に見舞われましたが、広く他の金融市場に目を転じると、その反応は様々である事が確認できます。
■例えば、トランプトレードで買われてきた仮想通貨は大きく下落する一方、為替市場に目を転じると、関税の発動が発表されたカナダドル、メキシコペソは、リスクオフで反応した株式市場と異なり落ち着いた推移となっています(図表2)。ちなみに、2月1日にカナダとメキシコに対するトランプ関税が初めて発表された直後は、今回とは異なり、カナダドルやメキシコペソは大きめの下落に見舞われました。
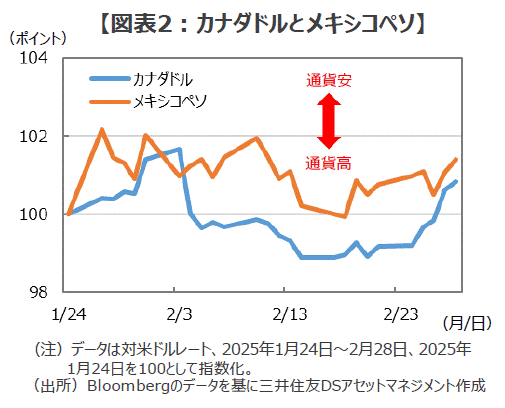
「マッドマンセオリー」との賢い付き合い方
■こうした為替市場の反応は、市場がカナダやメキシコへの関税措置について、その「仰々しい前振り」とは異なり仮に実行に移されたとしても、米国経済に深刻な影響を与えない範囲・期間で限定的に行われる可能性が高く、「交渉相手に譲歩を迫るためのアドバルーンにすぎない」と見透かしているからかもしれません。
■こうした交渉術は「マッドマンセオリー」と呼ばれます。米37代大統領リチャード・ニクソンの外交政策の要として有名で、あえて非常識な振る舞いをすることで相手方を動揺させて、交渉上の成果を得ようとする戦略です。トランプ大統領は選挙期間中からアメリカ・ファーストを掲げ、①経済活性化、②国内産業振興、③財政・貿易赤字の縮小、④国際秩序に挑戦する中国の抑え込み、といった米国の国益を追求する姿勢を鮮明にしてきました。そんなトランプ大統領が、米国のインフレ高進、景気減速、企業業績悪化につながるような「愚策」を実行する可能性は低いと考えるのは、むしろ合理的な判断と言えるでしょう。
■例えば、カナダに対する関税措置を見ると、米国のインフレに影響を与えかねないカナダ産原油の関税については、他の品目(25%)と異なり関税率は10%に抑えられています。現在の株式市場は、トランプ大統領の「マッドマンセオリー」を真に受けて、恫喝を受けた交渉相手と一緒に動揺してしまっているように見受けられます。しかし、国益重視のトランプ大統領が自国経済への深刻なダメージを回避しつつ、あくまでも「交渉カード」として関税措置を振りかざしているのであれば、米国経済や米国株、そして、日本株への実質的な影響は、極めて限定的なものにとどまるのではないでしょうか。そう考えると、トランプ大統領による「マッドマンセオリー」との賢い付き合い方は、市場の過剰反応をやり過ごすことにこそあるのではないでしょうか。
弱含む米経済指標をどう見るか
■ここもと、米国の個人消費の減速を示唆する経済統計が続いています。具体的には、小売売上高、全米供給管理協会(ISM)非製造業景況感指数、消費者信頼感指数などで、予想を下回る結果が続いたことで、米経済や企業の事業環境への警戒感が広がっています。こうした経済指標の変化や、予想との乖離に敏感に反応するのが市場の常ですが、米景気がこれからリセッションに向かって急減速すると断定するのも少々極端なように思われます。
■というのも、米国の個人消費を支える雇用環境は引き続き堅調で、2月に発表された1月分の雇用統計でも着実な雇用者増加が確認されるとともに、市場の予想に反して失業率は小幅に低下しています。また、賃金も市場の想定を超えて力強い上昇を見せ、消費者物価の伸びを上回って推移しているからです(図表3)。
■ちなみに、今年1月はロサンゼルスでの大規模な火災や東海岸での大雪などが、個人消費に影響を与えた可能性が指摘されています。もちろん、2022年3月から始まった大幅な金融引き締めの累積的な効果が表れた可能性は否定できません。しかし、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が明言するように、「米経済は利下げを急ぐような状況にはない」のであるとすれば、短期的なデータの振れに過剰に反応するのは避けたいところです。
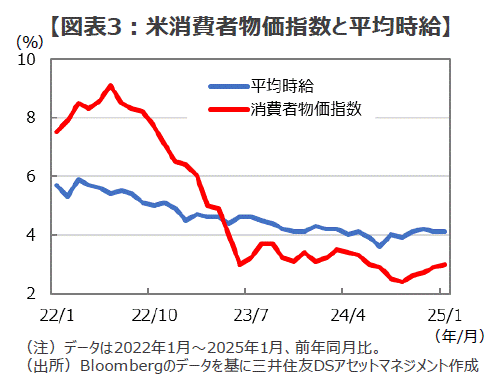
あくまでも「条件付き」の日銀利上げ
■日銀の金融政策については、植田総裁をはじめとする一連の高官発言が示唆するように、賃上げ動向や景気を確認しながら金融政策の正常化(利上げ)が進められていくものと思われます。弊社では、今年7月に0.25%、来年1月にも0.25%の利上げが実施されるものと想定していますが、その前提として、日本の景気回復の腰を折らず、物価上昇と賃上げの好循環が順調に進む限り、といった条件がつくこととなります。
■最近の長期金利の上昇を受けて、植田総裁は衆院予算委員会で、「長期金利が急激に上昇するなら機動的に国債買い入れを増額する」と発言して、市場の行き過ぎをけん制しました。こうした発言を受けて直近の債券市場では、これまで一本調子で上昇してきた10年国債利回りはいったん落ち着きを見せています。
■かつて、日銀審議委員として2000年に実施された拙速なゼロ金利解除に反対し、その後の金融政策の芳しくない成果を目の当たりにしてきた植田総裁が、同じような過ちを繰り返す可能性はそれほど高くないように思われます。そう考えると、日銀の拙速な利上げによるオーバーキル(金融引き締めによる景気失速)への懸念は、杞憂に終わる可能性が高いのではないでしょうか。
3. 株式という「頼もしくも、ままならない存在」
■今回のような株式市場の調整が起きると、投資家としては心穏やかに過ごすことは、正直言って難しいと言わざるを得ないでしょう。とはいえ、あらためて株式の性質を考えると、こうした市場の調整は定期的に訪れる「年中行事」であることは、覚悟しておく必要がありそうです。
■具体的な数字で確認してみましょう。2000年1月以降の276カ月における東証株価指数(TOPIX)の12カ月リターンを計算すると、平均リ
ターンは+6.5%(中央値+5.8%)、リターンのばらつきを示す標準偏差は21.8%でした。
生半可ではできない株式投資
■株式のリターンが正規分布(平均値を中心とした一般的な分布)すると仮定すると、株式の12カ月リターンは約68%の確率で▲15.3%~+28.4%の範囲に収まる一方、約16%(100%-68%の半分)の確率で▲15.3%を上回る大幅な下落が発生し、残り約16%は+28.4%超の大幅上昇を見せることとなります。
■あらためてこうした数字を眺めると、日本株投資はたかだか年率約6.5%のリターンを得るために、通常(約68%の生起確率)でも平均を中心に年率で±20%を超えるリターンの振れに耐えねばならず、約6分の1の確率(約16%)でびっくりするような下落に見舞われることになります。
■今回のような株式市場の大幅な調整を「事故だ」という人がいます。しかし、警察庁の発表によれば、令和6年の交通事故件数は10万人当たり233.9件(約0.23%)、死亡事故にいたっては同2.09件(約0.002%)にすぎません。つまり株式投資は、交通事故と比べても「けた違いの確率で痛い目に合う」ようです。
■「こんな危なっかしいモノ、関わりたくない」との感想を持たれる方も少なくないでしょう。しかし、預貯金や国債といった低リスク
(リターンのブレの小さい)資産への投資から得られる平均的なリターンは株式と比べて小さいため、長期の資産形成を考える場合、株式投資なしに十分な投資成果を得ることは数学的に不可能といえそうです。特に、昨今のようにインフレ率が上昇して金利水準を大きく上回るようになると、株式のようなリスク資産への投資は、私たちの資産の購買力を守る上での重要性はさらに高まる事になります。
株式市場にとどまり続けることの意味
■株式投資を続ける限り、大きなリターンのブレに見舞われることは分かるけれど、それなら「今回の調整のように相場が荒れる局面ではいったん手放して、落ち着くのをしばらく待った方がよいのではないか」と仰る方も少なくないでしょう。
■もちろんそうした相場の「乗り降り」がうまくできればそれに越したことはないのですが、実行することは極めて難易度が高そうです。というのも、先の数字で見た通り、株式市場は急に大きく調整して我々を驚かせるだけでなく、時に思いがけず大きく上昇して、私たちを良い意味でドキドキさせることも少なくないからです。
■最も大切なことは、心躍らせるような上昇のタイミングは予測困難であると同時に、それを逃してしまうと株式投資の成果に致命的なダメージを与えてしまう可能性が高いことです。具体的な数字で見てみましょう。過去10年間にTOPIXは約2.2倍(約+121%)に上昇していますが、そこから月次リターンが最も良かった10カ月を除いてしまうと、TOPIXの累積リターンは約+7%へと劇的に悪化してしまうことが確認できます(図表4)。
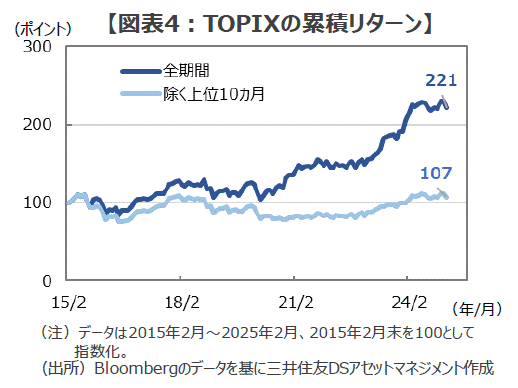
「いけず」な日本株
■株式投資はいわゆる元本保証の投資とは対局にあり、①普段は平凡な上下動を繰り返し、②定期的に大きい調整が起こり、③予想外のタイミングで訪れる大きめの上昇が長期的に高いリターンを支えている、ということになります。なんとも「いけずな投資対象」といったところでしょうか。
■そう考えると、株式投資で長期的な成果を得るためには、今回のような調整は甘んじて受け入れつつ、同じく予想外のタイミングで訪れる上昇を待ちながら市場にとどまり続けることが、何よりも重要と言えそうです。
まとめに
今回の日本株の調整の背景には、①トランプ関税への警戒感、②米経済の減速懸念、そして、③日銀による追加利上げ観測、などがあります。そして、こうした悪材料が同時に重なることで、下げ幅が増幅された側面がありそうです。また、トランプ関税への金融市場の反応は様々で、為替市場のように、あまり材料視されていない市場もあるようです。その背景には、国益を最優先するトランプ大統領のマッドマンセオリーが、一部の市場参加者に見透かされているからかもしれません。
長期の資産形成に欠かせないとされる株式投資ですが、大きめの調整や予想外の上昇が相応の頻度で生じる性質を考えると、有利な資産形成を進めるには辛い時も株式市場にとどまり続けることが何よりも重要と言えそうです。
関連マーケットレポート
- マーケットの死角
- マーケットの死角



