2025年2月26日
三井住友DSアセットマネジメント
チーフグローバルストラテジスト 白木 久史
【マーケットの死角】
日本株のブルマーケットは終わったのか
2025年に入ってからの世界の株式市場は、欧州株や中国のハイテク株が好調となる一方、マグニフィセント7に代表される米ハイテク株が出遅れるなど、昨年とは様変わりの相場展開となっています。そんな、逆張りが優勢な今年の市場で出遅れが目立つのが日本株です。日経平均株価は昨年2月に約34年ぶりに新値を更新して更なる上昇が期待されましたが、昨年の夏場以降は3万8千~4万円台のレンジ内での値動きが続いています。一部の投資家からは弱気の声も漏れ聞こえてきますが、日本株のブルマーケットは終わってしまったのでしょうか。
1. 業績見通しに素直に反応する日本株
■好調を続けてきた日本株が変調をきたしたのは、2024年の夏に米国経済への先行き不透明感が高まったことがきっかけとされています。いわゆる「令和のブラックマンデー」と呼ばれた市場の混乱は、急激な円高もあって思いのほか深い調整となりました。そして、この調整以降、日本株はレンジ内での値動きに終始しています。
■一部で過熱感が指摘されていた日本株ですが、ここ数年は業績見通しに連動したオーソドックスな値動きを続けてきました。例えば、業績予想が伸び悩んだ2022年度の株価はもみあいに終始し、業績拡大が続いた2023年度は大きく株高に、そして、2024年度は好調な業績見通しを素直に反映して夏場まで好調に推移したところで先の「令和のブラックマンデー」を経験し、追い打ちをかけるように増益期待が頭打ちとなる中で相場は勢いを失うこととなりました(図表1)。
■ここもと足踏みが続いた日本株の予想一株当たり利益(EPS)ですが、足元では反転の兆しが見られます。というのも、金利上昇が追い風となる銀行業やインバウンドが好調な小売・サービス業といった内需の非製造業が好調なことに加えて、自動車など製造業についても、ようやく底入れの兆しがみられるからです。
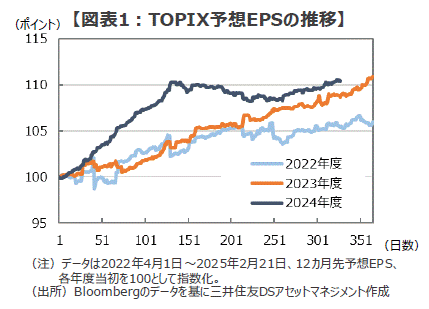
■自動車業界については、厳しさを増す中国の事業環境や一部完成車メーカーの業績不振にばかり目が行きがちです。しかし、よく目を凝らしてみると、世界的な電気自動車の不振をしり目に、ハイブリッド車の販売が好調なトヨタ自動車が今期の業績予想を上方修正するなど、業界全体としては底打ち傾向がみられるようになってきました。
■足元ではトランプ関税への不透明感もあって、投資家の日本株への視線は決して暖かいものばかりではないように思われます。とはいえ、
ディール重視のトランプ政権は中国以外の国・地域への関税について、大方の予想を超える柔軟な姿勢を見せており、今後は徐々に政策リスクへの過度な警戒感が緩んでいくことで、日本株は業績見通しの改善を織り込み下値を切り上げる展開となってもおかしくないでしょう。
2. 20年ぶりに現れた株式市場の難敵
■過去20年あまり姿を見せなかった難敵が、日本の株式市場に立ちはだかっています。それは、日銀による利上げと市場金利の上昇です。一般に金利上昇は景気を冷やすだけでなく、投資家が株式に期待するリターンを引き上げることで株価収益率(PER)を押し下げるため、株価全般にネガティブな影響を与えるとされています。
■株価を説明する投資理論に「配当割引モデル」がありますが、簡単に言うと、「株価は将来の配当を今の価値に割引いたものの合計になる」とする考え方です。この配当割引モデルの「配当」を「利益」に、「割引率」を「株主資本コスト」に読み替えると、代表的なバリュエー
ション指標であるPERは以下の式で表現することができます。
PER=1 ÷(株主資本コスト-利益成長率)
■この「株主資本コスト」は「投資家の期待リターン」と「無リスク金利」の合計になりますので、日銀が利上げをして短期金利が上昇すると、「株主資本コスト」もつれて上昇することになります。つまり、日銀が利上げをして金利が上がると、分母が大きくなってPERは縮小するので、理論的には利益が一定なら株価は下落する、というロジックです。
■長らくデフレとゼロ金利が続いてきた日本人にとってはピンと来ないかもしれませんが、日本と違い「金利のある世界」で動いてきた海外の株式、中でも米国株の動きを見ると、金利の動向が株価に大きな影響を与えてきたことが確認できます。具体的には、株価と金利の間には反対方向に動く「逆相関」が良く見られ、2022年や2023年の後半に米国の長期金利が上昇した局面では、流石の米国株も調整を余儀なくされました。
■ここもと、東証株価指数(TOPIX)の予想PERは概ね14~15倍の水準で推移していますが、数字を仮置きして「配当割引モデル」に当てはめてみたいと思います。株主の期待リターンを10%、短期金利0%、利益成長率を3%とすると、配当割引モデルから導かれる理論上のPERは約14.29倍となり、日本市場の実勢値とおおむね同水準となります。そして、短期金利(無リスク金利)が0%から1.5%へ上昇すると、PERの理論値は約11.76倍に低下します。
(短期金利0.0%のケース) PER=1÷(10%+0%-3%)=1÷7%=約14.29倍
(短期金利1.5%のケーズ) PER=1÷(10%+1.5%-3%)=1÷8.5%=約11.76倍
■仮に、利益水準が一定なら、PERが14.29倍から11.76倍に低下すると、株価は約17.7%下落する計算となります。昨年の夏以降、日本株が冴えない背景には、こうした金利上昇によるバリュエーションの低下懸念があるのではないでしょうか。
■特に、金利上昇の恐ろしさが骨身にしみている海外投資家は、日銀が本格的な利上げを開始した2024年7月末以降、大きく売り越しに転じており、日本の金利上昇に対する海外投資家の警戒感を伺わせる結果となっています(図表2)。
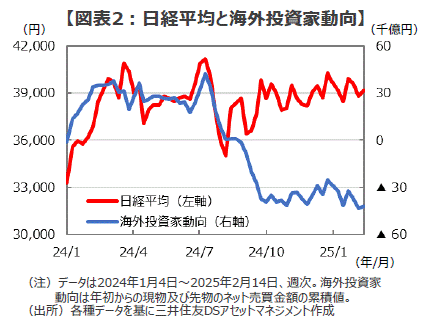
3. デフレ脱却の株価への影響
■金利上昇を背景とした日本株への悲観論には相応の根拠がありそうですが、1点大切な点を見逃している可能性があります。それは、日銀が強気で利上げを続ける背景に、日本のデフレ脱却と名目GDPの拡大が主因にあるからです。
■2011年3月末以降の名目GDPとTOPIXのEPSの推移を統計的に分析すると、この2つの数字の間には極めて高い相関関係がある事が確認できます(図表3)。つまり、名目GDPが順調に拡大すると、EPSも連れて増加する傾向が観察できます。
■日本の名目GDPはデフレが続いた2008年3月から物価の上昇傾向が顕著となり始める2022年3月まで、ほぼ横ばい(年率+0.2%拡大)の推移が続くとともに、この間のTOPIXのEPSの増加率は年率約+3.6%でした。一方、世界的にインフレが進んだ2022年4月以降、日本でも年率2%を超える消費者物価指数の上昇が定着すると名目GDPとEPSは騰勢を強め、その後は名目GDPは年率約+4.0%、EPSは年率+11.5%の増加
ペースを続けています(図表4)。
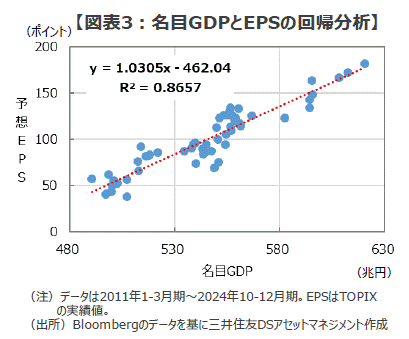
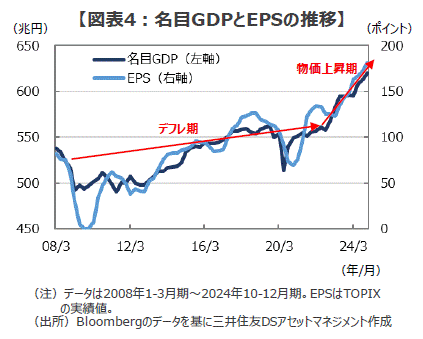
■ここで、先程の「配当割引モデル」のPERの計算式を思い出していただきたいのですが、利益成長率が上昇するとPERの計算式の分母(株主資本コスト-利益成長率)は小さくなり、PERの理論値は拡大(株価は上昇)することになります。
■弊社では、底堅い実質GDPの成長と2%前後の物価上昇が当面続くことで、日本の名目GDPは2025年度+3.4%、2026年度は+2.6%の成長を見込んでいます。仮に、2.5%の名目GDPの成長が続くと仮定すると、上記の統計的な分析結果から示唆されるTOPIXのEPS成長率は、年率
+6.3%となります。そこで、EPSが年率5%及び、6%で成長する場合の日本株のPERを配当割引モデルで試算すると、以下のようになります。
(5%増益のケース)PER=1÷(期待リターン10%+金利上昇1.5%ーEPS成長5%)=PER約15.38倍
(6%増益のケース)PER=1÷(期待リターン10%+金利上昇1.5%ーEPS成長6%)=PER約18.18倍
■ちなみに、足元のTOPIX12カ月先予想EPSは188.70、NT倍率14.17倍ですから、増益率+5%を仮定した場合の日経平均の理論値は
41,124円、同+6%なら48,611円となり、それぞれ上昇余地は約6.1%と約25.4%となります(2025年2月21日時点)。
(5%増益のケース)日経平均の理論株価=EPS188.70×PER15.38倍×NT倍率14.17倍=41,124円
(6%増益のケース)日経平均の理論株価=EPS188.70×PER18.18倍×NT倍率14.17倍=48,611円
■日銀が追加利上げを続ける背景に日本のデフレ脱却がある以上、その負の側面のみにフォーカスを当てることは、こうした投資機会を見逃すことになりかねません。仮に、利上げを続ける日銀の見立てが正しく、日本経済のデフレ脱却が確かなものとなるなら、業績予想に素直に反応を続ける日本株のアップサイドはなかなか侮れないものが有りそうです。そう考えると、「日本株のブルマーケットは終わってしまった」と嘆くのは、少々せっかちに思えてなりません。
まとめに
日本株が出遅れています。その背景には、昨年夏以降の予想EPSの伸び悩みに加え、日銀による利上げへの警戒感があるようです。特に、金利と株価の関係が身に染みている海外投資家としては、日銀の約20年ぶりの利上げを警戒するのは、ある意味当然のことと言えそうです。
ただし、利上げの負の側面だけに敏感になるのも、投資家としてはバランスを欠いているように思われます。というのも、日銀が利上げに転じる背景には、デフレ脱却への確信度の高まりがあるからです。もし、デフレ脱却が定着して日本の名目GDPが順調な拡大を続けるようなら、金利上昇の影響を差し引いても株価には相応の上昇余地が生じる可能性が高そうです。そう考えると、日本株のブルマーケットが終わったと諦めてしまうのは、少々気が早すぎるように思えます。
※個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。
関連マーケットレポート
- マーケットの死角
- マーケットの死角



