先月のマーケットの振り返り(2014年10月)【マンスリー】
2014年11月4日
1.概観
| トピックス |
日銀の予想外の量的・質的金融緩和拡充の公表から円はドルに対して下落、株価は上昇しました。 米国の株式は上昇したものの、米国の利上げ時期などを巡って、変動が比較的大きくなりました。 |
|---|---|
| 株式 |
米国株は、世界経済の減速懸念の高まりなどから下落する局面もありましたが、後半に上昇しました。 日本株は、量的・質的金融緩和の拡充の公表により、月末に急上昇しました。 |
| 債券 | 世界経済の減速などから投資家のリスク回避傾向が強まり、米欧日の国債利回りは低下しました。 |
| 為替 | 日銀の予想外の量的・金融緩和拡充の公表などから、円はドルやユーロに対して大きく下落しました。 |
| 商品 | 原油価格は世界経済の減速懸念から供給過剰懸念が強まり、大きく下落しました。 |
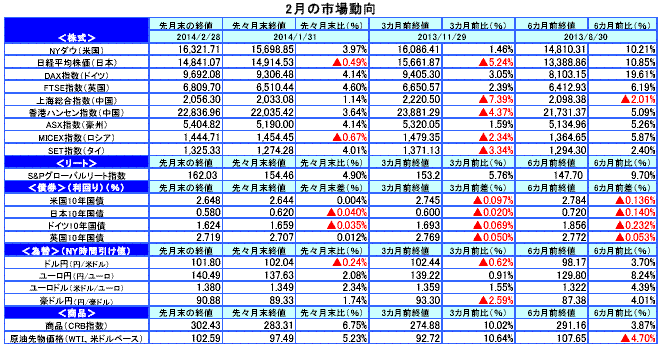
(出所)Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
2.トピックス
(1)日銀は量的・質的金融緩和を拡充、円はドルに対して下落、株価は上昇。
<現状>
10月31日、日銀は予想外の量的・質的金融緩和拡充を公表し、ドル円レートは2007年12月以来の112円台に突入し、約6年10カ月ぶりのドル高円安水準をつけました。日本株は公的年金の日本株運用比率の引き上げ決定もあり、日経平均株価の終値は31日の1日で755円高となり、約7年ぶりの水準となりました。
<見通し>
31日に公表された日銀の展望レポートでは、2015年度の物価見通し(消費増税の影響を除く)が+1.7%に引き下げられ、+2%の物価上昇目標を達成するというシナリオを維持するために日銀は追加緩和を決断したとみられます。政府と日銀が連携をとりながら、デフレ脱却の目標を掲げるアベノミクスの第二幕が始まった、との見方もあり、今後は政府による、補正予算の拡充などの追加景気対策に期待がかかる展開が見込まれます。
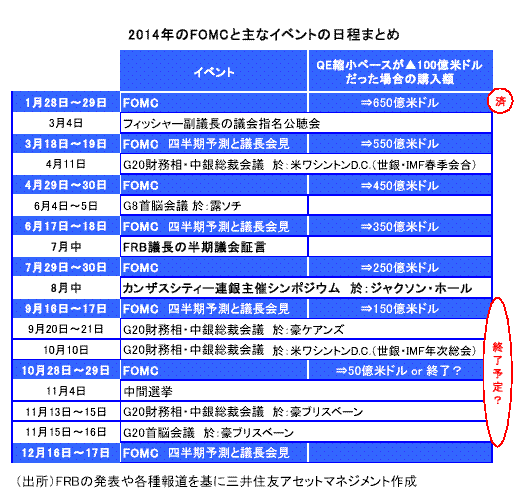
(2)米国の量的緩和が終了、利上げ開始時期を巡り株式の変動が大きくなる展開。
<現状>
10月の米国株式(NYダウ)は、月前半は世界経済の減速懸念や地政学リスクの高まり、金利引き上げ時期の前倒し観測などによる投資家のリスク回避的な動きが強まり下落しました。しかし、月後半では、堅調な企業決算、米国経済指標の改善、早期利上げ観測の後退などから上昇し、月末は前月比小幅に上昇する、変動の比較的大きな動きとなりました。
<見通し>
10月のFOMCでQEは終了し、今後米国の利上げ時期を巡る思惑から変動の比較的大きい展開が予想されます。米国の雇用環境の改善ペースが市場の見るポイントとみられます。FOMCの声明文では、「相当な期間の低金利の維持」との文言が残されました。今後、米国の雇用環境の改善ペースによっては、上記の文言の修正に注意が必要と思われます。

3.景気動向
<現状>
米国は、良好な雇用環境や住宅市場の持ち直しなどから、景気の改善が続いています。
欧州は、ドイツなどの企業景況感の悪化や物価上昇率の低下から、デフレ懸念が強まっています。
日本は、消費税増税後の経済指標の下振れからの改善が遅れ、景気回復が一旦足踏みしています。
中国は、1-9月のGDPは前年比+7.4%の成長とほぼ目標に沿った展開でしたが、消費や投資といった内需が減速しています。
豪州は、低金利から雇用情勢や住宅市場などの内需が堅調で、物価も落ち着いており、底堅く推移しています。
<見通し>
米国は、雇用情勢の堅調さに加え、住宅価格・株価の上昇傾向を受けた個人消費などが景気を支える見込みです。
欧州は、主要国ドイツにおける景況感が弱含んでおり、ECBによる追加緩和策が期待されます。
日本は、日銀が追加金融緩和を決定したこともあり、景気は再び持ち直すことが期待されます。
中国は、輸出増が景気の下支え材料です。また、来年度の成長率目標は+7%前後が見込まれ、安定した成長が期待されます。
豪州は、年+3%前後のGDP成長率が見込まれます。豪ドルは金利差への注目などから、底堅い推移を続けそうです。
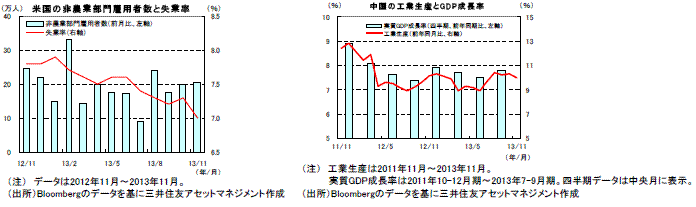
4.企業業績と株式
<現状>
主要米国企業の7-9月期の増益率は、前年同期比+8.3%(10月29日時点速報、トムソン・ロイター集計に基づく)となり、4-6月期の同+8.6%並みの水準となりました。日本の主要企業(東証1部、3月期決算、除く金融、10月29日時点速報)の2014年7-9月期決算は、経常利益が前年同期比2割程度の増益となっています。
<見通し>
主要米国企業の増益率予想は、今年10-12月期も7-9月期と同程度の利益を確保する見通しです。日本の主要企業の2014年度の経常利益は+12.9%と9月末時点から上方修正されています。増税後の景気の足踏みはあるものの、円安基調や米国景気の回復などを背景に、増益基調を維持しそうです。日米ともに堅調な企業業績を背景に、株価は底堅い推移が見込まれます。
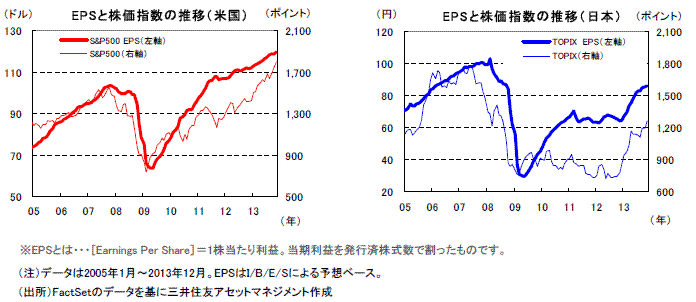
5.金融政策
<現状>
FRBは10月のFOMCで、量的緩和を終了し、今後の利上げについては、経済の改善度合いを慎重に検討し決める考えを示しました。ECBは9月のTLTRO実施に続き、10月には資産購入の拡大を開始し、金融緩和を拡大しました。日銀は、足元の景気や物価の動きを反映してデフレマインドの転換が遅延するリスクから、量的・質的金融緩和の拡充を決めました。
<見通し>
金利先物などから見ると、2015年半ばから後半の米国の利上げ開始が織り込まれています。ドイツ景気の弱含み、物価の低迷などから見て、ECBが資産購入の拡大などの追加策を実施する可能性が高まっています。日銀は今回、マネタリーベース、長期国債購入増額、ETFやREIT購入額の増加による量的・質的金融緩和の拡充を決めたことから、当面はこれらの政策効果の浸透を見極める姿勢とみられます。
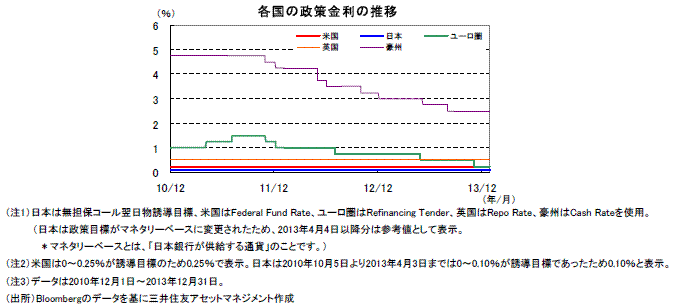
6.債券
<現状>
米国では、世界経済の減速懸念などから投資家のリスク回避傾向が強まり、10年国債利回りは低下しました。欧州では、ECBがTLTROに続き民間資産購入を開始して金融緩和を拡充し、国債の利回りは低下しました。日本では量的・質的緩和の拡充の公表から、国債の利回りは低下しました。米国の社債スプレッド(国債との利回り差)は、好調な企業決算などから、縮小しました。
<見通し>
米国では来年半ばの利上げを睨んで、米国国債などの利回りには上昇圧力がかかるとみられます。ただし、FRBは低金利を相当な期間維持するとみられ、利回りの上昇は緩やかになるとみられます。米国など主要国の社債市場では、企業の底堅い業績や慎重な財務運営などを背景に、利回りは低位で安定する見込みです。その結果、社債スプレッドは安定して推移すると思われます。
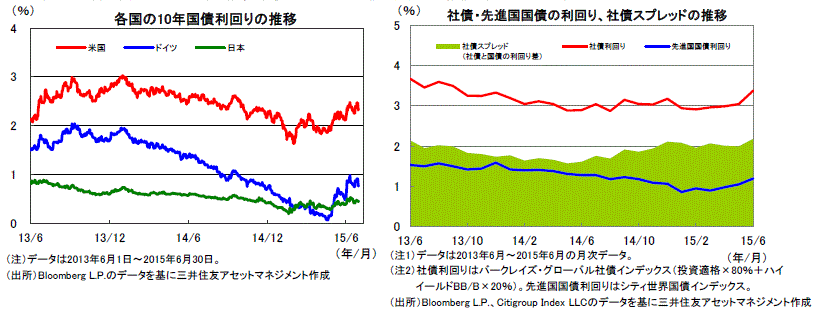
7.為替
<現状>
日銀の量的・質的金融緩和の決定が予想外であったことなどから、円に対して、ドルやユーロなどの主要通貨が大きく上昇しました。
<見通し>
ドル円相場は、日本の量的・質的金融緩和の進展に沿って、円が下落しやすい環境が継続する見込みです。日銀の追加緩和決定後の動きが急だったこともあり、一旦の足踏みなども見込まれますが、円の下落観測は根強く続きそうです。ユーロ円相場は、ECBの追加緩和策への思惑も強まる可能性があり、ドルに対する下落に比べて相対的に小さな動きとなりそうです。
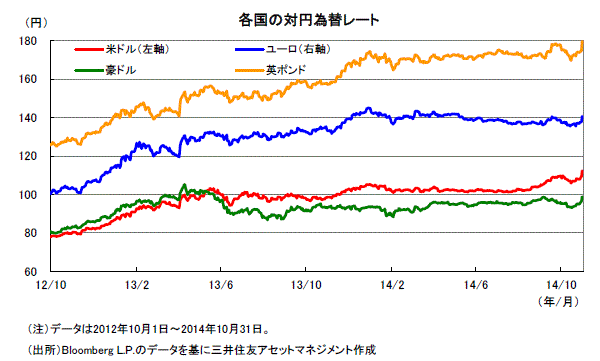
8.リート
<現状>
リート価格は上昇しました。米国などの主要国の国債利回りの低下や低金利環境が長期化するとの観測が高まり、リートに資金が流入しやすい環境が続きました。また、為替では円のドルに対する動きを反映し、円ベースでは値動きの変動が大きくなりました。
<見通し>
来年半ば以降の米国の利上げ観測が強まっていますが、FOMC後の声明文では「相当な期間の低金利の維持」との文言が残り、金利が急上昇するリスクは限定的とみられ、景気の安定化、資金調達コストの抑制という、双方の面でリートには好環境が期待されます。また、景気の緩やかな回復を背景に、不動産市場は今後も緩やかな改善を続けると見込まれ、リート市場は底堅く推移しそうです。
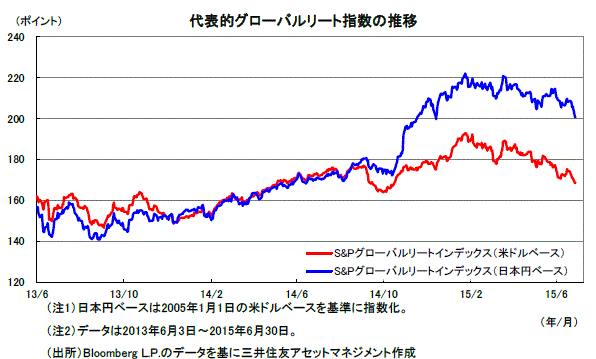
9.まとめ
| 株式 | 米国を中心に先進国景気は緩やかな回復が見込まれること、各国の企業業績が堅調に推移していること、低金利環境が続くと見られることなどに支えられ、先進国・新興国ともに、株価は緩やかな上昇基調が続くと思われます。 |
|---|---|
| 債券 | 米国の雇用回復や利上げ時期が早まる観測が高まるにつれ、米国の国債などの利回りに上昇圧力がかかると見込まれます。一方、FRBは長期間にわたり金利を低めに維持すると見られること、ECBが金融緩和を強化していることなどから、利回りの上昇は緩やかと思われます。 |
| 為替 |
米ドル円相場は、米国の利上げ観測、日銀の量的・質的金融緩和の拡充を背景に、円安・米ドル高圧力が残りそうです。 ユーロ円相場は、ECBが金融緩和策強化の方向性にあるとみられ、ドルに対してよりも小幅の値動きが見込まれます。 |
| リート | 国債利回りが急上昇するリスクは限定的で、リートの資金調達環境もしばらくは良好と見られます。また、世界景気の緩やかな回復を背景に、賃料など不動産市場は堅調に推移すると見られ、リート市場は底堅い推移が見込まれます。 |
|
|
※上記の見通しは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。 |



