【マンスリー No.69】先月のマーケットの振り返り(2014年5月)
2014年6月2日
1.概観
| トピックス |
ECB総裁が6月の追加緩和の可能性を示唆し、ユーロが下落、欧米の国債利回りは低下しました。 ウクライナの新大統領は親EU派ながら、対ロ関係の正常化を掲げており、市場の懸念は和らぎました。 |
|---|---|
| 株式 |
米1-3月期企業決算の上振れなどを背景に米株は最高値を更新したものの、高値警戒感も浮上しました。 日本株は、ドル安や追加緩和期待の後退で下落する局面があったものの、下値は底堅く、反発しました。 |
| 債券 | ECBの追加緩和期待、米国の賃金・物価上昇の緩慢さなどを背景に、欧米の国債利回りは低下しました。 |
| 為替 | 欧米の国債利回りの低下などを受け、ユーロやドルは対円で下落しました(円高)。 |
| 商品 | 原油価格は、米国での在庫増加に歯止めがかかるとの見方などから、上昇しました。 |
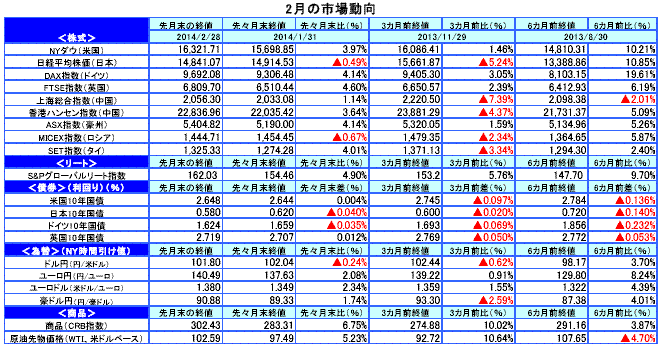
(出所)Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
2.トピックス
(1)ECBが追加緩和を示唆、欧米ともに国債利回りは低下
<現状>
ECB総裁が6月の追加緩和の可能性を示唆したことを受け、ユーロが下落し、欧州各国の国債が買われました。欧州では、従来から資金が国債市場へ流入していたこともあり、高債務国であるイタリアやスペインの利回りが2%台まで低下しました。その結果、米国債やドイツ国債との金利差は縮小しました。また、米国では、賃金・物価の上昇の緩慢さが低成長を招くとの懸念が浮上してきた(債券の買い要因)こともあり、米国債をはじめ先進国債券の利回りが全般的に低下する展開となりました。
<見通し>
米国のQEが今秋に終了し、利上げが視野に入る時期には、米国経済の回復も見込まれ、米金利やドルは緩やかな上昇基調に戻りそうです。この間、株価は低金利の恩恵と企業業績の回復を受け、底堅く推移しそうです。
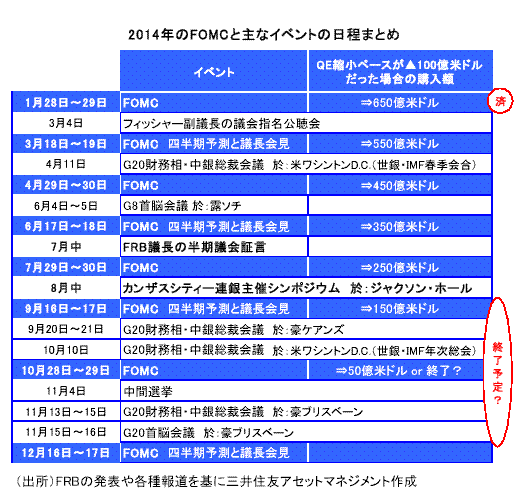
(2) ウクライナ懸念が後退するなか、米株は最高値、新興国に資金流入。
<現状>
ウクライナの新大統領は、親EU派ながらも対ロ関係の正常化を掲げており、欧米とロシアの対立が先鋭化する可能性が低下しました(ロシア株、通貨は急反発)。こうしたなか、1-3月期の米国の主要企業の決算が事前予想を大幅に上回ったことを背景に、米国の主要な株価指数は最高値を更新しました。また、4月以降は一旦停滞していた新興国向けの資金の流れも回復し、新興国の株価も上昇しました。
<見通し>
米国株の堅調さが持続するには、企業業績の回復シナリオの確度が高まる必要がありそうです。今年後半にかけては、米国や世界景気の回復がより明確となり、株価は緩やかな上昇基調が続くものと思われます。目先では、ユーロ圏や日本の追加緩和策の行方、中国の景気支援策の動向などを見極める展開が想定されます。
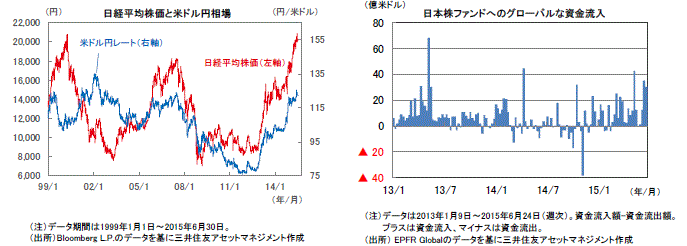
3.景気動向
<現状>
米国は、寒波による一時的な景気鈍化の影響が薄れ、雇用の増加を伴う景気回復が続いています。
欧州は、景気回復が緩やかに留まるなか、低インフレが今後の成長を抑えるリスクも意識されています。
日本は、消費税増税による各指標の振れを伴いながらも、基調としては景気回復が続いています。
中国は、景気の鈍化を受けて、政府が景気刺激策の実施方針を表明しており、景況感は底を打っています。
豪州は、住宅市場の活況さや貿易黒字への転換などを受け、景気は底堅く推移しています。
<見通し>
米国は、個人消費の堅調さに加え、今年は財政の崖などの特殊な下押し要因も薄れ、景気は堅調さを維持しそうです。
欧州は、低インフレから脱却するためにECBが追加緩和策を検討しており、緩和実施後の景気が注目されます。
日本は、消費税増税の影響は一時的に留まり、賃金上昇や輸出の増加、政府の経済対策により景気回復が続きそうです。
中国は、インフラ投資拡充を伴う景気刺激策が比較的早期に実行され、年+7%台での高めの成長が続きそうです。
豪州は、住宅市場が景気を支える一方、財政再建方針なども発表され、当面は年+3%を下回る成長ペースに落ち着きそうです。
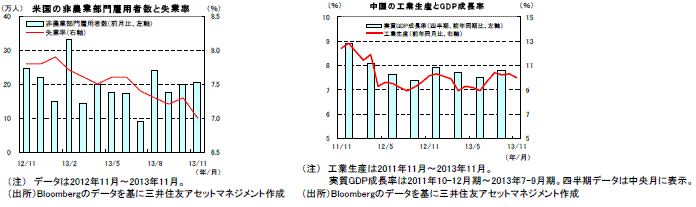
4.企業業績と株式
<現状>
5月22日時点で主要米国企業の2014年1-3月期決算は、前年同期比+5.7%(ブルームバーグ集計に基づく)となっています。10-12月期の同+9.9%から大きく鈍化しているものの、事前の市場予想からは、大きく上振れました。日本の主要企業(東証1部、3月本決算、除く金融)の2013年度決算は、経常利益が前年同期比で約+40%超と、大幅に増加する見込みです。
<見通し>
主要米国企業の増益率予想は、1-3月期に一旦鈍化した後は上昇傾向に転じ、今年後半には二桁増に回復する見通しです。日本の主要企業の2014年度の経常利益は、円高是正による大幅な押し上げ効果は一巡するものの、緩やかな円安基調や米国需要の回復などを背景になお底堅く増益基調を維持しそうです。企業業績が堅調ななか、日米ともに株価は底堅く推移するものと思われます。
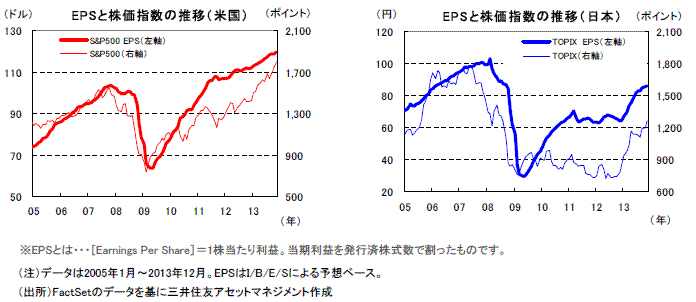
5.金融政策
<現状>
米連邦準備制度理事会(FRB)は、4月29日~30日の連邦公開市場委員会(FOMC)でQE縮小方針の継続を決定しました。欧州中央銀行(ECB)は5月の理事会において、6月に追加緩和を実施する可能性を示唆しました。日銀は、今年4月の展望レポートで成長見通しを引き下げた一方、物価の見通しを概ね据え置いたため、早期の追加緩和への期待はやや後退しました。
<見通し>
FRBは今後も100億ドルずつQEを縮小し、今秋にも終了させると見られます。金利先物から見ると市場は、2015年半ばから後半に利上げが開始されると織り込んでいます。ECBは景気と物価を下支えするため、政策金利の引き下げに加え、資産購入やマイナス金利などの緩和策を導入する可能性があります。日銀は年+2%の物価上昇という高い目標に向けて量的・質的金融緩和を続けており、緩和策を拡充する可能性もありそうです。
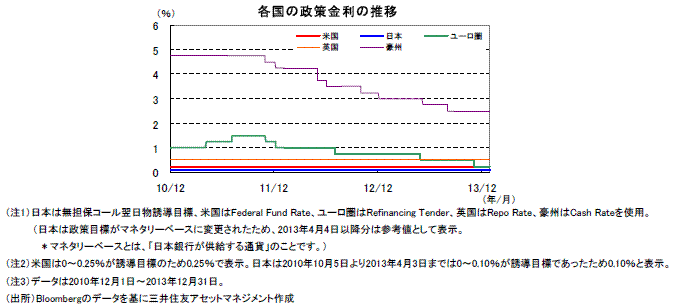
6.債券
<現状>
米国では、着実な景気回復の一方、賃金や物価の上昇ペースが遅いこともあり、国債利回りは低下しました。日本では、株価の不安定な動きを受けてリスク回避姿勢が強まるなか、国債利回りは低下しました。欧州では、ECBが追加緩和策の可能性を示唆し、国債利回りの低下が続きました。米国企業の社債スプレッド(国債との利回り差)は、利回りを求めた投資家の需要が社債の利回りを押し下げ、縮小しました。
<見通し>
米国の景気回復や将来の利上げ観測が強まるにつれ、米国債などの利回りは緩やかな上昇基調に転じそうです。ただし、FRBはゼロ金利政策を長期にわたり維持すると見られ、利回りの上昇は緩やかに留まると思われます。米国など主要国の社債市場は、底堅い企業業績や慎重な財務運営、旺盛な社債の需要などを背景に、利回りは低位で安定しそうです。その結果、社債スプレッドも安定的な推移を続けると思われます。
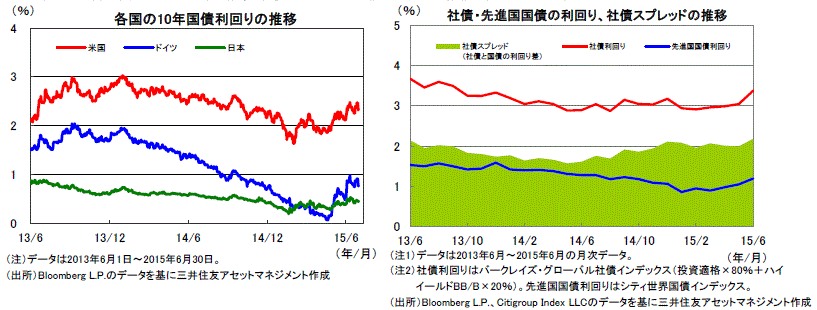
7.為替
<現状>
米欧の金利低下や、日銀の量的緩和拡充への期待が後退したことなどを背景に、円は主要通貨に対して上昇しました。
<見通し>
米ドル円相場は、日銀による大規模な金融緩和策や、米国のQE縮小などを背景に、円安・米ドル高観測が根強く残ると思われます。ユーロ円相場は、日銀の大規模な金融緩和策の一方、ECBも追加緩和の方向にあり、目先は一進一退となりそうです。先々ではユーロ圏の緩やかな景気回復期待などから、円安・ユーロ高に向かいそうです。
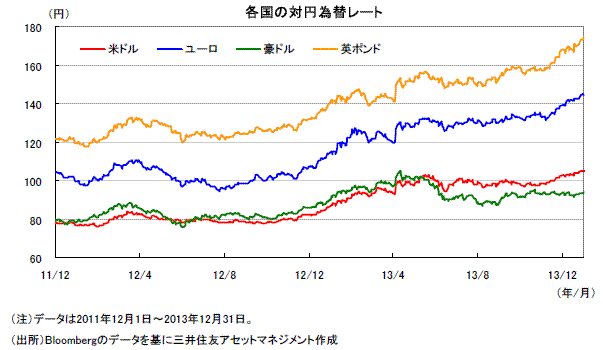
8.リート
<現状>
リート価格は上昇しました。不動産市場のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)はグローバルに改善傾向にあり、賃料なども上昇が見られます。また、主要先進国の低金利が続いていること、欧州の金融システムが安定化してきたことなど、世界的に資金調達環境が改善していることも好材料です。
<見通し>
FRBは出口戦略の検討を始める一方、金利上昇を抑制する姿勢を維持しています。金利が急上昇するリスクが限定的なことは、リートの好材料です。また、世界景気の緩やかな回復を背景に、不動産市場のファンダメンタルズは今後も緩やかな改善を続けると見込まれ、リート市場は底堅く推移しそうです。
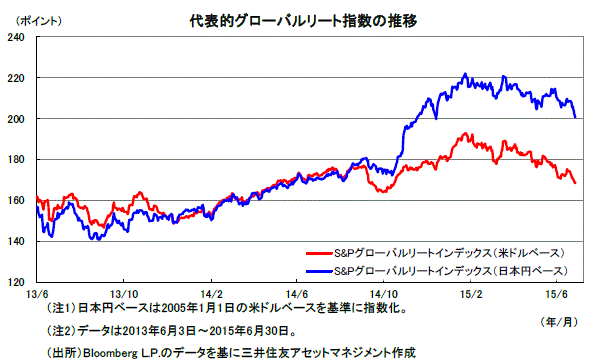
9.まとめ
| 株式 | 米国を中心に世界景気は緩やかに回復すると見込まれることや、各国の企業業績が堅調に推移していることなどにより、主要国の株式市場は底堅く推移すると思われます。 |
|---|---|
| 債券 | 米国の景気回復や将来の利上げ観測が強まるにつれ、米国債などの利回りには上昇圧力がかかると見込まれます。ただし、FRBはゼロ金利政策を長期にわたり維持すると見られることから、利回りの上昇は緩やかなものに留まると思われます。 |
| 為替 | 米ドル円相場は、日銀による大規模な金融緩和策の継続や、米国のQE縮小などを背景に、円安・米ドル高観測が引き続き根強く残ると思われます。ユーロ円相場は、日銀の大規模な金融緩和策の一方、ECBも追加緩和の方向にあり、目先は一進一退となりそうです。先々ではユーロ圏の緩やかな景気回復期待などから、円安・ユーロ高に向かいそうです。 |
| リート | 国債利回りが急上昇するリスクは限定的で、リートの資金調達環境もしばらくは良好と見られます。また、世界景気の緩やかな回復を背景に、賃料など不動産市場のファンダメンタルズは堅調に推移すると見られ、リート市場は底堅く推移すると見込まれます。 |
|
|
※上記の見通しは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。 |



