【デイリー No.1,875】最近の指標から見る米国経済(2014年5月)
2014年5月28日
<ポイント>
・4月の非農業部門雇用者数は前月比+28.8万人、失業率は6.3%と、ともに前月から改善しました。
・4月のISM景況感指数は、製造業、非製造業ともに新規受注指数が上昇し、今後の堅調さを示しました。
・1-3月の実質GDP成長率は、個人消費が下支えしたものの住宅投資などが下振れし、減速しました。
⇒米国経済は寒波の影響を脱して景気の復調が鮮明となっており、QEの縮小は今秋にも終了し、雇用の質改善や物価上昇が徐々に進めば、2015年後半以降の利上げが見込まれます。
1.雇用者数は大幅に増加、企業景況感も堅調
①雇用統計
4月の非農業部門雇用者数は前月比+28.8万人でした。また、3月は同+20.3万人へ、2月は同+22.2万人へ上方修正され、雇用者数の増加は3カ月連続で20万人超となりました。
雇用者数増加の内訳を見ると、民間部門が同+27.3万人、政府部門が同+1.5万人となりました。民間部門を業種別に見ると、建設業や製造業、小売業やビジネスサービス、教育・医療など幅広い分野で増加しました。
また、4月の失業率は6.3%と、前月の6.7%から大幅に低下しました。しかし、労働参加率が62.8%と前月の63.2%から低下しており、職探しを諦めた人が労働市場から退出したと考えられ、これが失業率低下の主因と思われます。このため失業率の大幅な低下が示すほど労働市場が改善しているとは言い難く、今後一時的な失業率の上昇も考えられます。
②ISM景況感指数
4月の製造業景況感指数は前月比+1.2ポイントの54.9ポイントと3カ月連続で上昇しました。また、4月の非製造業景況感指数は前月比+2.1ポイントの55.2ポイントと2カ月連続で上昇しました。それぞれの内訳をみると、製造業は足元の活動を示す生産指数や、生産活動の先行きを示す新規受注指数は前月からほぼ横ばいとなりました。一方、非製造業では、足元を示す企業活動指数は同+7.5ポイント、先行きを示す新規受注指数は同+4.8ポイントと、ともに大幅に上昇し、指数全体の上昇の主因となりました。
調査への回答では、製造業、非製造業ともに楽観的な見方が多い中で、製造業の一部で中国の景気減速やロシアへの輸出減少を懸念する声が見られます。
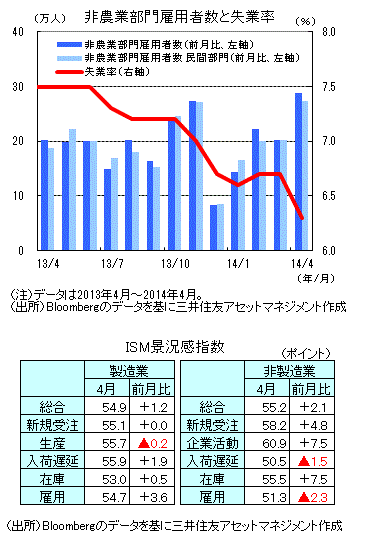
2.GDP成長率は減速、物価上昇率は低位が継続
①実質GDP成長率
2014年1-3月期の実質GDP成長率は前期比年率+0.1%と、2013年10-12月期の同+2.6%から大幅に減速しました。需要項目別にみると、住宅投資は同▲5.7%と前期の同▲7.9%に続き減少しました。また純輸出(輸出-輸入)は同▲0.8%と前期の+1.0%からマイナスに転じました。投資減税が2013年末で終了したことや、大規模な寒波の影響で燃料輸入が増加し貿易赤字が拡大したことが主因です。一方、個人消費は同+3.0%と前期の同+3.3%に続き堅調でした。なかでも光熱費など住宅関連費や医療費などへのサービス支出が同+4.4%と堅調でした。
②消費者物価
4月の消費者物価指数は前年同月比+2.0%と、3月の同+1.5%から2カ月連続で上昇しました。また変動の大きい食品・エネルギーを除いたコア指数は同+1.8%と、直近1年は同+1.6~1.8%での緩やかな上昇となっています。
居住費の緩やかな上昇が継続していることに加えて、当月は航空料金等一部のサービス価格などが押し上げ要因となりました。一方、FRBが目標とする個人消費支出物価指数は3月が同+1.1%と低水準であり、長期目標2%を下回っています。FRBは経済成長へのリスクとして、こうした緩慢な物価上昇を指摘しています。
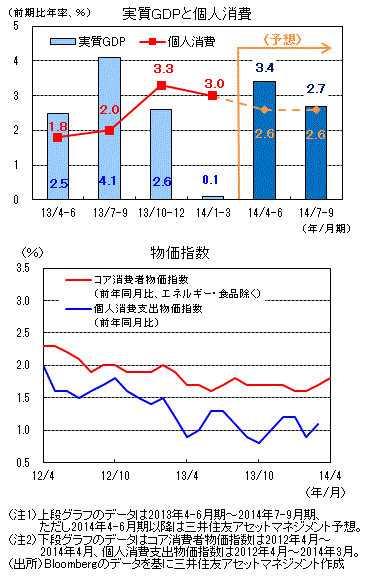
3.今後の市場見通し
2014年1-3月期の実質GDP成長率は、年末年始の寒波の影響などを考慮した事前の市場予想をさらに下回る大幅な低下となりました。しかし、4月以降の経済指標をみると、非農業部門雇用者数は過去分の上方修正も見られ、失業率の安定的な低下に必要と考えられる前月比+15万人~20万人を上回るペースでの上昇が続いています。このほか、景況感も年初来で一時的な低下は見られていたものの、中立水準の50ポイントを割ることなく足元では上昇してきており、先行きについても新規受注指数などからみて堅調と考えられます。一方、物価は足元で上昇率が緩やかに加速しているものの、FRBの長期目標とする水準を下回っており、FRBが指摘する雇用の質(時間当たり賃金の上昇や長期失業者数の割合など)の改善とともに、FRBが低金利政策を維持する要因となっています。今秋にも終了すると見込まれるQE縮小後の利上げのタイミングについては、雇用や物価の回復度合いなどから2015年後半以降と見る向きが大勢となっています。



