【デイリー No.1,794】最近の指標から見る日本経済(2014年2月)
2014年2月6日
<ポイント>
・世界経済の回復の一方、堅調な内需などから輸入の伸びが輸出の伸びを上回り貿易赤字は拡大傾向です。
・求人数の大幅増加に対し、求職者数は減少しており、労働市場のひっ迫が賃金上昇を後押ししそうです。
・12月は家具・家事用品が物価上昇に寄与し、2013年度は日銀の見通しに沿った物価上昇となりそうです。
⇒消費税増税後の経済対策や世界経済の回復基調などから、景気回復基調が維持される見込みです。
1.貿易収支は引き続き拡大傾向、生産は上昇傾向維持
①貿易統計
12月の貿易収支は▲1兆1,486億円(季節調整後)と、2011年3月からの貿易赤字が継続しました。季節調整前では▲1兆3,021億円でした。
輸出額は前年同月比+15.3%と、前月の同+18.4%から小幅に鈍化しました。品目別では、全体の14.8%を占める自動車や、鉄鋼、有機化合物が20~30%前後の伸び率となり、全体を押し上げました。一方、輸入額は同+24.7%と、前月の同+21.1%から再び伸びが加速しました。品目別では、発電燃料である液化天然ガスや原粗油などの増加が継続したほか、スマートフォンなど向けの半導体等電子部品も40%程度の伸び率となりました。
輸出を地域別に見ると、中国向けが同+34.4%と2カ月連続で30%超の伸びとなりました。一方、米国向けは同+13.0%と、前月までと比べ鈍化しましたが昨年4月からの二桁増を維持しています。今後も米国を中心に世界経済は緩やかな成長を続けると見込まれ、輸出は堅調に増加すると期待されます。
今後については、エネルギー価格や円安の程度により不透明ではあるものの、世界経済の回復を背景に、輸出の伸びが輸入の伸びを上回ることで、貿易収支は緩やかに改善に向かうと思われます。
②鉱工業生産
12月の鉱工業生産指数は前月比+1.1%と、11月の同▲0.1%(速報値+0.1%から下方修正)から上昇に転じました。業種別に見ると、はん用・生産用・業務用機械工業や金属製品工業、非鉄金属工業など多くの業種で上昇しました。一方、情報通信機械工業と繊維工業は低下しました。また、在庫指数は鉄鋼業、輸送機械工業などを中心に同▲0.4%と低下し、5カ月連続の低下となりました。
今後の生産動向の見通しを示す製造工業生産予測調査(企業の生産計画に基づく)を見ると、1月は前月比+6.1%、1月は同+0.3%と、引き続き増加傾向が見込まれています。今回の結果を受けて、経済産業省は前月に引き続き「生産は持ち直しの動きで推移」とし、判断を据え置きました。在庫の減少が続いていることなどからも、生産は増加基調を維持すると思われます。
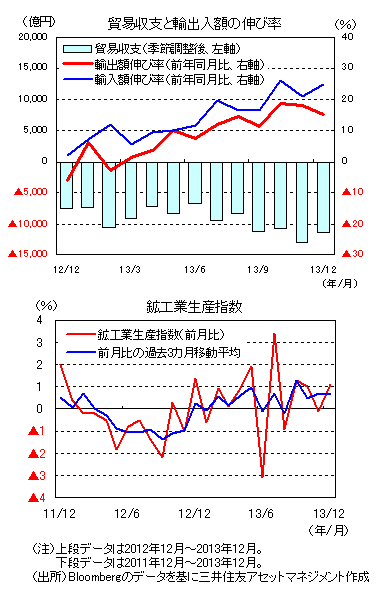
2.労働需給はひっ迫しており、賃金上昇への期待高まる
①雇用
12月の失業率(季節調整値、以下同様)は3.7%と、5カ月ぶりに4%を割り込み、一段と改善しました。また、完全失業者数は同▲20万人と大幅な減少となりました。
一方、有効求人倍率は前月比+0.03ポイントの1.03倍と、2カ月連続で1.00倍以上となりました。また。労働市場の先行きを示す新規求人倍率は同+0.08ポイントの1.64倍と、大幅に上昇しました。1992年5月(1.67倍)以来11年7カ月ぶりの水準です。有効求人数、新規求人数が前月比で二桁増となっている一方、有効求職者数、新規求職者数が減少していることから、労働需給はひっ迫しており、今後賃金の増加を後押しすることが期待されます。
②消費者物価指数
12月のコア消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比+1.3%と7カ月連続のプラスとなり、2カ月連続で1%台の上昇となりました。物価の基調をより反映する米国型コア消費者物価指数(食料(酒類除く)、エネルギーを除く)は同+0.7%と3カ月連続のプラスとなり、上昇ペースが加速しています。物価上昇の要因には、2009年2月以来プラスに転じた家具・家事用品などがあげられます。なかでもエアコンや冷蔵庫、洗濯機などの白物家電を中心に価格が上昇しました。
日銀は、1月の展望レポートの中間評価での政策委員の大勢見通しにおいて、2013年度のコア消費者物価指数は、前年度比+0.7%と見ており、日銀の目標とする物価上昇が果たされつつあります。一方、2014年度(消費税率引き上げの影響を除くケース)は同+1.3%、2015年度(同)は同+1.9%と見通していますが、消費税率引き上げの影響がどの程度消費の不振、若しくはそれによる価格上昇の妨げとなって表れるかが注目されるところです。
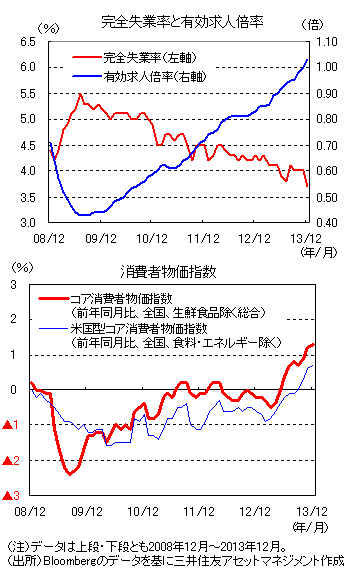
3.今後の見通し
政権交代以降でみると内需は堅調に推移してきましたが、4月からの消費税率引き上げにより内需は一時的に減速すると見られます。しかし、消費税率引き上げに伴う5.5兆円規模の経済対策により2014年度も景気回復基調が維持されると思われます。一方、今後も米国を中心に世界経済は緩やかな回復傾向が見込まれることから、外需は総じて堅調となると思われます。こうしたことから、生産は当面増加基調を維持すると考えられます。
米国ではFRBが先月のFOMCにおいて、2度目の資産購入額の減額(2013年末までは月額850億米ドル、2014年1月は同750億米ドル、2月以降は650億米ドル)を決定しました。一方、日本では昨春来の大規模な金融緩和の継続が見込まれる上、追加緩和策への期待もあり、今後も円安・米ドル高傾向となることが見込まれます。
一方で、米国では寒波など悪天候により足元のいくつかの経済指標の改善の足踏みも見られています。また中国の主要経済指標の悪化や、アルゼンチンペソに端を発する新興国通貨下落への不安などに対する投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから、株式市場や為替市場では当面神経質な展開となりそうです。しかし、国内企業の中長期的な収益改善、拡大基調に変化はないと見られ、株価は次第に回復へ向かうことが見込まれます。



