【デイリー No.1,825】最近の指標から見る中国経済(2014年3月) ~年初の指標は鈍化、全人代後に人民元の変動幅拡大~
2014年3月17日
<ポイント>
・生産、消費、投資といった1-2月累計の指標の伸びは総じて昨年12月から低下し、市場予想も下回りました。
・輸出額は、旧正月による振れに加え、香港経由の資金流入の反動もあり、1月、2月で伸びが乱高下しました。
・しかし、指標の鈍化は一時的と見られます。また、政府は人民元の変動幅拡大など、改革を続けています。
⇒物価安定と財政余力から、仮に改革路線で景気が鈍化した場合も、小規模な景気刺激策が想定されます。
1.生産、消費ともに伸びが低下、市場予想も下回る
①工業生産
1-2月累計の工業生産(実質ベース)は、前年同期比+8.6%と、昨年12月から伸びは低下し、市場予想の同+9.5%も下回りました。
主要商品の生産量を見ると、昨年10月から12月にかけて前年同月比+20%台と全体をけん引していた自動車が、1-2月累計では+12.5%となりました。鋼材、セメント、エチレンなどの素材関連、活動量との関わりが深い発電量などの伸びも鈍化しました。特に、鉄鋼業などは昨年末にかけて生産や原材料の在庫積み増しに積極的だった反動もあり、このところは活動がやや鈍化しています。
また、製造業景況感指数を見ると、昨年12月に51.0ポイントであったものが、1月に50.5ポイント、2月には50.2ポイントへと徐々に低下しました。内訳を見ると、先行きの参考となる新規受注、輸出向け新規受注はともに低下を続けています。昨年のように景気の持続的な減速を懸念するムードではないものの、3月の全人代を前に、先行きの不透明感が高まり、景況感を抑えたものと思われます。
②小売売上高
1-2月累計の小売売上高は前年同期比+11.8%と、昨年12月から伸びは低下し、市場予想の同+13.5%も下回りました。また、物価を調整した実質ベースでの伸びも同+10.8%と、昨年12月の前年同月比+12.2%から低下しています。
この間には旧正月に伴う休暇(1月31日~2月6日)もありましたが、期間中の消費の伸びは同+13.3%となりました。底堅い推移だったものの、政府の倹約姿勢が続けられるなか、特に高級料理店、贈答品などは官公庁関連の需要が伸びませんでした。
一方、昨年後半から物価の伸びは抑えられ、都市部の賃金増加ペースが再び加速するなか、中間所得者層の消費の伸びは活発でした。また、今年の旧正月の休暇中にも、旅行やレジャーといった分野の売上高は前年から大きく伸びました。
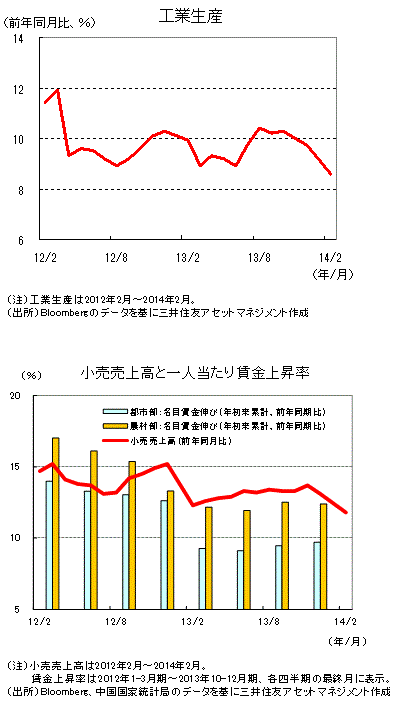
2.固定資産投資も鈍化、輸出額が1月、2月で乱高下
①固定資産投資
1-2月累計の固定資産投資(農村部除く)は前年同期比+17.9%と、市場予想の同+19.4%を下回りました。
先行きの参考となる新規着工計画は、1-2月累計で同+14.7%となりました。増加ペースは若干持ち直しましたが、まだ力不足といった感が否めず、政策の具体化が進む3月以降の動向が注目されます。
不動産開発投資の1-2月累計は同+19.3%と、昨年1-12月累計の同+19.8%を下回ったものの、高めの水準を維持しました。開発に先行する土地取引や新規着工が昨年後半に堅調だったため、今年前半は堅調な伸びが続きそうです。しかし、北京、上海や深センなど、一部の大都市では住宅価格の上昇ペースが鈍化してきました。当局の監督強化のなか、鈍化が趨勢的なものとなるか注目されます。
②貿易統計
1月の貿易収支は319億米ドル(約3.2兆円)の黒字、対して、2月は230億米ドルの赤字(約2.3兆円)となりました。収支が大きく振れたのは、輸出の伸びが乱高下したためです。輸出額は1月に前年同月比+10.6%と堅調でしたが、2月は同▲18.1%と弱含みました。
背景には、旧正月前の1月に輸出を前倒しする動きが強まったほか昨年1-3月期に、貿易の体裁をとって香港から流入する資金が急増していた(後の監督強化につながった)ことが挙げられます。輸出額の前年同月比の伸びは、今年4月~5月頃まで監督強化前と強化後を比べるため、振れやすくなりそうです。
しかし、香港を除いたベースで、2014年1-2月累計の輸出額を見ると前年同期比+2.4%と、なお底堅く伸びています。足元でも輸出が緩やかに回復していることには、変わりないと思われます。
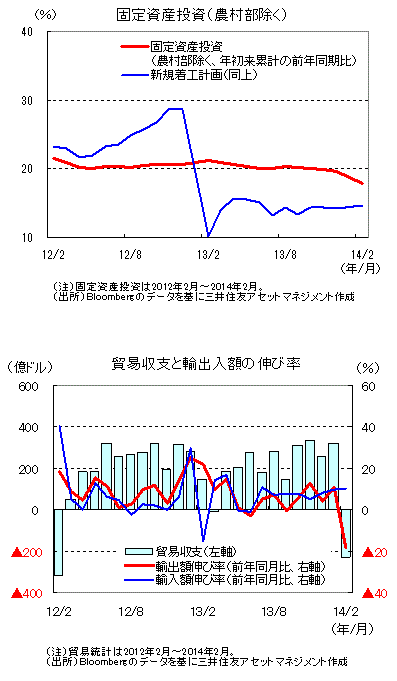
3.今後の市場見通し
1-2月の指標が予想以上に弱含んだ要因として、3月5日~13日に開催された全人代を前に、様子見姿勢が強まったことが挙げられます。加えて、経済、市場動向ともに、米国の寒波やウクライナ情勢の緊迫化といった、特殊な下押し要因の影響も受けていると思われ、今後の景気、市場動向の判断には、もうしばらく時間を要しそうです。
一方、全人代の改革姿勢は、市場から概ね好意的に受け止められています。会期中やその直後には、①人民元の対ドル変動幅拡大(1営業日当たり±1%⇒±2%、17日から適用)、②年内の預金保険の創設方針、③1年~2年のうちに預金金利を自由化する方針などが打ち出されました。市場からは、時期のメドへの言及など、想定以上に踏み込んだとの評価も聞かれます。経済に市場原理を一段と導入するに当たり、金融改革を率先して進めていることは好材料です。
また、これまでの慎重な経済運営によって、2013年の物価上昇率は年+2.6%に落ち着き、財政赤字の対GDP比も2.1%に留まったことなどは、大きな好材料です。仮に景気が下振れした際も、インフラ投資の積み増しや銀行のオンバランス貸出の促進など、小規模な景気刺激策は充分想定され、年+7%前半~半ばの成長は、維持できるものと思われます。
株価は、足元でシャドーバンキング対策が進められるなか、銀行・不動産株を中心に、上値が抑えられています。しかし、株価は歴史的にも、他の先進国と比較しても割安な水準にあります。今後の株価は中国経済や企業業績の中長期的な回復期待、国有企業の改革期待、相対的に高い成長力への評価などから、徐々に上昇基調へ戻ると思われます。



