【デイリー No.1,779】最近の指標から見る中国経済(2014年1月)
2014年1月23日
<ポイント>
・2013年の実質GDP成長率は前年比+7.7%と、政府目標(同+7.5%)を達成しました。
・12月は生産や投資が鈍化しましたが、2014年政府方針の発表前に様子見姿勢が強まったためと見られます。
・原油輸入が量、額ともに増えたことなどから貿易黒字額は減少しましたが、輸出の回復基調は続いています。
⇒2014年も7%台の成長が見込まれ、焦点は引き続き3月の全人代にかけての政策発表となりそうです。
1.2013年のGDP成長目標を達成
①実質GDP成長率・工業生産
10-12月期の実質GDP成長率は、前年同期比+7.7%となりました。2013年通年の成長率も+7.7%となり、政府目標である+7.5%を達成しました。ただし、10-12月期の成長率を前期比で見ると+1.8%と鈍化しました。2013年半ばに景気回復を先取りした生産再開があったことの反動や、年末にかけて新規の投資計画が伸び悩んだことなどが影響したと見られます。
12月単月の工業生産(実質ベース)を見た場合も前年同月比+9.7%と、11月の同+10.0%から鈍化しました。鈍化は2カ月連続です。
主要商品の生産量を見ると、発電量や鋼材、セメントなどは一段の伸びを示しており、経済活動全体が減速しているといった状況ではないと思われます。こうしたなかで伸びが鈍化したのは、10月~11月に同+25%台のペースで生産されていた自動車が同+22%台に若干ペースを落としたことなどが要因と見られます。
12月の製造業景況感指数を見ると、51.0ポイントと11月から0.4ポイント低下しました。内訳を見ると、先行きの参考となる新規受注、輸出向け新規受注ともに低下しました。
②小売売上高
12月の小売売上高は前年同月比+13.6%と、11月の同+13.7%を小幅に下回りました。しかし、物価の影響を除いた実質ベースで見ると、12月は同+12.2%となり、11月の同+11.8%を上回りました。
2013年通年の一人当たり賃金(物価調整後)は農村部で前年比+9.3%、都市部で同+7.0%となりました。発展が課題である農村部で伸び悩みましたが、景気のけん引役である都市部は2013年4-6月期を底に賃金上昇ペースが回復しています。また、物価上昇は2013年も前年比+2.6%と抑えられ、消費活動の支えとなっています。
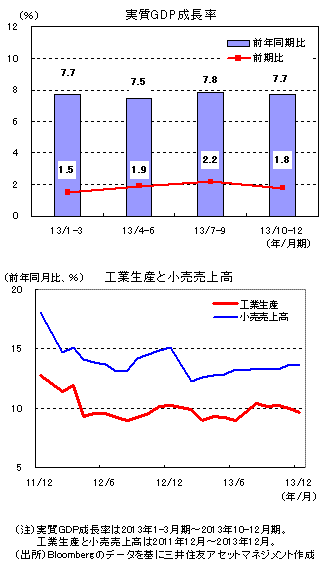
2.固定資産投資は鈍化、原油輸入などで貿易黒字は減少
①固定資産投資
1-12月累計の固定資産投資(農村部除く)は前年同期比+19.6%と、1-11月累計の同+19.9%を下回りました。先行きの参考となる新規着工計画も、1-12月累計で同+14.2%と、緩やかな鈍化が続きました。
2014年を占う上で、新規着工計画が同+20%前後で安定するかが注目されます。中国の景気減速局面では、政府のインフラ投資が対策の大きな部分を占めることが多く、実際に支援決定から数カ月後には同計画の伸びが加速します。近年は4兆元の景気対策を始めた2009年の1-5月累計が同+95%台、景気減速の歯止めにインフラ計画を前倒しした2012年の1-11月累計が同+28%台などとなりました。
不動産開発投資の1-12月累計は同+19.8%と、1-11月累計の同+19.5%を上回りました。土地取引や新規着工の伸びはなお高く、不動産開発は今後も堅調と見られます。
②貿易統計
12月の貿易収支は256億米ドル(約2.7兆円)の黒字となりました。原油の輸入が膨らんだことなどから、黒字額は11月を下回りました。
輸出額は前年同月比+4.3%と、11月の同+12.7%を下回りました。昨年12月実績が高かった反動に加え、2013年に虚偽貿易の取り締まりを強化したことなどが影響しました。ただし、10-12月期の輸出の伸びや貿易黒字額は7-9月期を上回り、回復基調は続いています。
輸入額は同+8.3%と、前月の伸びを上回りました。原油の輸入額が210億米ドルと、1年7カ月ぶりの水準に達した(輸入量は5カ月ぶりに過去最高を更新)ことなどが、輸入総額を押し上げました。
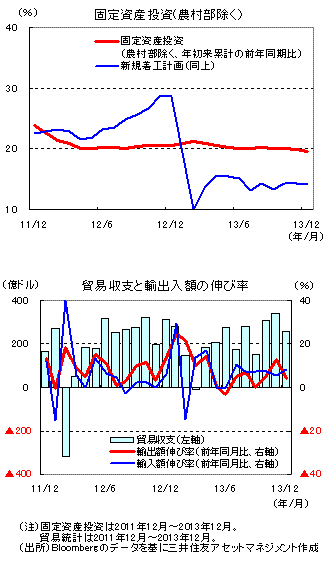
3.今後の市場見通し
旧正月の日程などのため、主な経済指標の次回発表は3月となります。市場はこの間、3月の全人代(5日から10日間程度の開催予定)や、同会議までの政策発表に注目しそうです。また、消費活動が持ち直してきたこと、物価も安定していること、綱紀粛正が昨年ほどの下押し材料にならないと見られることなどから、春節休暇中の小売売上高は底堅い伸びが期待できそうです。加えて、米国など先進国景気の復調が見られるなか、2014年は外需も中国景気を支える要因となりそうです。
市場では、2014年通年のGDP成長率を実質+7%台半ばと見る向きが大勢です。また、利上げなどの金融引き締めの可能性は限定的で、人民元も緩やかな上昇が続くとの指摘が多く聞かれます。仮に景気が下振れした際も、習近平体制の進める「新都市化」は、都市型交通、環境、衛生分野などでインフラ投資を積み増すことによって、構造改革と景気の下限維持を両立しやすいとも言えます。こうしたことから、2012年~2013年前半のように景気減速懸念が続くことは回避できそうです。
株価は足元ではIPO再開による市場の需給悪化懸念などから下落していますが、歴史的に見ても、他の先進国と比較しても割安な水準にあります。今後の株価は中国経済や企業業績の中長期的な回復期待、相対的に高い成長力への評価などから、徐々に上昇基調へ戻るものと思われます。



