【デイリー No.1,854】最近の指標から見る豪州経済(2014年4月)
2014年4月25日
<ポイント>
・失業率の低下、雇用者数の増加が見られましたが、正規雇用が減少するなど、改善は緩やかに留まります。
・小売売上高の伸びがやや鈍化しましたが、消費は今後も住宅価格上昇の恩恵などにより、景気を支えそうです。
・中国向け資源輸出が伸び悩んだ一方、日本、台湾向け資源輸出が急増し、貿易黒字が続きました。
⇒年前半の物価上昇が警戒されていましたが、今月の指標を踏まえると金融政策は今後も据え置かれそうです。
1.雇用統計は強弱入り混じり、小売売上高はやや鈍化
①雇用統計
3月の失業率は5.8%と、2月から低下しました。ただし、2月の結果は6.0%から6.1%へと修正されました。また、労働参加率が2月の64.9%から3月は64.7%へと低下しており、状況は強弱の要素が入り混じったものと言えそうです。
3月の雇用者数も前月比+1.8万人となり、市場予想(以下、予想はブルームバーグ集計)の同+3千人は上回ったものの、内訳を見ると正規雇用が同▲2.2万人、パートタイムが同+4.0万人となるなど、改善は緩やかに留まっています。
また、3月は企業の先行き見通しも、より慎重になりました。資源部門以外の企業活動は伸び悩んでおり、新規採用への意欲は引き続き低調です。今後も雇用者数の増加は引き続き緩やかに留まり、失業率の持続的な押し上げや賃金上昇など、雇用情勢の全面的な回復が見られるにはしばらく時間を要すると思われます。
②小売売上高
2月の小売売上高(季節調整済)は前年同月比+4.9%と、1月の同+6.2%を下回りました。2月は前月比でも+0.2%と、1月の同+1.2%ほどの伸びは見られませんでした。先行きの参考となる消費者信頼感指数を見ても、4月は99.7ポイントと、3月の99.5ポイントに続き、やや低調(統計開始以来の平均値は101.8ポイント)です。
昨年後半から小売売上高の伸びが急回復した背景には、住宅価格や株価の上昇による資産効果、物価上昇による金額の押し上げなどがあったと見られます。雇用市場の改善が緩やかなことなどを反映して、伸び幅は今後徐々に緩やかなものとなりそうです。しかし、当面は好調な住宅市場の恩恵を受け、消費が景気を支える要因となることは変わりないと見られます。
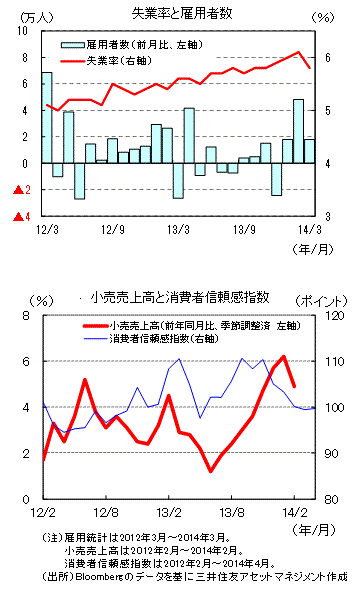
2.貿易収支は黒字が継続、物価は市場予想を下回る
①貿易統計
2月の貿易収支は、12億豪ドル(約1,100億円)の黒字となりました。
中国企業向けの鉄鉱石価格は3月末時点で1トン当たり113.5米ドルと、昨年12月から約2割下落しています。また、2月は中国向けの鉄鉱石、石炭の輸出量も急減しましたが、その一方で日本と台湾向けの輸出が急増した結果、ほぼ前月並みの貿易黒字となりました。
②消費者物価指数
1-3月期の消費者物価指数(CPI)は前年同期比+2.9%、前期比+0.6%となりました。それぞれ市場予想を0.3%、0.2%下回りました。
豪州統計局によると、CPIの集計対象は「貿易で代替可能な分野(約4割、為替の影響が大きい)」と「不可能な分野(約6割、主に国内要因で変動)」の2項目に大別できます。うち代替が不可能な分野は、これまで前年同期比+3%台後半~4%台で推移してきましたが、この1-3月期には同+3.1%と、2009年10-12月期以来の低水準となりました。
賃金上昇が抑えられるなか、国内発の物価上昇圧力は抑制されてきています。為替など不確定な部分は若干あるものの、同指数が前年同期比で年+3%を大きく超えることは無さそうです。
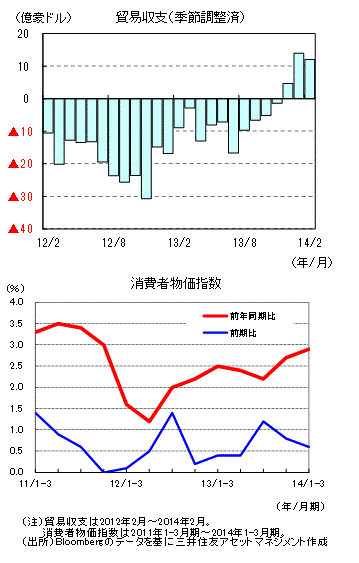
3.今後の市場見通し
昨年の豪ドルの対米ドルでの下落や住宅価格の大幅上昇などにより、2014年前半には豪中銀(以下、RBA)の想定以上に物価が上昇する、との見方も浮上していました。ただし、4月に判明した指標は概ね改善方向ではあるものの、市場が懸念していたほどの物価上昇圧力につながるものではありません。足元の物価上昇は短期的となり、RBAの目標上限である年+3%を大きく超えることは無さそうです。その後の物価は、国内賃金の抑制、住宅市場の盛り上がりの一服などに伴って徐々に落ち着くと見られ、RBAはしばらく政策金利を過去最低水準の2.5%で据え置くと思われます。
2014年通年の成長ペースは、RBAが予想するように年+3%をやや下回る程度と見られます。しかし、先行きでは資源輸出が中長期的な追い風となるほか、個人消費の底堅さなどを背景に、成長ペースは徐々に持ち直していくと見込まれます。
豪州の株式市場は、地政学リスクが一旦収まるなか、中国の景気刺激策も期待され、景気や企業業績の回復期待から緩やかな上昇基調が続きそうです。債券市場では、景気が緩やかな回復基調にあるとの見方を背景に、債券価格の上値は抑えられています。ただし、相対的に高い金利や信用力が豪州債券の需要を支え、債券価格は一進一退となりそうです。
2月以降の豪ドルは、地政学リスクが一旦収まったことに加えて、中国の景気刺激策への期待もあるなか、対円、対米ドルともに底を打ち、上昇してきました。しかし、RBAが通貨高へのけん制姿勢を再び示す可能性もあり、上値は抑えられやすいものと思われます。中長期では、相対的に高い金利水準、豪ドル建て債券の高い信用力、主要な貿易相手である中国景気の高めの成長などが下支え材料となり、豪ドルの底堅さは維持されそうです。



