「マグロ」の漁獲高規制(日本) 【キーワード】
2016年9月8日
<今日のキーワード>
「マグロ」は、寿司ネタをはじめとして、日本の食卓には欠かせない食材です。「マグロ」は、常温では腐敗や変色しやすいため、昔は珍重されていませんでしたが、冷凍技術や輸送インフラの発達により、今日では高級魚の代表格となっています。その「マグロ」に、資源枯渇の問題が発生しています。世界的な「マグロ」の需要の高まりを受けて、乱獲の問題が発生しているためです。日本はどのように対応していくのでしょうか?
【ポイント1】資源枯渇が懸念される「マグロ」
「マグロ」の漁獲高は減少傾向
■「マグロ」には、色々な種類がありますが、日本の食用として代表的なものには、「クロマグロ」、「ミナミマグロ」、「メバチマグロ」、「キハダマグロ」、「ビンナガマグロ」などがあげられます。日本は世界の「マグロ」漁獲高の3割程度、「クロマグロ」などの高級「マグロ」に限定すれば、8割程度を消費する、「マグロ消費大国」として位置づけられます。
■しかし世界の「マグロ」の漁獲量は、2003年ごろをピークに減少傾向に向かっています。中でも高級品である「クロマグロ」、「ミナミマグロ」の漁獲高は、一足早く1996年ごろをピークに減少傾向となっています。
【ポイント2】 「マグロ」が成魚になるには5年が必要
幼魚の乱獲が問題
■「マグロ」の漁獲高減少は、当然「マグロ」資源の減少によるものです。世界的に「マグロ」の需要が高まっているうえ、高値の日本市場に着目して、各国の漁船が競って「マグロ」を捕獲しているためです。
■また、「マグロ」は成熟するまでに、「クロマグロ」の例では約5年もの長い時間を必要とします。このため、幼魚段階での巻き網漁などでの乱獲が、資源減少に影響している模様です。
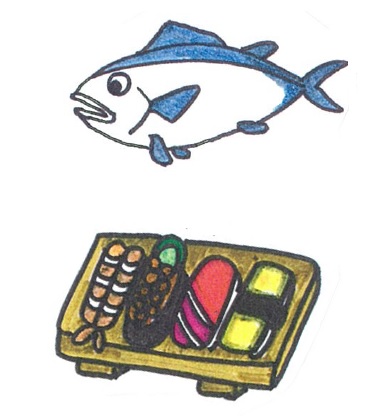
【今後の展開】 漁獲高規制を含む抜本的対策が不可欠
■世界の環境保護団体の中には、太平洋での「クロマグロ」捕獲の2年間停止を要請する声明を発表しているところもあるようです。これに対し、「マグロ消費大国」の日本は、むしろ積極的に漁獲規制ルールを設け、世界の「マグロ」資源の確保に努めようとしています。
■ ただし、9月2日まで開催されていた中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)では、日本側が提案していた幼魚の捕獲規制に関して、米国はより厳しい資源管理を求めて、合意に至ることができませんでした。「マグロ」が食卓から消えないように、早期の対応が求められています。
関連マーケットレポート
- 日々のマーケットレポート
- 日々のマーケットレポート



