「インフレ」への環境が整う?(日本)【キーワード】
2015年3月9日
<今日のキーワード>
景気が良くなるとモノが売れ、市場で商品が不足し、モノ(物)の値段つまり物価が上がります。物価が継続的に上昇する状況を「インフレ」と呼びます。逆に景気が悪くなるとモノが売れなくなり、モノの値段が下がっていきます。この状況を「デフレ」と呼びます。日本は長らく「デフレ」的な状況にありましたが、アベノミクスや異次元緩和などによりデフレ脱却への対策が進められています。
【ポイント1】物価の基調を見るには?
足元は原油安の影響でやや下振れ
■消費税や変動の大きい生鮮食品の影響を除いて見ると、日本の物価の状況はどうなっているでしょうか?消費者物価指数(生鮮食品、消費税増税の影響を除く)は、2013年4月に日銀が「量的・質的金融緩和策」を決定して以降、円安による輸入品価格の上昇などから、2013年5月に前年比横ばいとなり、それ以降は前年比でプラス基調が続きました。
■しかし、昨年秋ごろからの原油価格の急落でガソリン価格などが下落し、また消費税増税後の消費の回復にもたつきが見られたことなどにより、物価の上昇率は低下傾向になり、今年1月の消費者物価指数(同)は同+0.2%と小幅な上昇にとどまっています。
【ポイント2】日銀は、「物価は上昇基調」を堅持
円安による原材料高転嫁の動きも
■日銀は原油安などを受け物価の見通しを引き下げたものの、エネルギー価格を除く物価の上昇基調は変わらないとしています。2%の「物価安定の目標」については2015年度を中心とする期間に達成する可能性が高いとしました。
■円安により円貨建ての輸入品の価格は上昇します。加工食品などは原材料の輸入依存度が高いこともあり、原材料コストを製品価格に転嫁する動きが見られます。すでに即席麺やパスタ、冷凍食品が値上げされ、食用油や乳製品なども値上げが発表されています。
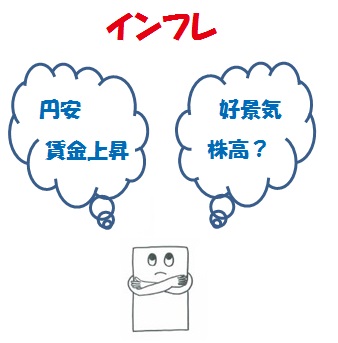
【今後の展開】「インフレ」への転換の対応策を考える時期
■「インフレ」に向けた環境は整いつつある
円安などによる企業収益の拡大が賃金上昇につながり消費が回復するという好循環への転換が期待されます。また、日米の金融政策の方向の違いから円安傾向は維持されると見られ、さらにガソリン価格に底打ち感が見られるなど、今後「インフレ」傾向が進むことが見込まれます。
■「インフレ」ではお金の相対的価値は目減り
1998年頃から10年以上もデフレ傾向が続き、一般的に将来の物価上昇期待を持ちにくくなると言われます。「インフレ」ではモノの値段が上がるため、お金の価値は相対的に下がります。一方、株式やリートなどは「インフレ」時に価格上昇が期待されます。保有資産の見直しなど、「インフレ」環境への備えを考える時期にあるかもしれません。



