ユーロ圏統合消費者物価指数(欧州)【キーワード】
2014年8月5日
<今日のキーワード>
欧州連合(EU)統計局(ユーロスタット)が毎月発表しています。EU加盟28カ国の家計における一定の消費構造(ウエイト)を基準に、モノとサービスの価格を総合したものを「統合消費者物価指数」といいます。このうち、統一通貨ユーロを採用している18カ国を対象とした指数を「ユーロ圏統合消費者物価指数」といい、欧州中央銀行(ECB)による金融政策の判断のために重要な指標です。
【ポイント1】7月の速報値は前年同月比+0.4%
2009年10月以来4年9カ月ぶりに+0.5%割れ
■7月31日に発表された「ユーロ圏統合消費者物価指数」(以下、「HICP」とする)の7月速報値によると、総合指数は前年同月比+0.4%となりました。前年同月比が+0.5%を割り込んだのは、リーマンショック(2008年9月)後、世界全体が厳しい景気後退に見舞われた影響で、2009年6月から10月の5カ月間、上昇率がマイナスに落ち込んで以来のことです。
【ポイント2】財政引き締めに伴う景気悪化が原因
2013年初めまでの景気後退の影響ひきずる
■一般に、消費者物価指数の変動は、景気の変動に対して遅れて推移する傾向があります。「HICP」の上昇率が低下したのは、2011年終わりから2013年初めにかけて、ユーロ圏経済が景気後退に見舞われ、モノやサービスに対する需要が減退したことが原因と考えられます。
■これは2009年10月に、ギリシャの財政赤字が公表数値を大きく上回ることが明らかになった「ギリシャ・ショック」に端を発します。その後、財政赤字の大きい他のユーロ圏諸国が早期の財政健全化を強いられました。厳しい財政引き締め(増税や財政支出の削減)を行った結果、財政が健全なドイツなども巻き込み、ユーロ圏全体の経済活動が縮小しました。
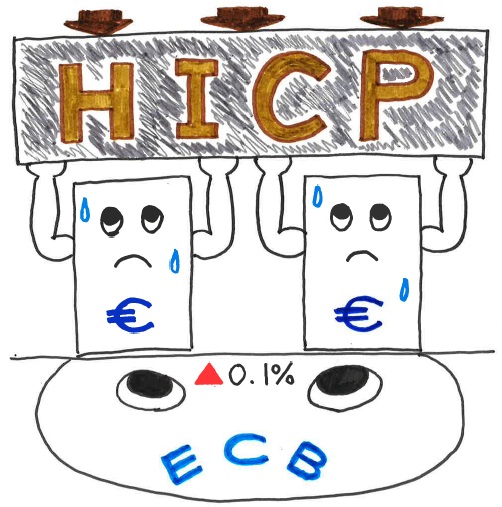
【今後の展開】金融緩和の強化で経済活動が刺激されればプラス幅拡大も
■景気回復が続きプラス幅が拡大する環境へ
ユーロ圏の景気は2013年4-6月期から回復に転じ、すでに2014年1-3月期まで4四半期連続で回復が続いています。景気回復初期は輸出回復の影響が大きかったものの、2013年終わりから個人消費などの内需が主導しつつあります。「HICP」はプラス幅を拡大させる環境が整いつつあります。
■マイナス金利導入の効果にも期待
しかし、景気回復の勢いが弱いと「HICP」の上昇率低下が続く恐れもあります。6月5日、ECBは金融機関の各国中央銀行への預金に対し、マイナス金利を導入しました。これで中央銀行に滞留する資金が民間に出回れば、「HICP」のプラス幅拡大が促されるため、効果のほどが期待されます。



