あらためて考えたい米国グロース株投資の魅力
長期投資の重要性に注目
2025年7月23日
1.米国の利下げ再開が視野に入り、グロース株に追い風
2.中長期で拡大するAI関連市場、米国ハイテク企業の業績をけん引
3.米国グロース株は上値追いの展開、長期投資の重要性を考える
1:米国の利下げ再開が視野に入り、グロース株に追い風
■2025年に第2期トランプ政権が発足して以降、矢継ぎ早に追加関税措置が打ち出され、世界経済に対する不確実性を高める要因となっています。とりわけ、4月に公表された相互関税の基本関税(すべての国に一律税率10%)や通商拡大法232条に基づいた追加関税(鉄鋼・アルミニウム製品に50%、自動車に25%など)は既に発動されており、貿易赤字の大きい国・地域を主に対象とした上乗せ関税が8月1日以降に発動される可能性が残されています。依然として、世界経済の先行きは不透明な状況にあると考えられます。
■このような状況下で、世界の株式市場、特にハイテク関連株を中心とした米国株の上昇が目立っています。6月27日には、混迷を深めつつあった中東情勢の緊張緩和への期待が支えとなり、米国株(S&P500種指数、ナスダック総合指数)は年初来の下落幅をすべて取り戻して史上最高値を更新し、その後も上値を試す展開が続いています(図表1)。
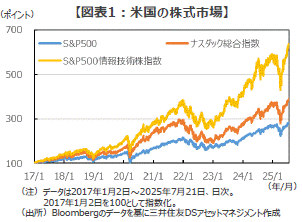
■米国株の上昇は、中長期的な業績拡大が期待されるAI(人工知能)・半導体関連など主要ハイテク企業を中心とした成長(グロース)株がけん引役となっています。生成AIの開発に不可欠な先端半導体を手掛けるエヌビディアの時価総額は7月10日、終値ベースで世界初の4兆ドル(約590兆円)を突破しました(図表2)。足元(7月21日時点)では、AI関連需要の拡大によるクラウドサービス事業の成長が見込まれるマイクロソフトも史上最高値圏で推移しており、エヌビディアとマイクロソフトの時価総額合計(約8兆ドル)は、日本の東証株価指数(約6.7兆ドル)を凌駕しており、そのスケールの大きさを再認識させられます。
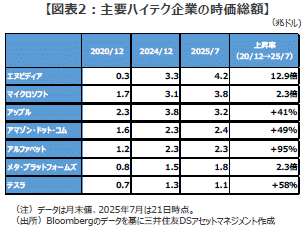
■6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨によれば、ほとんどの参加者がトランプ関税による物価への影響は「一時的もしくは緩やかにとどまる見込み」で、「年内に政策金利を引き下げるのが適切」との見解を示しています。2024年12月のFOMC以降、政策金利は据え置かれていますが、弊社では年内2回(10、12月)の利下げを想定しており、市場も同様に織り込んでいるとみられます(図表3)。既に発動済みのトランプ関税は、一定のタイムラグを経て2025年7-9月期以降に景気や雇用市場を減速させるとみられるため、仮に景気・雇用関連指標が大きく悪化すれば、9月のFOMCで利下げを再開する可能性もありそうです。
■一般に、景気指標の悪化やインフレ率の低下により、「近い将来に利下げが行われる」との見方が広がると、米2年国債利回りは低下する傾向がみられます。米2年国債利回りと、グロース株(S&P500グロース)と割安(バリュー)株(S&P500バリュー)のリターン格差(図表4)を確認すると、金利の低下局面ではグロース株が優位となり、金利の上昇局面ではバリュー株のパフォーマンスが相対的に優位となる傾向がうかがえます。
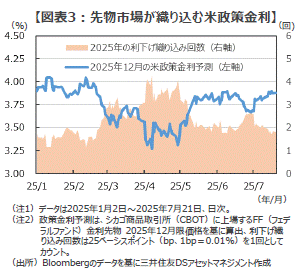
■ハイテク関連に代表されるグロース企業は、現在よりも将来により大きな利益を生むと見込まれるため、金利の低下によりそうした将来の利益を現在の価値に換算するための割引率が低下すると、将来得られるキャッシュフロー(現金収入)の価値が一段と高まり、企業価値(株価)が上昇する傾向があります。また、AI関連市場のように、景気循環に依存せずに構造的な成長が見込める点が、景気減速が懸念される局面において、相対的に魅力度が高まることも考えられます。
■トランプ関税がインフレ再燃につながり、利下げが先送りされるリスクには留意が必要ですが、6月の消費者物価指数など米国のインフレ指標は比較的落ち着きを示しており、現時点では過度な懸念は不要とみられます。
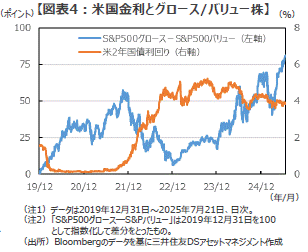
2:中長期で拡大するAI関連市場、米国ハイテク企業の業績をけん引
■前述の通り、米国株の上昇は、中長期的な業績拡大が期待されるAI・半導体関連など主要ハイテク企業などのグロース株がけん引役となっています。
■米オープンAI社が2022年11月に対話型生成AI「ChatGPT」を公開した後、わずか2カ月でアクティブユーザー数が1億人を突破し、大きな注目を浴びました。それから約2年半の月日を経て、生成AIは情報検索や文章の要約などの簡単なテキスト生成から、写真やイラスト、音声や音楽の生成など、プライベートやビジネスを問わず幅広い場面で活用されるようになりました。
■AI関連需要がけん引する形で、米国の主要ハイテク企業の好業績が続いています。トランプ関税の影響などを受け、2025年4-6月期の増益率(純利益ベース)は、S&P500(指数採用企業)で前年比+7.0%に減速する一方、ハイテク企業を中心とした情報技術株指数で同+17.8%と、2ケタ成長が続く見通しです。
■半導体の受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)が7月17日に発表した2025年4-6月期決算によれば、主要顧客であるエヌビディア向けなどにAI関連需要が大きく伸長し、純利益は前年比+60.7%の3,982億台湾ドルとなり、四半期ベースで過去最高益を更新しました。好調な決算を受け、同社の2025年増収率見通しは20%台半ばから+30%前後(米ドルベース)へ上方修正されました。
■今後について、トランプ政権が検討している半導体関連製品向けの追加関税措置の動向は留意点ですが、AI半導体の対中輸出規制が一部緩和される見通しとなるなど前向きな動きもみられます。今後公表される米国の主要ハイテク企業の決算においても、AI関連需要の拡大に支えられた力強い利益成長が期待できそうです。
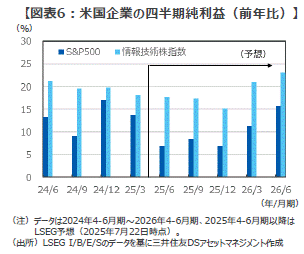
■また、企業の生成AI活用も急速に拡大しており、ITインフラとして重要なデータセンターへの投資や新しいサービス、デジタル広告など幅広い分野で市場が拡大していく見込みです。特に、AIの活用による省人化や生産性の改善へのニーズが強いようです。
■私たちの生活に欠かせない存在になりつつある生成AIの市場規模(ハードウェア、ソフトウェア、サービスなどの関連売上高)は急速に拡大すると予想されています。Bloomberg Intelligenceの調査によれば、2025年の生成AIの市場規模は3,139億ドル(前年比+46%)となり、2032年には約1.8兆ドルまで拡大すると予想されています(図表5)。
■生成AIの進化が加速する中で、一定の範囲、条件下で人間の具体的な指示なく自律的に判断し行動する「AIエージェント」が注目を集めています。AI技術のさらなる進化により、市場拡大余地は一段と高まりそうです。
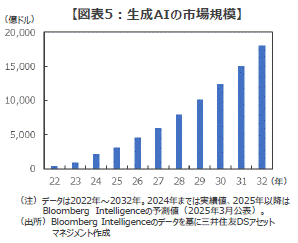
■トランプ大統領は2025年1月、オープンAI、ソフトバンクグループ、オラクルが共同で、AI向けデータセンターなどに計5,000億ドル規模を投じる「スターゲート」プロジェクトを公表しました。その後、トランプ大統領はAIに関する規制緩和を指示する大統領令を発表し、「国策」としてAI関連の民間投資を呼び込む方針を示しました。米国の強みは、生成AIの基盤技術を支える大規模言語モデル(LLM)、大規模なデータセンターとそれを支える電力インフラ、そしてAI開発に不可欠な先端半導体にあると考えられます。今後もAI関連市場の成長を支援する政策が打ち出されることで、米国のAI分野におけるリーディングポジションは容易には揺るがないとの見方が大勢のようです。
3:米国グロース株は上値追いの展開、長期投資の重要性を考える
■主要な米国株指数に10年間投資した場合の実績トータルリターン(図表7)を確認してみます。例えば、2025年6月まで10年間投資した場合の年率リターンは、S&P500情報技術株指数が+23.2%、ナスダック総合指数が+16.3%となり、S&P500(+13.6%)を上回っています。主要ハイテク企業を中心とした米グロース株が上昇基調に回帰していますが、投資期間をできるだけ「長期」とすることで短期的には大きな値動きが均され、相対的に有利なリターンを安定的に獲得する確率を高めることができそうです。
■米国グロース株の真価は、高い利益成長率と景気循環に左右されにくい構造的な成長力にあります。2020年の「新型コロナショック」や2022年の世界的なインフレ懸念など、マーケットの一時的な調整局面は幾度となく訪れましたが、優れた成長企業は新市場の開拓や技術革新によって業績を拡大させ、長期的にはその企業の利益成長が株価に反映されるものと考えられます。
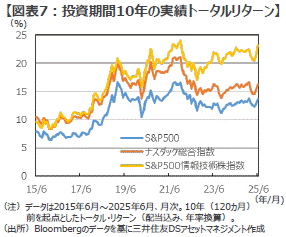
■「株主から集めた資金を活用してどれだけ効率よく利益を稼ぎ出しているか」を示す財務指標である自己資本利益率(ROE)を確認すると、主要国の中でも米国が相対的に高く、中でも主要ハイテク企業で構成される「情報技術」の高さが際立っています(図表8)。景気サイクルを超越した「構造的成長企業」は、成長性や収益力の高さから、株価純資産倍率(PBR)といった株価評価が相対的に高まる傾向があります。
■トランプ政権の高関税政策などを懸念し、4月上旬には米国の株式・債券・自国通貨が揃って下落する「トリプル安」が生じ、米国資産からの資金逃避が懸念される局面もありました。しかし、その後の株価の順調な回復を見る限り、長期視点で米国グロース株を資産ポートフォリオに組み入れ、長期にわたり保有を続けることが、効率的で有利な資産形成につながると言えそうです。
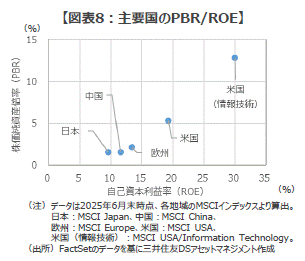
まとめに
トランプ関税による世界経済の不確実性が残る中、米国の利下げ再開が視野に入りつつあります。世界経済の減速懸念がくすぶる中でも、米国の主要ハイテク企業はAI関連需要がけん引し、好業績が続く見通しです。構造的な成長が期待される米国グロース株に投資する際には、短期的な株価変動に一喜一憂せず、長期保有を心掛けて資産ポートフォリオに組み入れることが重要と考えられます。
※個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。
シニアマーケットストラテジスト
久髙一也(ひさたか かずや)
関連マーケットレポート
- 日々のマーケットレポート
- 日々のマーケットレポート



